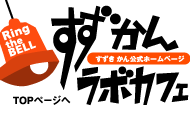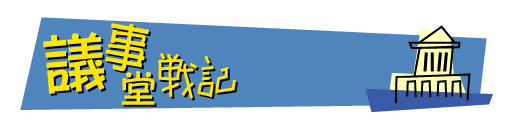2006年11月29日 教育基本法に関する特別委員会那谷屋正義君今、国民に、教育にもっと税負担を掛けるべきだということ、そうした決意ということを言ってお聞かせいただけたのかなというふうに思うわけでありまして、もう今は本当にこうした教育の問題がどんどんどんどん出てくる中で、教育予算を増やすということ、そのことについてはもうほとんどの国民が賛成するのではないか、賛成していただけるんではないかと。 毎年、私も前は教員でありましたから、毎年この予算編成の時期になると教育予算の拡充に向けていろいろと署名を行うんですけれども、その署名がやはり毎年大量の、たくさんの方に協力をしていただき、それを市議会ですとか、あるいは県議会の方に持っていく。そうすると、これだけの署名にはやはりかなわぬということで、やっぱりどんなに苦しい財政の中でも一定、教育の予算をはたいてくれるというふうな状況になるわけでありますから、そういう意味では、是非この部分については堂々と胸を張って頑張っていただかなければいけないというふうに思うわけであります。 一つ、夕張市の問題、財政再建団体になった夕張市の再建計画が実施されると、七校ある小学校が一校に、そして四校の中学校がまた一校にということで減らされるわけであります。こうしたことは、この部分について、教職員の給与というのはまたちょっと別な話だと思いますけれども、そういう意味で、再建団体になったことによって学校が統合される、しかも七校が一校にというような状況は、やはり大人社会の不始末のしわ寄せを子供が背負わされているんではないかというふうに思うわけでありまして、これは非常に容認し難い状況であります。 そういう意味では、この教訓からしても、自治体間の財政力格差が教育の格差につながらないようにするべきではないかというふうに思うわけでありますけれども、いかがでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)夕張市の現状については、私もいろいろお聞きをしてみますと、平成二十二年までに先生がおっしゃったような状況になるようでございます。本当に私はこれはひどい話だと思いますね。 やはり地方分権、地方自治と言う限りは、適切な理事者を選んでもらわなければならない。それと同時に、それをチェックする市議会の立派な議員さんを選んでもらって、それをチェックをするという機能が欠けているとこういうことになるということなんですね。 ですから、私たちがやれることは、できるだけ地方自治体の格差が生じないようにということは、もう人件費のことは先生別だとおっしゃったからここでは触れませんが、例えば文部科学省が持っておる予算だと、学校が一つになっちゃったらやっぱり通うのは大変ですからね、スクールバスの補助をするとかね、そういうことは私たちはやりたいと思いますが、多くの納税者の立場から言うと、不始末をした自治体のためになぜそこに集中的にお金が入るんだと、こういうことになっちゃうんですよ。だから、しかし、先生がおっしゃったように、児童には何の、投票権がないんですから、そこは私どもの予算の範囲の中ですが、私はできるだけのことをしたいと思っております。 那谷屋正義君是非、そうした御努力をお願いしたいというふうに思います。 そうした教育予算のことについて、ここで民主党の財源確保法というのが、ここでそういう案が出されているわけでありますけれども、この部分については正に、今いろいろと官房長官を始め答弁されましたけれども、やはりここで一つの勇気と決断が必要ではないかというふうに思うわけでありますけれども、そのことが時代の要請ではないかというふうに思うわけでありますが、では民主党の方について明快な答弁をよろしくお願いします。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 財源確保法というアイデアを更に進化をさせまして、私ども教育振興法、学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律という法律をこの参議院に提出を既にさせていただいているところでございます。 私どもは、これは日本国教育基本法の十九条あるいは二十条で教育の振興そしてそのための予算の確保ということを明記をいたしておりまして、それを受けて、日本国教育基本法とともにこの教育振興法でもって財源の確保そして環境の整備の充実ということを図っていきたいというふうに考えているわけでございますが。 今、正に夕張のお話が出ました。こうした事態には、やはり学習権というのはもう一人一人の子供たちに完全に保障されなければいけない、そのために国家というものがあるんだということで、日本国教育基本法の七条の三項では正に国の最終責任ということを規定させていただいているわけでございます。 今御紹介申し上げました教育振興法の第三条の第四号というのがございまして、そこは「安全かつ容易な通学のための諸条件を整備すること。」という条項を入れております。これは、例えばフィンランドなどでもそうでありますが、一定の時間の中に、通学時間の中に学校がなければいけないと、こういうことを規定しておりまして、それができない場合はスクールバス、さらには個別の輸送機関による補助等々も規定している例なども参考にして、きちっと容易に通学ができる条件を整備することということを国が定めます学校教育の環境整備のための基本方針に盛り込んで、このことが実現されるように計画を作り、そして予算が確保されると、こういうふうなことになっております。 先ほど来、総人件費改革と教育振興の問題が議論がなされておりますが、この正に教育基本法の特別委員会でこの議論をさせていただいていること、これ極めて重要な政策論争であります。その中身をよく国民の皆様方に御理解をいただく今このプロセスが行われていまして、非常にいいことだと思いますが、確かに北欧などの場合は、これは税金も大変に高い。要するに、高負担そして高満足といいますか、高福祉の国づくりが行われているわけであります。 もちろん、アメリカ型の国づくりを目指すのか北欧型の国づくりを目指すか、ここのもちろん議論はありますが、アメリカ型を仮に選択をするにしても、教育費についてはアメリカ・レベルにも達していないということは、まずこれは国民の総意として是正をすべきではないかと。すなわち、二〇〇三年の日本のGDPに占める公財政支出というのは三・五%でございます。米国は五・四%で、二%の開きがGDP比率においてあるわけですね。アメリカはじゃ高負担の国かというと、決してそうではないというふうに思っておりまして、まずはそこまでは、これ大体OECDの平均にも沿うわけでございまして、そこまでは引き上げていくというのが妥当ではないかというのが、これは我々の党の考え方でございます。 もちろん、違う考え方もあることは承知をいたしておりますが、ここは正に国民の皆様方に御議論をいただければというふうに思いますが、今教育現場で起こっているいじめの問題、じゃこれに対してどういう対応をするのかということの有効な解決策の一つに、例えばスクールカウンセラーを増強するということがあります。 これは今非常勤ですし、そして十分に配置されている学校がまだまだ少ないという事態があります。スクールカウンセラーを増やしていくという上でも教育の予算、人件費というものは掛かってまいりますし、それから関東のある県では、今民間の景気が若干良くなる中で教員の採用内定者が辞退をするという事態が今多く発生をしております。そのようなこととか、あるいはキャリアカウンセラーとかITのサポートとか、あるいは学校経営に十分な能力を持った人材を登用するとかいろいろな、教員の質を上げていくということと教育現場における人材の層を厚くしていくということのためには、やはりアメリカ並みの教育費は税金を投入をすべきではないかというのが我々の考え方だということでございます。 以上でございます。 |