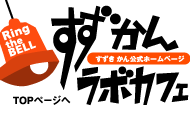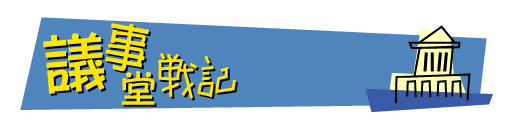2006年11月24日 教育基本法に関する特別委員会福山哲郎君民主党案、民主党案は、国が最終責任を有するという話、それから知事に権限を渡すという話が今の非常に不安定な文部行政の中で一定の役割を果たすという認識の下に民主党案は作られていると思いますが、そのことについて、民主党案の真意というか、思いをお述べをいただけますでしょうか。 西岡武夫君お答えいたします。 私ども民主党の日本国教育基本法案におきましては、国が最終的に普通教育についての責任を負うということを明記をいたしております。ここが実は、まあ伊吹大臣とは、今の御議論とかその他、若干違うところもありますけれども、おおむね、多分本音は同じお考えではないかなと私は思っているんですけれども、残念ながら、伊吹大臣は前の内閣の提出された政府の教育基本法案をひっ提げて、まあ心ならずもひっ提げて御答弁になっておられるんで、大変ある意味ではお気の毒だなと思っているんでございますけれども、そこが民主党の私どもの案と政府案と大きく異なるところでありまして、確かに言葉の上では国と地方とがそれぞれ役割分担をしてと、それは言葉としてはちょっと美しく聞こえます。しかし、いろいろな問題が起こったときにだれが最終責任を持つのかということになりますと、全く現行法においては、教育基本法はもとより、関連の教育関係法案においては全部不鮮明になっている。これを明確にするということが、私どもが今回、日本国教育基本法案の中で国が最終責任を負うということを明記した最大の理由でありまして、是非この点につきましては政府におかれてももう一度検討をし直していただきたいという最大の問題点でございます。 それと、立たせていただきましたついでに申し上げますけれども、先ほどの不当な支配ということにつきましても、先ほどの委員と大臣との議論をお聞きしておりましても、こういうある意味では幾ら議論してもなかなか通じ合わない不毛な議論のような感じを私は受けたわけでありまして、私ども民主党案におきまして不当の支配ということをあえて削除いたしましたのは、第一に、教育という大変日本の将来を決定する重要な問題、そして子供たちの未来を決定する基本的な問題について、不当な支配という言葉が教育基本法の中になじんだ言葉だろうかという、そういう感じもありまして、まずなくしました。 それともう一つは、不当な支配という場合の不当ということについての解釈ですけれども、どこから見たらどれが不当なのか、これがなかなか分からないわけですね。こういうことで教育現場が混乱するということが長いこと、昭和三十年代、四十年代、五十年代にかけて続いたわけであります。その経緯を私自身はずっと体験をしておりますので、ここは明快に国の責任と、そして日常の教育行政の責任と、そして学校現場における学校の理事会制度を創設して日常の学校の運営についての責任を明確にし、また、地方の教育行政については教育監査委員会というものを設けてという仕組みをつくることによって、不当な支配というような文言は不必要であって、最終的には選挙によって選ばれる国会議員また首長の皆様の責任が取られると、このように考えて日本国教育基本法案は構成されていると御理解をいただきたいと思います。 鈴木寛君第二点目の知事に権限が移るという云々の議論についてお答えを申し上げたいと思います。 伊吹大臣少し誤解をされているところもありますので、提案者の方から民主党案をきちっと御説明申し上げたいと思いますが、水曜日の御答弁でも申し上げましたように、今現在は、小学校、中学校におきまして、そこで教えておられる教員の人事権は県の、県の教育委員会に所属をいたしております。私どもの案では、小学校、中学校につきましては、これは市立あるいは区立、町立でございますから、それは知事にではなくて、市長さん、区長さん、町長さん、ここに移すということを言っておりますので、まずその点はきちっと明確にさせていただきたいというふうに思います。それで、県立高等学校につきましては、これは県立でございますから知事さんが行われると、こういうふうになるということはまず御理解をいただきたいというふうに思います。 それで、そもそも一九五六年の以前と、そして、すなわち一九五六年というのは地方教育行政法が作られて、要するに教育委員会法が廃止されたと、そういう年でございますが、それ以降で、元々の日本に教育委員会を導入した精神あるいはその精神を実現をするための制度、担保するための制度論というのはもう本質的に変わっているわけですね。 六十年ぶりにこの教育基本法をきちっと議論をし直して現場にきちっと対応し得る教育行政制度をつくるという観点に立ち返りますと、そもそも、ここに私ども、教育基本法ができたときのそのコンメンタール持ち合わせておりますが、住民を広く教育行政に参加させると、これが重要なんだということであります。それから、従来の官僚的な画一主義、形式主義の是正、あるいは公正な民意の尊重、教育の自主性の確保、教育行政の地方分権云々、これが教育刷新委員会でもきちっと大綱としてまとめられております。 このことをきちっと現状において実現をされるためには、正に教育現場そのものに学校理事会ということで、正に住民をレーマンコントロールの観点から参加をさせて、そして、まず自主性と民意の尊重ということを行っていくと。 今はもう事実上、完全な官僚による画一的な支配が行われているわけでありまして、ここをどういうふうに正していくのかという観点で申し上げると、正に今、現状においては、正に民意によって選出をされている、そして一番教育現場に近い基礎自治体の首長さんに人事権を付与して、そして現にいじめの問題などで保護者の皆さんがどこに行っていいか分からないと、門前払いを食らってしまう、たらい回しにされてしまうと、こうしたときに、きちっと市長、区長に直接事態の改善を求めるような制度にすることによってワークするだろうと。 そして、もちろん区長、市長が法律に基づいて適正なことを行うことは、これは当然でありますけれども、万が一この政党、党派的な介入があってはこれはいけませんから、教育委員会を教育監査委員会ということに発展的に改組をして、そしてこの教育監査委員会は私どもがこの参議院に提出をさせていただきました地方教育行政の適正な運営の確保に関する法律、正に新地方教育行政法と言ってもいいと思いますが、ここの中で、選挙管理委員と同じように地域の議会でこの人選は行っていくということで、完全に民意を反映した民主的な組織、そもそもの教育委員会を導入したときの教育刷新委員会の大綱の正に基本に立ち返った制度設計をさせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 |