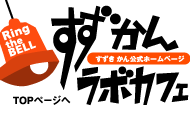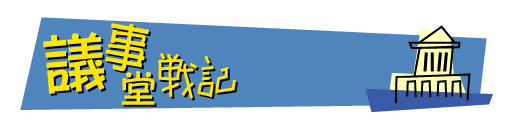2007年5月22日 文教科学委員会鈴木寛君民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。 本国会は教育改革国会ということでございます。政府からも教育三法が提出をされましたし、私どもも、日本国教育基本法案を始め、それを実現を確実にしていくための法案を出させていただいて、この文教科学委員会で議論を深められますことを大変意義深いことだというふうに思っております。 まず、総理にお伺いをしたいと思いますけれども、教育改革、いろんな議論があります。教育再生会議も行われておりますし、国会でもいろんな議論がありますが、その教育を良くしていく根本ですね、これは何だというふうに考えておられるかというのを是非議論をさせていただきたいんですが。 私は、やはり教育再生の王道というのは、現場に、教育現場に優秀な人材を大量に十分に投入をして、そしてその教員あるいはその人材に思う存分その力を発揮してもらうと、もうそのこと以外にないんだと、こういうふうに私は考えておりますけれども、総理はどのようなお考えかをお聞かせをいただきたいというふうに思います。 内閣総理大臣(安倍晋三君)私も委員と同じように、教育も、教育は人なり、正に優秀な人材を教育の分野に投入をしていくことが重要であろうと思います。子供たちがすばらしい先生に巡り合う、そのことが本当に私は教育にとって一番大切なんだろうと、こう思うわけでございます。と同時に、もちろん、私の内閣におきましては行政改革を進めております。そうしたことも踏まえながら、優秀な教員、人材を確保していきたいと思っています。 鈴木寛君御賛同いただきましてありがとうございます。 民主党が今回提出をいたしております、教員免許改革法案というのを出させていただいておりますが、その第一条でも、その目的に、質の高い学校教育を実現するためには、高い資質及び能力を有する教員が学校教育に携わることが不可欠だと、こういうことを明記をさせていただいているわけでありますが、この教員の資質の向上でございますけれども、政府のお考えは、政府の案では十年の有効期間を設けて免許を更新をし、そのごとに三十時間の講習を受けると、こういうことが明記をされておりますが、これは別に悪くはないんですけれども、これは既に都道府県で十年経験者研修というのが行われていまして、そのことを法律上追認をすると、こういうことにすぎないんではないかなと、こういうふうに思います。これだけではやや私は不十分なんではないかと。 是非議論すべきは、そもそも今、教員実習というのが日本では二週間から四週間ぐらいしか行われていないというのが実態であります。そして、二万人が大体一年間に新しく教員になる数なんですけれども、教員免許というのは二十万人弱ぐらい出ているわけですね。結局、二十万人を受け入れなければいけないので、まあ言い方は悪いですけれども、少しこの教育実習が薄くなっていると、少しどころか私は大いにというふうに思いますが、ここを何とかしなければいけないのではないかと。 で、この国会でも、あるいは最近は新聞、メディアでも、教育世界一、これはフィンランドでございます。フィンランドを見ますと、授業時間は必ずしも日本より多くない、にもかかわらず学力世界一だと。その理由は幾つかありますけれども、やっぱり一つ重要なポイントは、そもそもフィンランドの先生は全員修士課程を終わっておられて、しかも最低でも四百時間以上の教育実習をやっておられてですね。 私は、やっぱりいいものは見習った方がいいと、やっぱりこのフィンランドに見習って、我が国も教員のレベルを、この正に教育再生を議論しているこのタイミングで修士レベルに引き上げていくと。加えて、教員実習もやっぱり一年間ぐらいやっていくと。それから、今の先生方も、八年ぐらいたったところでもう一回そういう大学院に戻っていただいて、きちっともう一回勉強し直していただくと、こういうことが必要であるというふうに思っておりまして、私どもの教員免許改革法案ではこうしたことを提出をさせていただいているわけでありますが、これは総理に、どうぞそっくりまねしていただいて結構でございますので、教員の養成についての充実、これを是非御決断をいただきたいと、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。 内閣総理大臣(安倍晋三君)ただいま委員がおっしゃったように、教員の養成を充実をさせていく、それは私は確かに方向性としては大変重要な御指摘だろうと、このように思います。 また、フィンランドにおいては、すべて先生が修士を卒業しておられるということでございます。フィンランドにおいて大変教育が成果を上げている。教育において成果を上げている。これは先生の資質がすばらしいということにもあるんでしょうけれども、また地域やクラスみんなで子供たちを育てていこうと、お互いに助け合っていこうという機運も非常に高いものがあるというふうにも承知をしているわけでございまして、そういう点からも、やはり社会総掛かりで子供たちの教育に当たっていくことは大切だなと、こう思います。 民主党案にございます教員養成の一律六年制への移行でございますが、ただ実現のためには課題も多いと思うわけであります。具体的には、現行の教員養成は短大と学部、そして修士レベルでそれぞれ教員の養成が行われています。現行の修士課程における教員養成数と教員採用数との比較においてはまだこれは大分乖離があることでありまして、直ちに対応するというのは困難であると、こう思います。 また、修士課程への移行のための財源確保や、大学の指導体制の構築が必要であります。そのための修士課程のこの受入れの学生の数を増やすためには、その予算も必要ですし、それを教える体制もつくっていかなければいけないという中において、慎重な検討が必要ではないか、こう思います。なお、大学における教員養成課程の改善を図っていくことはもちろん大切であると、こう認識をしております。 政府としては、教員養成カリキュラムの改善、そして教職大学院制度の創設などを実施をして質の高い教員の確保に努めてまいりたいと、このように思っております。 鈴木寛君これ、総理、今慎重にということでございますが、もう少し踏み込んで御検討いただけないかと。 これ、私思いますのは、やっぱり今、我々はどういうつもりで教育再生の議論をしているかと、こういうことだと思うんですね。その基本問題だと思うんですね。基本姿勢だと思うんです。すなわち、日本の教育というのは戦後一貫してトップレベルにありました。しかし、この二〇〇〇年に入って急速に、例えば読解力とかコミュニケーション能力で申し上げると、二〇〇〇年に国際学力調査でいうと八番になってしまって、二〇〇三年に十四番と、急速に落ち込んでいるわけですね。 このコミュニケーション能力とか読解力というのは、単に学力だけの問題ではなくて、正に今問題になっているいじめとか引きこもりとかあるいはニートとか、こういう問題のやっぱり根底にもあることでありまして、これを何とかやっぱり本当に総掛かりで上げていこうと。そのことは私たちも全く同じ思いで前国会から総理、大臣とも一緒に議論をしてきたと思うんです。 それで、特に中を分析してみますと、やっぱり塾に行けないお子さんあるいはスポーツ教室に行けないお子さん、今は学力だけじゃなくて体力のこの学力格差も問題になっていますよね。でありますから、公教育をきちっと立て直して、もう一回この世界一の教育立国を目指していこうではないかと、こういうことで議論をさせていただいているんだというふうに思います。 確かに、今、大体五千人弱でしょうか、修士の枠というのは。二万人ということになりますと一万五千人の枠が必要だと、こういうことで、そこについては慎重にと、こういうことなんですが、私は、だからこそ正に国会の最大の課題で、これ結局、財務省とか文部科学省にお任せをしていたんであればこの一万五千というところの定数は埋まらないと思います。しかし、そこで正に政治的リーダーシップでこの一万五千に向けて、もちろん来年からというわけではありません。しかし、大きな方針をきちっと決めて、五年とか十年とかという目標を持ってこの一万五千を埋めていこうと、こういう議論に私は是非この国会の議論をしていきたいと。 実は、この場は今日は文教科学委員会ですが、文教科学委員会は私は六年間所属させていただきましたが、この六年の間に二つの修士化というのをやっているんですよ。それは、一つは二〇〇二年にロースクールというのをつくりました。法科大学院です。これ総理も御承知のとおり、今までは法学部を出て、そして大変難関な司法試験を受けてそこから法曹、弁護士とか検事さんとか裁判官になると。これはまあ、もちろん優秀なすばらしい人徳の方も大勢いらっしゃるんですけど、余りにも過酷な司法試験によってその才能に偏りがあるということで、もっと、きちっと修士課程をまじめに通えば、まあ半分ぐらいの方々が法曹になれると、こういうことで、基本的には法曹人材というのは修士化をするということでやりました。そして、本当に大勢の方の御努力によって、今七十を超える大学に法科大学院ができて、そこで六千人の方が正に法曹を目指して頑張っておられるわけですね。とかですね、あるいは二〇〇四年にも薬剤師、これを六年制にしました。これも今、毎年薬剤師というのは八千人なんです。 ですから、その法曹人材で、法曹人材になるのは三、四千人ですけれども、しかしその枠としては六千人の枠を確保し、薬剤師についても今こうした方向に向けて頑張っているわけです。薬剤師の八千人ができて、弁護士の六千人ができて、そして今、安倍内閣、一番大事だと。私も教育、本当に大事だと思います。恐らく、国民の皆さんも裁判官とか弁護士とか薬剤師と同じように教師は大事だというふうに恐らく思っていただけると思うんです。合意いただけると思うんです。この問題にあと一万五千人、何とか取り込めないだろうかという御提案を申し上げているわけです。 先ほどお話ありましたように、今すべての大学生の数というのは三百万人いるんですよね。三百万人の中でそれこそめり張りを付けて、もちろん奨学金なんかはちゃんと、ロースクールのときもつくりましたから教職大学院向けの奨学金もつくらなきゃいけないと思います。私たちもそういう提案をしています。もちろん、お金は多少掛かりますけれども、しかし本当に今危機的にあるこの日本の教育を立て直すために、ここは是非、昔は、私は、昔いいことも悪いこともありましたけれども、やはり師範学校というのはなかなか良かったと思うんですよ。やはり戦前、戦後、先生になる、正に帝大に行くよりも東京高等師範に行くということは社会的にも尊敬を集め、それぐらいのステータスがあった、総理もそのことは御賛同いただけると思いますが。 やっぱり、そういう中で、今ほとんどのこうした専門職ですね、プロフェッショナルが六年制になっていると。この実態を踏まえて私たちは真剣に予算のことも提案をさせていただいていますんですが、もう一度、積み上げの議論ではなく、正にリーダーシップをここで発揮していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 内閣総理大臣(安倍晋三君)鈴木委員は常に建設的な御議論をされていると、敬服をする次第であります。 この修士化の問題についても、大変今委員の御議論を拝聴させていただきまして、言わばどれぐらいの専門性を求めていくかということなんだろうと、このように思うわけでございます。 修士化、まず、修士化そのものが本当にどれぐらい必要かどうかということも議論もしなければならないと、このように思うわけでございますが、いずれにせよ、レベルを上げていく、そしてその中で、やはりそのためにこの限られた財源の中でどう効果的に対応していくかという観点もあるわけでございまして、その中で我々、更にやはり検討をしていく必要があると、このように認識をしているところであります。また、フィンランドの例等も更に掘り下げておく、勉強していく必要もあると、こう認識をいたしております。 鈴木寛君慎重にという言葉を取っていただきましてありがとうございました。是非検討していただきたいと思います。 やっぱり、優秀な人材を教育現場にということだと思うんですね。それと、我々が、今どれだけの専門性とおっしゃったとおり、やはり教員の皆さんに更なる使命感を持っていただくためにも、やっぱりそれぐらいの大事な専門職なんだということを制度論、政策論からも我々が掲げていくということは非常に私は重要なことだと思いますので、是非御検討をいただきたいと思います。 総理のそうした御発言がやや曇る理由、私、分からないではないんです。と申しますのも、行革推進法というのがなければ総理ももう少し明快に前向きに検討と言っていただけるんじゃないかと思うんですけれども、実は行革推進法の四十二条の一項と五十三条の一項というのがありまして、これ国立大学の教職員を純減をする、あるいは人件費の総額を五%以上カットするという話なんですね。 確かに、ロースクールの議論をした二〇〇二年とか薬剤師の六年化の議論をした二〇〇四年には行革推進法なかったんですよ。だものですから、この国を、命の安全とか、あるいは本当に司法改革とか、その時々の重要課題をやるためのやはり人材ですからと、そういう議論ができたんだと思いますけれども、二〇〇五年に行革推進法ができてしまって、そして一律にそうした人材をカットしていくんだと。これは、後で西岡先生の方から公立学校における教員人材の話も出るかと思いますけれども、要するに、やっぱりこの行革推進法、いろんなところに、その教員の養成の現場、そして正に教育の現場、この双方に大変なひずみを生んでいるということは私は事実だと思います。 したがいまして、私たち民主党も、学校環境整備推進法の附則で、今申し上げました四十二条の一項と五十三条の一項と五十五条の三項と五十六条の三項、これは要するに国立大学と公立学校の教職員を純減をさせるという、その規定を外さないとそもそも教育改革の議論ができないのではないかという危惧を持っておりまして、ここを変えられるのは、文部科学大臣は変えられないんですよ。総理しか、この行革推進法の正に教育の部分と抵触する部分を直せるのは総理しかいらっしゃらないんですが、総理、ここについての御決断、御決意をお聞かせをいただきたいと思います。 内閣総理大臣(安倍晋三君)この行革推進法につきましては、行政改革を進めていくと同時に、これは、行政改革を進めていくというのは、機能的な政府をつくっていくということと、国が大きな言わば借金を抱えている中において、国民に対して、我々、現在政権を預かる者として責任を果たしていくためにはこの財政再建を進めていかなければいけないと。そのためにも、この行政改革を正に例外なく、聖域のない中で進めていかなければいけないと。それにつきましてこの法律で縛っているというものでございます。その中で各分野、大変な御努力をいただいていると思います。 そこで、ただ、文部大臣からも、例えば少子化によって減っていくクラスにおいても、例えば八人とか七人とか、そういう減り方をしていって、全体では例えば何クラス分、先生何人分減るけれども、学校においてそれをそのまま個々に当てはめることは難しい、困難であるという話も伺っているわけでございます。しかし、今我々は、すべての行政の分野において行政改革を行っていくという強い意志を持って努力をしている中において、今の段階で、それがたとえ教育の分野であったとしても、直ちにその変更をするということを私が申し上げるわけにはいかないと、こう思うわけであります。 取りあえずは、この行革を進めていく中において、効率化を図りながら、めり張りを付けて、何とか真に必要な財源を確保するために努力を、また人員を確保するために努力をしていきたいと、このように思います。 鈴木寛君もちろん、私たち民主党の中でも、この行革も大事、教育改革も大事、あるいはすべての国においてそうだと思うんですね。 私は、昨年一年間、民主党の中で次の内閣の文部科学大臣をやらせていただきましたが、もう大議論をしました。その結果、民主党も行革推進法、対案を出させていただく中で、しかし、やはりこの教育とかあるいは医療とか、やっぱり人の命にかかわるとか、あるいは人生にかかわるところというのは、もちろん行革も大事だけれども、公共事業とか公共調達の官製談合とかあるいは天下りを、これを完全に廃止して、これを廃止すれば無駄遣いがもっともっと減るわけですから、それを正に教育費に向けていこうではないかと、こういうことを我々は議論しました。 昨年の秋に、小沢代表を筆頭とする政策マグナカルタというところで、これ、まずは、まずこの議論の前提で確認をさせていただきたいのは、OECDの諸国が三十か国あります。三十か国の中で日本の教育費というのは三十番目だということですよね、対GDP比で。ちなみに、日本はGDPの三・五%しか教育費に使っていません。これは三十番目なんです。三十か国中三十番目なんです。 この教育費の使い方を、教育改革というのであれば、本当に今、私たちも大事だと思うんです。で、我々民主党としては、少なくとも、OECDの平均が今五・二ですから、そこに少しは近づけて、何とかOECDの国の真ん中辺りまでは、いろいろな努力ももちろんしなければいけません、それから国民の皆様方にも御理解をいただかなければいけませんけれども、このことを我が党は決めさせていただきました。これは参議院選の最大の私は論点だと思いますけれども。 これ、総理、改めて伺いますけれども、結局、やっぱり優秀な人材と、そしてその数なんです。もう一度フィンランドの例を出しますけれども、やっぱりフィンランドは優秀な人材が日本の一・六倍の割合で学校現場に投入されているわけですよ。これも結局、一人当たり教員の生徒数というのも、これもOECDの国の中で最悪のランクにあるわけでありまして、やはりこれも、正に十分な必要な予算を、もちろん効率、めり張り、先ほどその言葉しか出てきませんでしたけど、やっぱり予算の総枠を改善しないとこの問題は解決できないんではないかなと、こういうふうに思います。 これは結局、我々は教員を増やします、教員を六年制にします。総理は教員を増やすのか。先ほど有村委員に対する御答弁、よく分かりませんでした。もちろん効率とかめり張りとか、当然であります。当然でありますが、教員増をやるのかやらないのか、その点についてもう一度総理に姿勢をきちっと明確にさせていただきたいと思います。 内閣総理大臣(安倍晋三君)ただ単にこの予算を増やしていく、あるいは教師の数を増やしていくということではなくて、やはり大切なことは、本当に何が真に必要な教育の予算なのか、そしてまた教師においては優秀な人材と、そしてまた先生方が子供たちと向き合える時間を増やしていくことが大切であろうと、こう考えているわけでございます。ですから、そういう中におきまして、我々は真に必要な教育の予算と優秀な人材を確保していきたいと、このように思っているわけであります。 教員一人当たりの児童生徒数については、これはまたやはりきめ細かな指導を行うために、これまで諸外国の水準に近づけることを目標に改善を図ってきました。その結果、教員一人当たりの児童生徒数は、OECDの調査では、二〇〇〇年に小学校の二十一・四人だったものが、二〇〇六年には小学校で十九・六人と、また中学校でも十七・三から十五・三と、一応これは改善をされてきています。また、平成元年以降、生徒一人当たりの教師の数は三〇%以上の増になっているわけであります。にもかかわらず、教育をめぐる状況は厳しい状況になってきているということも我々認識をしなければいけないと、こう思います。 また、教員一人当たりの児童生徒数が比較的大きな我が国や韓国は、国際的な学力調査については上位を占めているわけでございまして、教員の数と学力との関係は必ずしも一致はしないのではないか、こう思うわけでございます。 しかしながら、もちろん、教員の質を高めていく、あるいは先生方が子供たちと向き合える時間をこれは増やしていくことは、単に学力だけではなくて、規範意識の問題等々も含めてこれは考えていかなければならないと、こう認識をいたしております。 鈴木寛君総理、今、全国高等学校長会から教科「情報」の、今必修になっているんですね、実は。これ情報科、私も以前、内閣の高度情報通信社会推進本部とか、この教科「情報」を必修にしようということをやっていた一人なんですけれども、で、この必修になってやっとIT立国に追い付くという体制ができて今日、この教科「情報」を必修から外してくれという要望が文部科学大臣、中教審のところに上がっているんですよ。 これも、結局はやっぱり十分な定数を確保できない、そうすると結局未履修になってしまうと。これもう本末転倒なんですね。今どき、どこの国にIT教育、情報教育を、必修なものをやめようと言っている国があるかと。これはもう一番やらなきゃいけない。正に本当に今悲惨な事件が、これほとんどネットが関係しています。それからいじめの問題も、携帯メールによるいじめという問題なんです。 ですから、本当に子供たちに、これは高校だけじゃなくて中学校でも小学校でも、今もう行われておりますけど、更に充実をしなければいけない一番重要な部分の一つであるにもかかわらず、こういう要望が出てきていると。これも、先ほどいろいろ工夫をしてとおっしゃいましたが、やはり工夫には限界があるんで、ある程度の人間と、人員と、そして予算を確保するということは、これはやっぱり不可欠だと思うんですね。 そういう意味で、先ほども少し御答弁にありましたけれども、文部科学大臣から既にその御説明も行っているようでありますけれども、行革推進法の五十五条の三項、これよく読んでみるともう破綻していると思うんですね。すなわち、教員数について、児童生徒数の減少に伴う自然増を上回る削減を規定されているんです、行革推進法というのは。要するに、生徒が減るよりももっと強いレベルで教員を減らしなさいと、こういうことが書いてあるわけでありまして、しかし一方で標準法というのがありまして、標準法で例えば四十人学級と決めていれば、八十一人だってこれは三人先生を置かなきゃいけないわけですね。八十一人から百二十人まではこれは三人なわけですよ。 そうすると、単純に、単純に生徒数に応じて、更にそれを上回るレベルで教員を切っていったら、情報の教員もいない、それから先ほど有村委員からも、自民党の有村委員からちゃんと提起があったように、免許外の教員に教わるという事態がどんどんどんどん深刻化するんです。このことは標準法違反なんですよ。そうですよね、大臣、文部大臣。 だから、片や標準法違反な状態と行革推進法と、これコンフリクトしているんです。こういう問題があって、もう既に行革推進法というのは破綻をしていると思いますし、あるいは人確法についても十八年度中に結論を得るという話になっています。しかし、もう十八年度終わりましたけれども、これについてどういうふうな議論があるのかということもまだ決まっていません。 いずれにしましても、今日、私、申し上げたいのは、今回正に総理が教育を掲げておられる、これは私はチャンスだと思うんですね。正に国会を挙げて、国民の皆さんの合意もいただいて、OECDの中で一番教育にお金を使わないこの日本という国をもう一度、皆さんからいただいている税金です、その使い道を、本当に、この教育改革をやろうというのは本当に国民の皆さんの総意だと思うんです。そのために、きちっとその予算を確保し、人員を確保し、もちろんただ人員を確保すればいいということを私は申し上げていないのは総理御理解いただいていると思う。ちゃんと修士にして質を上げて、教育実習もきちっとやって現場の実践力を上げていこうと。そうしなければ、今総理は答弁では子供に向かい合う時間が大事だとおっしゃいますけど、どうやって向かい合うんでしょうか、いないのに、人が。 確かに、明らかに学校現場にいろいろな大人がかかわるとすごく教育効果が上がっていることは、総理も御理解いただいておりますコミュニティ・スクール、これいろんなところでやっています、三鷹の第四小学校でも。やっぱり、ボランティアの方々がアシスタントティーチャーという形でどっと入っていただくと、それはもう明らかに教育効果上がっていますし、斜めの関係ができて、そしていじめられたときの相談相手とか、あるいは人生の希望を持つ、そのあこがれの対象に出会うとか、やはり本当に子供たちを愛する大人たちが本当に温かい輪で子供たちを包んでいく、そういう学校を本当に総掛かりでつくるということは明らかに教育的に意味がある。 その主軸になる、その中核になるのが正に学校の教員であり、そしてもちろん地域のボランティアの皆さんですけど、その大前提として、私たちは教育予算をきちっと確保し、そのことを促進する制度をつくるという、法律を作り予算を作る私たちは責任があるんだということを申し上げさせていただきたいと思いますが、是非今日の議論を踏まえて、更なる教育改革に旗を上げられる以上、きちっと形で、政策の形で示していただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございました。 |