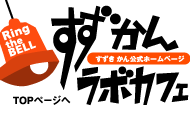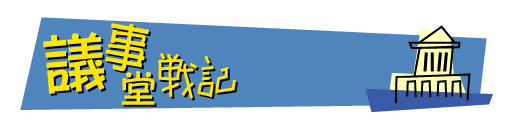2007年5月14日 行政監視委員会166-参-行政監視委員会-3号 平成19年05月14日鈴木寛君民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。よろしくお願い申し上げます。 今日は、行政改革の実施状況に関する行政監視ということがテーマでございます。実は私は、行政改革推進法ができるときの審議にも立たせていただきました。二〇〇六年の五月八日に行政改革特別委員会というのがございまして、そのときに、この行政改革推進法が成立をいたしますと、幾つか、とりわけ医療とか教育とか、非常に国民生活にとって重要な公共サービスに重大な支障が出る可能性があると、その点は大丈夫なのかということを議論をさせていただきました。やはり、当時の私どもの懸念というものは、ここに来て大いに顕在化をいたしております。 その典型例が医療の分野でございまして、例えば、行革推進法は五年間で国家公務員の総数を五%以上純減をするという目標を掲げておりますし、それから地方公務員に関しましても四・六%以上純減するように地方公共団体に要請し協力すると、こういう法律になってございます。その中で、医療公務員あるいは教育公務員も別に対象から外れているわけではなくて、正に医療公務員もここに含まれているわけでございます。 こうした中で、今公立の、まあ国公立のと言ってもいいかと思いますが、特に公立の県立でありますとか市町村立の病院、これはもう大変な今実態になっております。医師不足の深刻な状況でございます。例えば、今産婦人科、小児科の実態というのはもうこの一年間いろいろなところで、今国会でも議論をさせていただいてきましたが、例えば一人医長の問題ですね、要するに産婦人科の専門医がお一人しかいない。そういう中で大変に深刻な事態が起こり、そしてそのことが、更に申し上げると、そうでなくても大変に過酷な勤務状況の中で、産婦人科だけじゃありませんけれども、そうした公立病院の医師の皆さんあるいは看護師の皆さんは過酷な労働条件の中で頑張っておられる。そこに更に訴訟リスクあるいは刑事訴追リスクということが重なって、正に悪循環というものがもうとどまらずに、更にそこが加速していると、こういう状況でございます。 先般も、実は私、北海道の夕張にも行ってまいりましたし、それから赤平病院のいろいろな実態を教えていただきましたけれども、三年前には十八人いたお医者さんがこの四月には十一人に減っているという、限界集落という言葉がありますが、正に限界自治体というんでしょうか、限界病院というんでしょうか、そういう状況が本当に全国各地で、正に医療現場の崩壊ということになっているわけであります。 私は、やはりこの行革推進法、もちろん行政改革というのはやらなければいけませんけれども、しかしその行政改革以上に非常に重要な命の問題、こうしたことについてやはり配慮が少し足らなかったのではないかと。公立病院におきましても、やはりこの五年間に採算採算ということが本当によく言われます、赤字の垂れ流しとかですね。もちろん、それはその財務内容、経営は改善するにこしたことないわけですけれども、そんなに無駄がじゃぶじゃぶあるわけじゃなくて、特に医療現場は。本当にむしろその医療関係者の大変な献身的な御努力によって成り立っている。そこに一律にそうした効率性とか採算性ということを過度に言い過ぎている。そういう中で私は医療崩壊を加速しているという面もかなりあるんではないかと、このように思っておりますが、大臣の御見解を伺いたいと思います。 国務大臣(柳澤伯夫君)鈴木委員の方から、行革というものが医療従事者、お医者さん、看護師さん、薬剤師さん等々、そういうような人の定員の削減ということを推し進めていることが昨今非常にいろいろなところで強く訴えられている医師不足ということにつながっているんではないかと、こういう御指摘でございます。 私どもといたしましては、直接の私どもの外の組織としてのナショナルセンター、高度医療センターですね、そういうようなものであるとか、あるいは療養所といってハンセン病の方々の療養所等を持っているわけでございますが、これらにつきましてもやはり定員削減という一般的な努力を求められている一方で、また必要な分野については増員もお願いしているというようなこともございまして、これは定員の問題といたしましても、直接に医療にかかわりのある医師あるいは看護師、さらには助産師さん、あるいは薬剤師さんというようなところについては、できるだけその減員というものを避けるというようなことで、総定員の中でのやりくりというようなことをしている面が多うございます。 地方公共団体の公立病院につきましても、私ども同じような努力をしていただいているんではないかと、こういうように思いますが、総じて言いまして、今委員の御指摘の定員の問題なのか実員の問題なのかというのがまた別途にございまして、私どもといたしましては、定員の面では少なくとも今申したようなやりくりの中で努力をさせていただいていると、こういうことでございます。 鈴木寛君私、ずっとこの行政監視委員会では医療問題の議論を続けさせてきていただいております。それで、私とこの三年ぐらい、二〇〇四年辺りからずっと厚生労働省とさせていただいている議論で、医師不足問題についての認識論というのを、これいまだに決着が付いてないんですが、私は今日もあえてさせていただきたいと思いますが。 川崎厚労大臣ともさせていただいたんですけれども、昨年の予算委員会では少し改善が見られるとかいう話とか、あるいは去年の七月に、ちゃんと需給の研究会をやるのでそこでもう一回出てきたところで議論しようとかいろいろなことがやり取りがあるわけでありますけれども、厚生労働省は一貫して、全体としては足りていると、しかし偏在はあると、偏在説なんですね。私は、医師は絶対的不足説なんですよ。これでまだいまだに折り合いが付かない。 私の根拠は、例えばOECDなんかの統計を見ましても、人口当たりの数字で見るとOECD三十か国中二十七番とか、これは開業医と臨床医両方含めて二十七番ですから、病院の臨床医ということになるともっと厳しい数字になってくるわけで、この数字をもってしても、あるいはいろいろ聞こえてくる全国の医療現場の実態、あるいはもうこれは東京でもどこでもそうでありますけれども、本当にお医者さん、特に病院の勤務医の皆様方は、もう過酷な残業、あるいは徹夜明け、宿直明けでもうそのまま三十六時間ぶっ続けで仕事をしておられるとか、もう明らかに労働基準法違反の実態が、正に大臣は厚生部門と労働部門と両方やっておられるわけでありますが、どう見ても医師の労働条件から見るとこれは足らないということが絶対的不足説の根拠なんですね。 そこで、厚労省と私どもとでずっとこの論争をやっておりましたところ、最近、与党におかれまして、自民党が緊急医師不足対策特命委員会というものを立ち上げられたり、それから、公明党におかれましては医師不足問題対策本部というのを立ち上げられたり、新しい説が出てきたのか、あるいは自民党、公明党も我々の鈴木説に御賛同をいただいたのかなと思って、一生懸命三年間この同じことをいろいろな角度で言い続けてきた成果かなと思っているんですが。 さて、この期に及んで、厚生労働省の御認識は絶対的医師不足説なのか、それともやはり引き続き偏在説なのか、これはいずれでございましょうか。 国務大臣(柳澤伯夫君)厚生労働省といたしましては、従来、歴代の大臣が鈴木委員と意見交換をしているという御説明をいただきましたけれども、医師の総数においては、委員もこれはお認めになっていただけると思うんですが、三千五百ないし四千人、毎年増員が行われているということがございます。他方、そしてOECDなぞと比べますと、確かに人口当たりのお医者さんの数というものが日本は決してゆとりのあるような状況ではないと、これもまた事実であるわけでございますが。 私ども、この今の状況と、それから三千五百ないし四千人増えていく状況と、医師の今後の需要というようなものを考えたときに、やはり全体としては、今委員も御指摘をいただいたように病院のお医者さんに非常に負担が掛かっている、勤務時間が長い、そういうようなことで実際上賄いを付けているという面があるわけですが、他方、また診療所の先生方はそれほど労働時間も多くないと。こういうようなことで、今正にこの病院の勤務医の先生方に負担がしわ寄っているということは私どももよく認識いたしておりますけれども、他方で、診療所のお医者さんがそういう状況にありますと、これも一つ偏在ということを読み取れるのではないかと。 それから、地域的にも同じでございまして、医療圏ごとに見た場合には、非常に高い人口当たりの医師数が認められるところと非常に厳しいところと両方あるというようなことで、やはり地域的にもそうしたことがあるんではないか。それからまた、診療科目ごとに、余りもう長話はいたしませんけれども、偏在というか、そういうものがあるということは私ども認識をいたしているところでございます。 ところで、そういう中で、今自民党及び公明党で、今委員が御指摘になられたような名称のPTと申しますかそういうものを立ち上げて、医師不足ということを名前に、タイトルにうたったそういうものが立ち上がっておりまして、これからいろいろ御検討をいただくということでございますが、これは私どもといたしましては、私どもが認識しているその延長線上で、更にいろいろ我々も努力を、後でまた御説明させていただく機会があるかもしれませんけれども、そういう努力をさせていただいておりますが、それを更に後押ししていただくようないろんなお考えをお寄せいただくということであろうというふうに認識をいたしているところでございます。 鈴木寛君柳澤大臣は自民党員でもいらっしゃいますが、正に今のお話を確認させていただくと、厚労省の認識と基本的には自民党、公明党の考え方は同じだと、こういうお話と理解させていただきます。 それで、確かにそうなんですね。と申しますのは、この医師不足、地方に足らない、このことは私どもも認めており、というか我々は、全体的に足りませんから、地方も足らないし、診療科で足らないところもあるし、いろんなところで足らないところがあるということなんですけれども。新聞報道ではございますけれども、幾つかのこの対応策というものが報じられておりまして、これは厚労省ではなくて与党の方でお出しになっているんで、党員としてお答えをいただくということになるんだと思いますけれども、地方の医師不足を解消するために国公立病院などの拠点から派遣をすると。要するに、今までは大学の医局がやっていたけれども、その機能を今度は国公立病院が代わりに担っていくと、こういうことだと思うんですけれども、こういう構想が近々まとめられるというのは事実なのかどうかということですが、これはいかがなんでしょうか。 国務大臣(柳澤伯夫君)拠点病院、これは現実に、例えば研修医の先生方をたくさん引き寄せて引き付けているところ、こういうところを拠点病院というふうに位置付けまして、そして地域によってもう不足だというところに派遣をするというそういうシステム、ネットワーク化とも申しておりますけれども、このシステムというのは、実は現在私どもも進めさせていただいているそういうシステムでございます。 私どもも、この医師の養成ということについても、非常に医師不足が顕在化していたり、地理的ないろんな条件でお医者さんが足りないということ、これはまあそういう地理的な条件、人口的な背景というようなものでいろいろ我々地域の状況というのを細かく見ていかないといけないと思うんですけれども、いずれにしても、そういう地域的な事情で不足のところには、その拠点で研修医の先生方等をたくさん引き付けていらっしゃるところからお願いをして配分をする、派遣をしていただくようにということをお願いいたしておりますが、これは現に我々のやっているところでもあるわけでございます。 と同時に、ちょっと言い掛けたんですが、明らかに不足なところを十県くらい選定しまして、そこの医科大学でもって将来の養成数を先食いする形のような形でもって、これは伊吹大臣の御専門でもあるんですけれども、定員を増やしているというようなことも努力させていただいていますが、お医者さんが一人前になっていただくにはざっと十年掛かるということですから、これは急場の間に合わないということで、今のとにかく急場の間に合うというか、緊急の対応としては、主として今の派遣制度というかネットワーク制度を使わせていただいているわけでございまして、それをどういうふうにしていくかということについてまた新たなお知恵をいただけるのかなと思って審議の行方を見守っているところでございます。 鈴木寛君厚労省さんは、この偏在あるいは不足の解消を、あるいはその原因を、その卒後臨床研修が始まったことで研修医の配分といいますかローテーションが今までとちょっとゆがむというか、変わったことによってそのひずみが出ているという御認識に立っているので、そういう大臣の分析と御発言なのかなと思うんですけれども、そのことも私は否定はいたしません。否定はいたしませんけれども、要するにないパイの中でやりくりをしたら、どういうふうな方法を取ったとしてもやっぱりその足らないところが出てきてしまうわけですよね。ですから、私たちは絶対的不足説を取っていて、やっぱりそこをきちっと特に臨床医については増やさなければいけないと、こういうことを主張させていただいているわけでありますが。 例えば今、医局に人が、大学病院に集まらなくなってしまったと。したがって、国公立病院の研修医は、研修医が集まっているからこれを地域に派遣するんだと。こういうことになりますと、じゃどうなるかというと、今度また、若い卒後臨床研修の皆さんは今度は国公立病院を避けて私立病院とかあるいはまた大学病院に戻るとか、こういうことの繰り返しになってしまいまして、結局はそのねらっていることというのが、また何といいますかイタチごっこと言ったらおかしいんでしょうけれども、要は、結果としては、その地域に対して、地方に対して医師を供給するということにならない。そもそもの国公立病院のところのその人材集約力すら落ちてしまうという懸念もあるということを私どもとしてはやっぱり指摘させていただきたいと思いますし、それからそもそもやはり問題は、例えばその研修医だけの問題なのかと。 例えば、女医さんなんかが、産科の場合はもう十年たつとほとんど特に臨床の現場から離れてしまうと。そうすると、中堅医師の確保も含めて、やはり今のこうしたことでは結局は抜本的な解決にならないんではないかなというのが私どもの懸念でありまして、そういう懸念は十分踏まえて今後議論していただきたいということが私の意見でございます。 それで、それと同時に今の方法論というのは実は日本全体にとって非常に心配がある。それは何かといいますと、自民党、公明党、あるいは大臣のお話も、地方は足らないと、まあこういうお話。地方も足りませんけれども、私申し上げたいのは、都会も足らないんです。人口十万人当たり医師数の一番少ない県は埼玉県ですよね、四十七番。人口当たりにして、十万人当たりにして医師数百三十四人、四十七番。その次に足らないのが茨城県ですよ、次が百五十人。そして、その次が千葉県。正に埼玉、茨城、千葉が一番足らないんですね、人口当たり。もちろん、要するに広さの問題はあります。広さの問題もありますけれども、こちらが足りているという話じゃなくて、北海道も足らないし、千葉、埼玉、茨城も足らない。だから、どっちも足らないんですね。だったら、じゃ千葉、埼玉の国公立病院に人を寄せてそれを送ったら、今でも足らない、だけれども逆に小児救急とか救急とか、現に大臣も御承知のように、もうこの五年間で二割ぐらい救急病院返上していると。この現象は埼玉でも千葉でも茨城でも起こっているわけですよね。 ですから、私はややそういう意図、意図はないと思いますけれども、今の報道とか今の政策議論を積み重ねてみると、地方は足らないんだと、じゃそこから、都会から送ればいいんだと、こういうふうにミスリードしているのが私は大変心配なんです。そのことによって既に空洞化している埼玉、千葉、茨城、それから東京でも多摩の方は小児救急とか産科とかはありません。あるいは神奈川でも同じ状況でございます。確かに青森県は四十三番ですから青森県も足らないんですけれども。だから要は、申し上げたいことは、どこも足らないんですよということでありまして、その辺りはやはり正確な認識に基づいてきちっとこの医師不足問題というのはやっぱり取り組んでいかなければ、これは別に与野党の問題じゃなくて正に行政監視委員会、こういうところでその議論をきちっと整理をし、前提を確認をしていくということが大事ではないかなと思って、こういう発言をさせていただいております。 それから、正に大臣もおっしゃったように医師不足問題は中長期的アプローチと短期的アプローチとあると思います。それで、私はやっぱり短期的アプローチは、とにかく今過酷な労働条件とそして訴訟リスク、更に言うと最近は刑事訴追リスクと、こういう中でどんどん臨床医を辞めて、病院勤務医を辞めて開業してしまうとか、そこを何とか食い止めるということが重要ですよね。そして、報酬を出してももう関係ないと、要はそこで働く人数を増やしてくれと。とにかく少しでも休み時間あるいは休日を下さいというそういう状況でありますから、やはり病院、いわゆる病院で行う医療行為に対する診療報酬というものを少し増やして、そうなれば、公立であれ私立であれ病院経営者は、お医者さんの数を増やそう、あるいは看護師さんの数を増やそうと、こういうことになって、結果として休日とか休暇とか休養時間とかというものが取れると、こういうことになりますので、これをやはりきちっと速やかにやるということが短期的にはまず必要ではないかというふうに思うんですが、いかがでございましょうか。 政府参考人(水田邦雄君)お答えいたします。 診療報酬の設定に当たりましては、医師や病院団体の関係者が参画いたします中医協におきまして、医療機関の経営実態に関する調査を踏まえて設定しているところでございます。例えば平成十八年度の診療報酬改定について申し上げますと、産科、小児科、それから救急医療等につきまして、診療科や診療部門によりまして医師の偏在で地域において必要な医療を確保されていないと、こういった御指摘があることも踏まえて手厚い評価を行ったところでございます。今後とも、広く病院団体等の御意見を伺いながら、そういった御意見が適切に反映できるように努力をしていきたいと考えております。 鈴木寛君このことはもう本当に毎年毎年申し上げておりますけれども、やっぱりまだまだ足らないと思いますので、この点、是非、頑張っていただきたいというふうに思います。 それから、長期的な話でございますが、今日、伊吹文部科学大臣もお越しをいただいておりますが、これも報道によりますと、卒後十年の地方での勤務条件を付けて、医学生を、その入学時にいわゆる地域医療枠というんでしょうか、自治医大方式を参考にして四十七都道府県で年五人程度こうした枠を設けていくというようなことが報じられておりますが、これは文部科学省が最終的には御判断される話だと思いますが、この真偽あるいはこうしたいわゆる長期的なアプローチについての御意見をお聞かせいただきたいと思います。 国務大臣(伊吹文明君)新聞報道で存じている程度で、与党からまだ私には何の話もございません。もちろん、ふるさと枠のようなものをつくるということはある意味では有能かも分かりませんね。しかし、現在の医師不足というのは、私は二つ大きな原因があると思います。 一つは、六年たって医師免許を取った後の人たちの研修の場所を自由化しましたから、結果的に民間あるいは大都市にその人たちが散逸をして、そして大学病院である意味では安価な労働力として実態的に使っていた人たちが不足になったので、大学院を出た後の、インターン終わって、研修終わった後の大学院を出た後の教室から派遣していた人たちを含めて、大学の教室が引き揚げたというところに大きな一つ問題がありますね。ですから、研修制をどうするかということは、私は大きな問題が一つあると思う。 それから、市場経済で動いているわけですから、そして子供さんの数と新生児の数が減っているわけですから、ここに対して、これは柳澤大臣の御所管ですけれども、ここに対する医療の需要が減ってきているときに、診療報酬の点数をある程度考えてトータルの収入を確保してあげなければ、産科、小児科のお医者さんのなり手は減っていくというのは当たり前のことなんですね。 ですから、対症療法的にふるさと枠を設けるだけでは私は解決しないと思いますし、職業選択の自由その他いろいろな問題がありますから、少し事柄を深めて議論をしてみる必要があるんじゃないでしょうか。 鈴木寛君分かりました。また、ここについては文教科学委員会でも議論をさせていただきたいというふうに思います。 正に大学の医局が人を引き揚げたと、そのことなんですよ、この特に激化している理由はですね。その大きな契機となりましたのは、私は、これもこの委員会であるいは他の委員会で御議論させていただきましたが、福島県立大野病院の産婦人科医らが刑事訴追をされるという事件が一つ端を発して、そして大学の医局が、特にこの一人医長、そうした一人で極めて難しい手術も含めてやっているような現場から医局員を引き揚げざるを得ないと、こういうやむにやまれぬ御判断ではあったと思いますけれども。そうしたいわゆる萎縮医療とか保身医療とかという言葉がありますけれども、そうしたことが急速に残念ながら進んできてしまっているということだと思います。 こうしたことを受けて、今厚生労働省で診療行為に関連した死亡に関する死因究明等の在り方に関する検討会というのを設置をされて、こうしたいわゆる萎縮医療でありますとか保身医療を何とか食い止めて、そして、医療崩壊を食い止めて医療現場を正常化すると。その一つの重要な論点がこの論点だと思いますけれども、検討会を開いていただいていることは私は大変時宜を得たことだというふうに思っておりますが、幾つかその中身、まだ御議論のもちろん途上だとは思いますけれども、その中身について御質問をいたしたいと思います。 大野病院のときもそうでありましたけれども、業務上過失致死罪の問題とそれから医師法二十一条の問題と、これは二つあったかと思います。それで、この検討会では医師法二十一条についてどういう方向で御議論をされていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 こちらの御要望といいますか、私の意見を申し上げておくと、元々医師法二十一条ができたときの趣旨と今の運用がかなりやっぱり私は乖離しているというふうに思います。したがって、やっぱりいわゆる医療関係の死亡を異状死に含めるべきではないと私は思うんですけれども、こういう御議論というのはここでされていっていただけるのかどうかを御答弁いただければと思います。 政府参考人(松谷有希雄君)委員御指摘の今般の診療関連死の死因究明制度の構築に当たりましては、現在検討しております診療関連死の届出制度をこの中で検討してございますが、これと今御指摘の医師法二十一条による異状死の届出制度の関係を整理する必要があるというふうに認識しておりまして、これまでも法務省、警察庁及び厚生労働省の関係省庁連絡会議におきましてもこの点に関する議論を行ってきたところでございます。 この医師法第二十一条、異状死の届出の問題につきましては、意見募集に対しても多数の意見が寄せられたところでございまして、今後、こうした意見やあるいは検討会での議論を踏まえまして、十分にこの件についても検討してまいりたいと考えております。 鈴木寛君これは本当に重要なポイントでございますので、是非、警察庁あるいは検察庁あるいは法務省等々との折衝もあろうかと思いますけれども、是非お願いを申し上げたいというふうに思います。 それと、ここで幾つかの検討課題というのが挙がっておりまして、死因究明のための調査機関というようなことについても御議論をされるんだと思いますが、そもそもこの検討会が、これ趣旨を読みますと、診療行為に関連した死亡に係る死因究明の仕組みやその届出の在り方について整理すると。是非、整理をしていただきたいと思うんですが、やはり政策というのは、やりたい目的というのがあって、その目的達成のためにはどういうふうな政策を講じたらいいのかということなんで、これを見ますと、目的がよく分からない。もうちょっと申し上げると、もちろんいろんな目的があっていいと思います、再発防止とかあっていいと思うんですけれども、結局、再発防止もする、あるいは訴訟リスクとか刑事訴追リスクとかというのを減らして萎縮医療を回避する、そのことによって医療崩壊を食い止める、悪循環を食い止める、それからあるいはその公正な調査を実現すると。まあどれも重要な課題なんですけれども、そこをきちっと腑分けして整理しないと、これでき上がったシステムというのは、何か結局事態の改善につながらずに更に悪化するという、こういうことを私、ややちょっと気になってというか、心配しております。 再発防止は、既にいろいろなモデル事業をやっておられて、そのカバレッジをもっと増やすとか深めていくとかということで私は足るんではないかなと。そうすると、あのモデル事業がありながら、加えてこういう第三者検討委員会をおやりになるということは、もう一回何のためにどういうことをねらってやっておられるのかということをちょっと整理していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。 政府参考人(松谷有希雄君)診療行為に関連した死亡等につきましては、これまで死因の調査や臨床経過の評価、分析あるいは再発防止策の検討などを行う専門的な機関が設けられていないといったようなこともございまして、結果として民事手続や刑事手続に期待されるようになっているという現状があるというふうに認識しております。 ここが出発点でございまして、これらを踏まえまして、患者さんにとって納得のいく安全、安心な医療の確保、また不幸な事例の発生予防、再発防止等に資する観点から、平成十九年三月に、診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する課題と検討の方向性と題する厚生労働省の試案を提出したところでございます。専門性の高い調査組織による原因究明の仕組みを構築するということでございますが、それによりまして再発防止あるいは萎縮医療の回避にもつながるというふうに考えておる次第でございます。 いずれにいたしましても、パブリックコメントの御意見、また検討会の議論を踏まえまして、死因究明の在り方につきましても今後検討してまいりたいと思っております。 鈴木寛君正に医療事故あるいは医療関連のこうしたことというのは非常に複雑でありますので、そういう意味ではそうした専門的な機関によってきちっと調査がされる、そのこと自体は結構なんですけれども、じゃ、だれのためかと。まあ民主党は患者の権利法案というのを国会にもお願いをしておりますけれども、正にその情報は非常に非対称で、特に患者さんが何が起こったのかということを正確に知りそして理解をする、調べ理解をするということが非常に難しいわけですね。是非、こうした機関ができるとすれば、私どもは患者のための、患者さんがこれを活用することによって、あるいはこの機関が患者さんを応援していただくことによって何が起こったのかということを正式に理解すると、そういう本旨に基づいてこの制度設計というのは是非やっていただきたいなと。 これだれのためのというところが間違ってしまいますと、結局、屋上屋といいますか、今、結局医師法二十一条は残ってしまって、医師法二十一条に基づく警察への届出もやらなきゃいけないと。加えて、今度新しい第三者専門機関ができて、そこに、まあそんなことはないと思いますけど届出義務なんか掛けて、まあそんなことは考えておられないと思いますけれども、仮に掛けて、その届出義務違反もあれされて、更にそこでの立入検査を受けなければいけない。警察からも立入検査があって、そして第三者機関からも立入検査があって、そしてそこに何か、何といいますか手続上の落ち度があった場合には、もう両方からの訴訟リスクであるとか訴追リスクということになってしまったら、何のためにこういう議論をしていただいているのかというのは全く分からなくなってしまうわけですね。 ですから、そういう意味で申し上げると、この検討課題の中で行政処分の在り方ということについても書いておられますけれども、これはもちろんきちっと医師法に基づく行政が行われるという、これは大事なんですけれども、今民事訴訟があって、そして刑事訴追があって、更に行政処分が強化されるということになると、結局、萎縮医療がもっと萎縮してしまうんじゃないか、あるいは保身医療がもっと保身になってしまう。 この前も正に奈良県の大淀病院で、まあいわゆる新しいタイプの形の患者のたらい回しというのが深刻化しているわけですね。しかしあれは決して珍しいことではなくて、それこそ先ほどからお話し申し上げている、千葉でも埼玉でも茨城でも神奈川でも、ああしたたらい回しの状況というのはもう日常茶飯なんですね。結果として、その患者さんが命を取り留めて回復しておられるのでニュースにならないだけで、元々はこの問題は正に保身、萎縮、医師の立ち去りと、こうしたことによって結果として一番困っているのは患者さんなんだというところから始まった議論だと思いますので、そこのところを是非とももう一回きちっと基本に立ち返ってやっていただきたいということと、そういう中で、結局司法という枠組み、これ自体が限界があるという、これ非常に難しい問題なんですね、医療にどこまで司法が入るかと。すなわち、裁判あるいは訴訟ということになりますと、原告、被告という関係、あるいは被告人と検察という、こういう関係になりますから、どうしても対立概念です。しかし、医療現場というのは、基本的には患者と医師との極めて濃厚な信頼関係というものがなくてはいけない。 最近、これは非常にレアケースだと思いますけれども、患者さんが初診のときからテープレコーダーを机に置いて、そしてどういう発言があったかと。これじゃ、もうお互いの信頼関係も何もあったものではないわけでありまして、これはもちろん極端なケースでありますけれども、もう一度医師と患者との信頼関係というのをつくっていくために、この訴訟制度も含めてどうしていったらいいのかと。そういう中で、対話型医療ADRの議論というのもしていくというようなお話も聞いておりますけれども、そうした点も是非心掛けていただきたいと思いますが、この対話型医療ADRについてはいかがでしょうか、この検討会ではどういうふうに議論されていくんでしょうか。 政府参考人(松谷有希雄君)委員御指摘のとおり、医療の本質は、患者さんと医療提供者とがそれぞれ信頼関係を持って構築をしていく、そういうふうにしていくものであるというふうに思っております。 診療行為に関連した死亡につきましては、先ほど申しましたけれども、これまで死因の調査あるいは臨床経過の評価、分析、再発防止策の検討等を行う専門的な機関が設けられていなかったというようなこともございまして、結果として、民事手続あるいは刑事手続に期待するようになっている現状があるというふうに認識をしてございます。 このため、今般の診療関連死等についての死因究明制度が構築をされ、事実関係が明らかになるということになりますれば、医療機関と患者さんとの間での話合いも促進されるということになるものと考えております。 さらに、今回の診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する課題と検討の方向性におきましても、調査報告書の活用や当事者間の対話の促進などによります、当事者間や第三者を介した形での民事紛争の解決の仕組みを検討していくこととしてございまして、今後、意見募集に対していただきました御意見や検討会での議論等も踏まえまして、十分に検討していきたいと考えております。 鈴木寛君大臣にお願いをしておきたいんですけれども、この問題は本当に医療関係者、それは患者さんも含めて大変関心を持っていただいておりますし、もう制度設計いかんで本当に、更に医療崩壊が進んでしまうのか、ここで医療崩壊がきちっと止まるのかという極めて重大な岐路にあると思います。 そういう中で、昨年来、この大野病院の問題などで、川崎前大臣などにも意見書を出したりしているグループがあったり、現場の、特に臨床現場のお医者さんたちが非常に問題意識高く、この一年間、いい意味で立ち上がってきていただいていまして、例えば、現場からの医療改革推進協議会のワーキンググループがパブリックコメントに対して五千七百十六名の方が署名をして意見を出しておられます。こういう形というのは非常に今まで珍しいことだなというふうに思っておりまして、もちろんそれぞれの有識者で構成されている日本の専門医の皆様方の学会の代表も出されております。 いろいろな方々が真剣に考えて真剣な議論を厚生省に寄せていただいておりますので、是非こうした議論を大臣、重く受け止めていただいて、遺漏なきようこの問題、対応していただければというふうに思いますが、いかがでございましょうか。 国務大臣(柳澤伯夫君)厚生労働省におきましては、今先生がお触れになったような諸般のいろいろな問題を踏まえまして、診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する検討委員会を設置をいたしまして、去る三月九日に厚労省試案というものを発表しておりまして、四月の二十日までにパブリックコメントをいただいているところでございます。個人、団体を合わせまして、合計百四十件のパブリックコメントがいただくことができました。今、委員の言及されました現場からの医療改革推進協議会ワーキンググループの方々からもコメントをいただいたところでございます。 どのパブリックコメントも患者や御家族あるいは医療関係者からの真剣な御意見であるというふうに受け止めておりまして、今後、これらの御意見を十分踏まえまして、今委員も御指摘になられたように、なかなか難しい問題であるというふうに思いますけれども、何とかこの取りまとめを一定の筋の通った体系的なものとしてまとめることを目指しまして努めてまいりたいと、取り組んでまいりたいと、このように考えております。 鈴木寛君霞が関や永田町で考えているいわゆる、何というんですか、こういう言葉は使いたくありませんけれども、机上のことと、現場のいろいろな、表に出ること出ないこと含めてやっぱり現場の皆様方の声というのは本当に是非聞いていただければ有り難いなというふうに思います。 それから、そういう意味で、もう一点だけお願いを申し上げたいんですけれども、DPCが進んでおります。これにはもちろんいい点、悪い点、両方あるわけでありますけれども、お願いは、昨年私も民主党の医療改革PTの副座長といたしまして、がん対策基本法、これは正に与野党でできたすばらしいことだったと思いますけれども、その中で、がん対策基本法ができまして、抗がん剤治療について大きな後押し、大きな一歩が進んだと思います。これは厚生省に感謝をいたします。 例えば、抗がん剤の審査なども早くなっております。このこと自体は大変結構なことだと思いますし、基本法を作った一つの成果だというふうに思いますけれども、結局、いい薬ができて、審査も早く通していただいても、まあ新しい薬は高いですから、そうすると、DPCだとなかなかこれ、それは現場の判断なんですけれども、お医者さんは使いたいと、しかし病院の経営者は従来のと、こういう中で、せっかくいいことを行政もやってくれたし、それから医療者も一生懸命勉強して、そして製薬会社もそういうふうな開発をしてくれてということが、患者さんにあと一歩のところで届かないということになっているんですね。これは大変残念だと私は思います。 是非御検討をお願いしたいのは、今手術はDPCの外ですよね、その算定の枠の外ですよね。ある意味、患者さんからしますと、結局、これはがんだけじゃありませんけど、手術を選ぶのか、こうした抗がん剤治療をやるのか、あるいは放射線治療をやるのかと、その状態に応じてどれかを、それは医学的にベストなものを選ぶわけですから、この抗がん剤治療にしても、薬ではありますけど、やっぱりそれの投与というのは非常にある意味で医者の高度な技術、ケアの下にやらなければいけないということも事実でございますので、是非この点は、抗がん剤治療をDPCの枠組みの外に、手術と同じような扱いにしていくということについて是非御検討をいただきたいということ、これはもうお願いでございますので、よろしく御検討をお願いをしたいと思います。 それと、農林省さんに来ていただいていますので、もう時間がありませんのでお願いを申し上げますが、築地の卸売市場の豊洲地区への移転問題でございますが、私たち民主党は、この問題は実はこの委員会で私、二〇〇二年の四月一日にも問題提起をさせていただいて、余りにも強引に東京都が、六価クロムを始め有害金属の土壌がもう確認をされている、その土地所有者が確認をしているところに、食べ物の正に、しかも築地ですから、それを持っていくというのはこれはいかがなものかということをずっと言わしていただいております。 私ども民主党は、東京都連あるいは都議会民主党を含めて、この移転問題について白紙撤回をするためのプロジェクトチームを立ち上げております。それから、日本環境学会も移転反対の御意見を出されたところでございますけれども、是非やっぱり農林省としても、これは東京都の問題じゃなくて日本全部の消費者の食の安全、あるいは消費者の皆さんの食に対する安心の問題でございますので、是非ここはやっぱりきちっと再調査あるいは追加的な措置、こうしたことをやるように農林水産省から東京都に働き掛けるなり指導するなりアドバイスされるなり是非していただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。 副大臣(国井正幸君)今の御指摘の点はさきの都知事選でも政策の争点になったようでございまして、私どもが伺っているところによりますと、再度専門家の御意見等もしっかり聴くと、こういうふうに東京都が再調査に向けて取組を始めるような話を聞いています。 今先生御指摘のように、これはやっぱり食べ物ということで消費者にとっても大変重要なことでありますし、あるいはそこで勤務をして、常時働いている人たちの健康状況にも極めて重大な問題を含んでいるというふうに思いますので、しっかりと、これは第一義的には東京都の問題でありますが、農林水産省としてもしっかり働き掛けて、少なくとも疑義が挟まれないように、そういう努力を重ねていきたいと、このように思っています。 鈴木寛君是非、今御答弁いただいたように積極的に農林省、食の安全ですから厚労省も絡むと思いますが、政府挙げてこの問題、注視していただいて、的確な指導、アドバイスをしていただくようにお願いを申し上げたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。 |