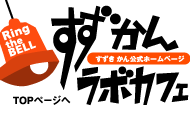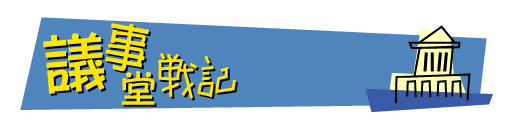2007年3月15日 文教科学委員会166-参-文教科学委員会-2号 平成19年03月15日鈴木寛君民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。 西岡先生に引き続きまして御質問をさせていただきたいと思います。 まず、質問に入ります前に、ちょっとお礼を申し上げたいと思いますが、昨年九月に安倍政権発足いたしまして、伊吹大臣も御就任になられて、本会議で私から放課後学校プラン、私ずっといろいろNPOや学生と進めてまいりまして、これは放課後子どもプランという形で受け止めていただいて、そこで質問をさせていただきました。本当に伊吹大臣から真摯にかつ誠実な御答弁をいただいて、かつ今回の予算案、全体論については私も野党でございますので立場はございますけれども、そのことについてはあそこでお答えをいただきましたように、きちっと前向きに取り組んでいただいておりますことを大変に感謝を申し上げております。 お願いは、これはステップ・バイ・ステップということでございますから、来年度の概算要求に向けてということで聞いていただくだけで結構なんですが、今回は小学校ということではございますけれども、是非やっぱり要望の強い、社会的ニーズも高い事業でもございますので、中学校についても何らかのやはり、いろいろな要素ありますけれども、塾に行ける子と行けない子の格差を埋めるとか、あるいは地域の人との斜めの関係をつくっていくとか、本当にいろんな多様な要素がございますので、そうしたことも御検討いただきたいと思いますし、今年度はむしろ準備段階なので六十八億円の文部省計上で、あとは県と市がこれに三分の一ずつということで、これも逐次大臣の御指示の下に事務方に何度も御説明に来ていただいて、私もその額も含めて今年の措置としては非常に妥当だと思っておりますが、これは来年一挙に、本当に一万校単位で、数千校単位で広めていかれるということでありますので、是非御奮闘をお願いを申し上げたいというふうに思います。 それから、併せて御礼を申し上げますが、奨学金の件も、今年、五万二千人更に上積みをしていただきまして、百十四万人ということで、伊吹大臣のテリトリーといいますか、そこについては非常に私どもの真摯なお願いを正面から受け止めていただいていることに心から敬意を表したいと思っております。 それで、ただ、それでそれはお礼でございます。次に、そこには何のあれも付きません、ただというのは取り消しますが。 でありますが、同じ本会議のときに、先ほど来、西岡先生と大臣との間で御議論がありました、行革推進法の話を安倍総理に私、聞かせていただいたんですね。聞いた相手が間違ったなと、伊吹大臣に聞けば問題は片付いたのかなと思って私の至らなさを反省しているんですけれども。 先ほどの御議論は、大臣がおっしゃったとおりなんですけれども、私、残念だったのは、やっぱり第八次定数改善計画、これは少なくとも昨年の暮れ、伊吹大臣のリーダーシップの下で予算編成が行われて、そしておととしの暮れのときに、正に小泉政権下で第八次定数計画が見送られたのは、これは小泉政権の中の連立方程式という議論で分かりますけれども、昨年は正に安倍総理、伊吹文部科学大臣、そして尾身財務大臣と、この政権の下で二回目の持ち越しといいますか、が行われてしまったわけであります。 それで、行革推進法の直し方、これはいろいろ方法があるということ、私どもが方法があるとおっしゃるけれどもそうでないのではないかと思っている理由は、今までも、もう大臣御存じのようにといいますか、大臣もおやりになられたと思いますが、例えば行政改革で総定員法の大原則があって、総定員法の中で定数削減が各省一律に掛かっている中で、しかし、必要なところには一律分の定削は受けるけれども、しかし必要な行政分野については定数増をすると、こういう手法でやってきたことはございますし、大臣もそのことを念頭に置いておっしゃっているというふうに思いますし、そういう手法論というのは、二・七六削ってこちらで三とか四とか増やすと、これは私どもも理解はしているんです。 なんですが、先ほどの繰り返しにもなりますけれども、行革推進法、これもう釈迦に説法でございますが、教育をねらい撃ちにしているものですから、要するに一般政策を個別政策でオーバーライドするというのは、これはよくやる、正に立法あるいは政策論なんですけれども、教育についてねらい撃ちしていますから、要するに教育個別政策なんですね。そうすると、そこでのバッティングというのは、要するに一般法に個別法がオーバーライドするという原則では解決ができないものですから、そこでコンフリクトが生じるんで法的な手当てが必要じゃないでしょうかと。 私どもは、教育についてきちっと体制を整えるということであれば、その附則か何かで、行革推進法の五十五条、五十六条を、そちらの法律の附則でいじるというようなことがいろいろ勉強をしておりますと必要になってくるなということを我々日々研究と、で、悩みながら、そして御一緒に何とかこの日本の教育現場を立て直すために正にこの文教委員会で与野党超えて知恵を出したいなと、こういうことで臨ませていただいているということでございまして。 質問戻りますけれども、八次定数ですね、これを見送らざるを得なかった、伊吹大臣ですら見送らざるを得なかった背景というのはどういうことだったのか、お聞かせをいただきたいと思います。 政府参考人(銭谷眞美君)私からまず経過を御説明をさせていただきたいと思いますけれども、教員定数の改善につきましては七次の改善までをやってきたわけでございます。十八年度に第八次の新しい改善計画をやりたいということで概算要求をいたしましたけれども、十八年度は見送られたという経緯がございます。 十九年度につきましては、十八年度見送られた後のことでございましたので、私ども、本当に緊急に必要な特別支援教育とか幾つかの事項に限定をして緊急三か年間の定数改善をできないだろうかということで概算要求をしていたわけでございますけれども、これにつきましても、大変現在定数に非常に厳しい状況の中で、これにつきましてもいわゆる純増という形での定数改善はできなかったということで、合理化を一部定数について行いまして、そして特別支援教育あるいは食育について定数改善を行ったという経緯でございます。 今後、私どもとしては、教育界の教育の、今の教職員の状況あるいは学校教育の現状を考えたときに、二十年度以降の教職員定数をどうするかということはやはり大きな課題だと思っておりまして、今こういう行革推進法がある中でございますけれども、この問題についてはまた二十年度概算要求以降よく考えていかなければいけない課題だと思っております。 国務大臣(伊吹文明君)事実関係は今参考人が申し上げたとおりなんですが、安倍内閣ができたのは昨年の九月なんですよね。財政法の規定によって概算要求の締切りは八月三十一日なんですよ。これは小泉内閣ですべての作業が終わっておったということは、もうこれは先生は公務員をやっておられたからよくお分かりだと思います。 同時に、この定数のしりだけを我々は持っているわけであって、実際はこれは地方の財政計画にも関連してくることですね、基準財政需要にも関係してくることですから。勝負はやはり二十年の概算要求段階からかかわれるときでないと、先ほど西岡先輩がおっしゃったように触れないというのが行政の常識なんですね。そこでひとつ頑張ってみたいと思いますから、是非ひとつ応援もしてもらいたいと。 そして、一番最初に先生から聞いたことについては、一応やったなというお話がありますが、私はさっき西岡先輩と大変いいお話をさせていただいたと思いますが、国会を私は大変重視をしているんです。ですから、教育特のときも民主党の皆さんの御質問あるいは民主党案というのもかなり私は参考にして、今回ああいう総理の決断をなさったときに総理にインプットしているものもかなり参考にさせていただいているつもりなんです。そして同時に、民主党も賛成された株式会社のあれは参入法案なんですよ。そういうことも尊重しながらやっているわけですからね、どうぞ間違いのないようにしてください。 鈴木寛君私はよく分かります。大臣のテリトリーの中では相当いろいろ玄人好みの知恵も出されて御努力されているというのはよく分かっております。そのことは大変私自身は評価させていただいているんですけれども。 ただ、結局、前提となっているといいますか、文部省からすると追い込まれている前提というのがありますよね、それは小泉内閣からの慣性力の部分もあろうかと思いますが。そこの土俵を広げないと、狭い土俵の中では本当に御奮闘いただいているというのはよく分かるんですけど、例えば暮れの予算でも、今局長からもお話いただいたように、その土俵の中では最大限の、一番現場のニーズをとらまえて、そこに何といいますか、今年は特別支援教育元年でもありますし、食育も始まるという中で、そこの整合をきちっと付けようとされている。そういうところは非常に分かるんですけれども、やっぱり今、六十年ぶりに教育基本法を変えて本当に平成の大教育改革ということの中で、やっぱり大きな枠組みについてもう一回ゼロからあるべき論を議論しようではないかと、こういうことで我々は議論に臨ませていただいているんですが、二十年度の予算編成を大変期待したいと思いますが。 お考えをちょっとお聞かせいただきたいんですが、今まで、結局七次まではまあ順調にといいますか、もちろん中身のその数が多い少ないという議論はあれど、少なくとも六次、七次ときちっと五年ごとに決めると、それを実施すると、それをいろいろ現場に照らして検証してという、正にプラン・ドゥー・シー・チェックというか、PDCAサイクルがこの教員定数についてはきちっと回ってきたんですね。ただ、我々危惧しているのは、もちろんあの厳しい中で定数を増やしていただいた、頑張っていただいたことは多とするんですけど、そうじゃなくて、これまで来たそういうフレームワークがどうなってしまうんだろうかというところが懸念なんです。 だから、結局今まではそれが法制化しないまでも、かなり慣習法に近い省庁間のルールとしてなされてきましたから、それを別に明文の法制にする必要はなかったと思いますし、けれども、結局二年ない状態で続きますと、じゃこれが三年、四年、そもそも第何次定数改善という枠組み自体どうなってしまうんだろうかと。やっぱりここは心配といいますか、それをなくすならなくすでまた別の枠組みをつくらなきゃいけないし。それから、事務方に聞きますと、八次やりたかったけれども行革推進法がありましてと。まあ、ありましてというのは、法的にあるからできないということなのか、そういう安倍内閣のあるいは小泉内閣から引き継いできたときの力関係という意味でおっしゃっているのかは、それはここではあえて細かくは問いませんけれども。 むしろ、二十年の、未来の話の議論として、きちっと年次年次で、八次、九次、十次と、こういう形での枠組みというものをどういうふうに考えておられますかということをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。 政府参考人(銭谷眞美君)教員の定数改善の場合は、一つには学級編制との関連ということで、いわゆる四十人学級まで定数改善は来ているわけでございます。それで、第六次とか第七次の定数改善計画は、むしろ少人数指導とかチームティーチングとか、そういったきめ細かい指導をするための教職員の加配措置を中心に平成十七年度まで掛かって言わば定数改善を行ってきたということでございます。現在の教職員の定数というのは、したがってこの十七年度までの定数改善の状況を引き続いて、そのままの状態で基本は引き続いているということでございます。 教職員の定数というのは、御案内のように、基礎定数と加配定数と、こういうことから成り立つわけでございますが、学級数に応じました基礎定数は、これは別に悪くなるとかそういうことではなくて、現在の状況が続いているということでございますし、加配定数につきましても、子供の数等を見て、それに応じた数は確保されているわけでございますから、いわゆる生徒と教員の関係における教育条件というのは現在の水準を悪化させないというのが十八年度、十九年度の状況でございます。 それで、私ども第八次の、先ほど申し上げましたように第八次の教職員定数改善計画、これを策定をして十八年度概算要求したわけでございますが、残念ながらそれが認められなかったと。十九年度は緊急三か年対策ということで特別支援教育と食育を中心に改善要求をしたわけでございますけれども、事実上の実質増ではなくて、合理化を伴う定数改善ということで、特別支援教育と食育について三百三十一人の所要の措置、定数措置ができたという状況でございます。 二十年度以降につきましても、私ども、現在のこの行革推進法の中でございますけれども、そのことも含めまして、二十年度以降の定数改善につきましては現在の教育条件を悪化させないと、その中で、かつ本当に必要な教職員の定数措置をするということで、概算要求に向けてどうするのか真剣に今考えているところでございます。 鈴木寛君真剣にということなんですが、枠組みを提案しましょうということを私、申し上げていまして、だから枠組みをどうするかと。ですから、局長のおっしゃった答弁は、私も標準法を読んでいますから、標準法って物すごいトリッキーな作り方ですよね。恐らくこれは、この法律ができたときに大蔵省からこのようなことを強いられたんだと思いますが、そのときに伊吹大臣がいらっしゃったかどうか分かりませんけれども。要するに、定数改善ですからね。だから、ほっておくと維持なんですよね。ずっと状態が維持なんですね、標準法の状態が維持で、それで附則でもって五か年というのを担保していますから、そうすると、その法律状態が実現されるというのは五年のうち一年しかないと、四年間は全部附則の状況、移行期間という極めてトリッキーな、本当に知恵が出たんだな、そのころの大蔵省はと思うんですけれども。逆に言うと、そこも含めて、ちょっと反転攻勢といいますか、やっぱりきちっと分かりやすく、これやっぱり分かりにくいですよ、この標準法のトリッキーな枠組みというのはですね。 だから、もちろんその財政状況あります。そして、もちろんもっと重要な教育のニーズというのはあります。それはだから、その内容の改善の度合いとかというのは、それはいろいろ議論をしたらいいんだと思いますけれども、枠組みとしては今回せっかく、私どもは反対はいたしましたけれども、教育基本法の改正の中で教育振興計画というのができて、恐らく教育振興計画というのは、内容の話はそんなに文部省が口出すという話ではなくて、基本的なこと以外はですよ、むしろやっぱりこういうふうな環境整備といいますか、その体制整備ということなんでしょうから、だから、そういう議論の中でこの定数改善の問題もやっぱりきちっと位置付けていただいて、そういう枠組み論も含めて真剣に御議論いただいて、堂々と大蔵省に、財務省に要求をしていただくということを是非御期待を申し上げたいというふうに思います。 何かありますでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)ちょっと参考人の答弁と先生のおっしゃっておられることがかみ合っていなかったと思いますが、大蔵省、当時の大蔵省がトリッキーなことをやったのか、自治省がやっぱりこれは一番難しいんですよ、率直に言うと。地方財政の問題ですからね、基本は。ですから、自治省との間で話をして、もちろん財務省も絡んでまいりますよ、文部科学省予算に計上されている部分がありますから。ですから、(発言する者あり)うん、教育。だけど、財政の要請だけですべてが決まるんなら教育というのは一体何だったかということになるわけですから、先ほど西岡先輩がおっしゃったような安倍政権の姿勢を反映できるようなものをつくっていかなければならないわけですから、ひとつ先生も選挙が終わったら是非御協力をいただきたいと思います。 鈴木寛君ありがとうございます。 では、ちょっと質問を変えますが、これもせっかく教育再生を唱えておられる内閣の中でもう一押し頑張っていただきたいなというお話でございます。 弱視者用の拡大教科書の件でございますが、これは今でも大変感謝しておりますけれども、前小坂文部科学大臣が、この文教科学委員会の場でも御議論をさせていただいて、非常にリーダーシップを発揮していただいて、平成十八年の七月の二十七日に教科書発行会社の代表に極めて明確に要請をしていただいたんです。このことは本当に弱視教育に携わっておられる方は大変感激をし、そして本当に喜んでおられたわけでありますけれども、この要請以降、この拡大教科書問題は今どういう状況になっているのか、ちょっと概略をお話しいただけますでしょうか。 政府参考人(銭谷眞美君)昨年の七月の二十七日に、国会等での議論を踏まえまして、当時の小坂文部科学大臣から各教科書発行者の代表者にあてまして書簡をお送りをして、弱視の方のための拡大教科書の充実について要請をいたしました。 内容的には、一つには、教科書本文のデジタルデータの提供ということをお願いを申し上げたわけでございます。それからもう一つは、教科書発行者による拡大教科書の発行の検討をお願いをしたという、この二点が要請の主たる内容でございました。 この点につきましては、教科書協会の方におきまして、この要請文を受け、九月の業務連絡会で各社集まったところで審議をし、前向きに取り組んでいくということは確認をいたしております。その後、役員の改選等が行われ、ちょうどこの三月から新体制になりましたものですので、今正に具体的な取組を始めているところでございます。 拡大教科書の普及充実のための調査研究小委員会というのを教科書協会の方でつくりまして、具体的な今検討を行っております。具体的には、二十年度用に向けまして、今年の十一月ごろまでに提供できる本文デジタルデータについて検討していこうということになってございます。需要の多い主要科目の書目について検討していこうということで、国語、社会、理科の順でデジタルデータの提供をやっていこうということになろうかというふうに伺っております。 それから、各教科書会社自身が拡大教科書の発行をするということにつきましては、現在は一社が小中学校の国語について発行しているわけでございますけれども、十九年度からもう一社、中学校の一年の国語について発行を今予定をいたしているところでございます。その他の各教科書発行者におきましても、拡大教科書の発行についてまだ検討の段階だというふうに認識をいたしております。 なお、平成十九年度の予算案におきまして、拡大教科書の普及充実のための調査研究費というのを文部科学省におきましても計上させていただいております。この経費も活用しながら、教科書発行者によるその拡大教科書の発行が多くの教科書について一日も早く発行されるよう、私どもまた努めてまいりたいと思っております。 鈴木寛君弱視のこうした教科書のサポートをされているボランティアの皆さんは、実はこの四月の教科書からもう少し何とかなるんじゃないかなという期待があったものですから、私どものところにも何とかならないのかなと、こういう要望が来ております。もちろん、ボランタリーな要請に基づいてボランタリーに協力いただくというフレームワークですから、なかなか難しいのは分かるわけですけれども、今回も中教審で憲法に規定された教育を受ける権利が侵害され、教育を受けさせる義務が果たされていない場合には文部科学省が是正措置をするというようなことも議論されていると。これは、相手は教科書会社でありますからちょっと対象は違いますけれども、学ぶ側から見れば、私たちも学習権ということをずっと申し上げてきておりますけれども、やっぱりすべての学習者、その方が弱視であっても、逆に言うと、あればこそなおということだと私は思いますが、しかも今年は特別教育元年と、こういうことでもありますので、その方に教科書が十分に行き渡らないと。 ここはやはり私は、国の責任で最後は何とかしていかなければいけないんではないかなと。この半年、いろいろ手を尽くしてみてこういう状況になっておりますから、それこそ教科書法を手直しするなり、あるいは教科書法に基づいていろいろな制度をいじるなりして、これは何としてでもすべての学習者に検定教科書が行き渡るように、ここは強力にやっていただきたいし、それから今後、二十年に相当な改善が見られると、こういう御答弁でしたから、それをちょっと関係者に事前に、こういうタイムスケジュールでこうなりますよと。もう本当に大変疲れておられて、ボランティアの方々も。非常に、逆に言うとどこまでどれだけ頑張ればいいのかっていうやっぱりめども含めて、コミュニケーションをよく取っていただければ有り難いなと思いますが、これは御要望でございますが、これは大臣、よろしくお願いいたします。 国務大臣(伊吹文明君)承りました。 鈴木寛君ありがとうございます。それではよろしくお願い申し上げます。 それでは、引き続き中教審の答申の件についてお伺いをしていきたいと思っております。 今回、三法と言われておりまして、その最終的な今法案作成の段階だと思います。今日の議論も踏まえていただいて、どんどんいいものにしていっていただきたいと思いますが、少しちょっと分からないことがありますのでお伺いをしたいと思います。 中教審答申では、学教法の改正をすると。そこで副校長、主幹、指導教諭という職を追加をする、創設をすると、こういうことでございます。学校評価とか情報提供の整備というのは、これは私ども日本国教育基本法案の中でも提案させていただいたことをお酌み取りいただきまして、ですから、先ほど伊吹大臣が我々の提案もよく勉強していただいているということを、もう中教審の答申を見ながら、感謝一杯で読ましていただいているんですけれども、そこはそれで大変結構なんですが、例えば、教頭と副校長というのは違うのか同じなのか、あるいは教頭がなくなって副校長に変わるのか、でも主幹は副校長及び教頭を助けると、こういうことになっていますから。だけど、世の中の理解は何となく、しかも市によっては、市区町村によっては教頭を廃して副校長にしているところもあったりして、ちょっとこれ混乱するなと思いまして、是非そこをお尋ね申し上げたいと思います。 政府参考人(銭谷眞美君)学校に副校長等の新しい職を設置をするということにつきましては、既に中教審は平成十七年十月の答申で触れているわけでございます。また、教育再生会議でもそういった趣旨のことが報告をされております。加えて、中教審の給与の検討をする中でこういった新しい職についていろんな意見が出てきたということを踏まえまして、今回三月十日の答申の中に、副校長その他の新しい職の設置に関する事項ということで、学校教育法の改正内容として示されたところでございます。 まず、副校長、それから主幹でございますけれども、これは各学校に置くことができる職として提案をされております。 副校長につきましては、校長を補佐をし、校務を整理するとともに、校長から任された任務について自らの権限で処理をすること、こういう規定でございまして、教頭に比べますと、校長から任された校務について自らの権限で処理することということが付け加わっておりまして、言わば教頭よりも自分で処理できる権限を持つというところが権限として加わっているという形でございます。 それから、主幹につきましては、校長、副校長及び教頭を補佐するとともに、校長から任された校務について、校長等が判断、処理できるよう取りまとめを整理すること、あわせて児童生徒等の教育を担当することということになっておりまして、校長、副校長、教頭の補佐役として、校務の取りまとめ、整理に当たると。例えば、今教務主任という方がおりますけれども、こういう方が例えばこれからは主幹、教務担当といったような形で校務の処理に当たるということが考えられるわけでございます。 なお、副校長と教頭につきましては、副校長は置くことができる職でございますので、最終的には設置者の判断になろうかと思いますけれども、副校長に教頭を切り替えていくというところも考えられますし、一方で、複数の教頭先生いるところは、お一人を副校長というような扱いということも考えられますし、あるいは、高等学校などでは全定通とかいろいろ課程が分かれておりますので、例えばそういう場合には課程ごとに副校長とかそういうのを置くとか、ある特定の課程に置くとか、いろいろな置き方がそれぞれの学校の事情で考えられるところでございます。 鈴木寛君ちょっと手短に事実関係だけ教えていただきたいんですが、副校長、主幹、指導教諭というのは担任を持つんですか、持たないんですか。それぞれイエス・オア・ノーで答えていただきたい、可能性として、標準形として。 政府参考人(銭谷眞美君)典型的なことで申し上げますと、副校長はまあ持たないケースが多いと思います。それから、主幹も一般的には持たないのかなと思います。指導教諭は、担任持ってもこれは全くおかしくないというふうに思っております。 鈴木寛君私も答申読みましたけれども、主幹は、割とアドミニストレーションみたいなことも校務ということになっていますからサポートするのかなという印象受けたんですけど、そこは、もちろん教諭からなるのもありだし、それからそうでない、そういう理解でいいんですよね。今、教務主任とおっしゃったんで、もちろん教務主任もいろんなことやっていますけれども、そこは教諭、教員からなるのか、それとも事務職からもあり得るのか、そこはどういうことで考えておられるんでしょうか。 政府参考人(銭谷眞美君)基本的には教諭からなるというふうに、そういう人が圧倒的に多いとは思います。 鈴木寛君分かりました。是非、更に詰めていただければと思います。 それで、次に教員免許更新制の議論ですが、先ほども御議論がありましたけれども、私どもは、先ほど西岡先生からお話があったようにフィンランドのようにマスター化というのはあるんじゃないかと。移行過程の話は、この委員会でも薬剤師を六年にするとかということはやってきていますから、それはテクニカルな話だと思います。 それで、私、確認をさせていただきたいんですが、教育再生会議の議論が少し荒れてて、更新制の目的が、要するに不適切教員の排除というような、これは報道ぶりなのか何なのかよく分からないんですけれども、それで中教審の答申を読みましたら、文部省は一貫して不適切教員の排除ではなくて必要な知識、技能をリニューアルしようということでその更新制を導入するんだということで、不適切教員の排除とはきちっと整理して分けて御議論をされていらっしゃると理解をしておりますが、その理解でよろしいですか。 国務大臣(伊吹文明君)再生会議は、各分科会の会議に私は出席いたしておりません。総会というのか、全体会議でしか議論を聞いておりませんが、まあいろんなことをおっしゃるわけですよね、皆さんが。ですから、先生がおっしゃったような議論もあると思いますし、逆に中教審が考えているようなイメージでとらえておられる方もいらっしゃると思います。 鈴木寛君これは、どこかのタイミングというか、まあこのタイミングだと思うんですけれども。やっぱり文部科学大臣がきちっと整理していただいた方がいいと思うんですね。もちろん出ておられないんで今までのことは知らなかった、それはもう別にそこをどうこう言うつもりはないんですけれども。 国民の皆さんが、まあそれはメディアを通じて情報を得られているわけでありまして、何か更新制をやると学校現場から不適切教員が直ちにいなくなる、だけど直ちにいなくなるんじゃないんですね、更新制ですから、十年ですから。例えば十年なのか七年なのか、いずれにしても。更新期間十年に決まったんですか、十年ですよね。そうすると、まあ遠くは十年、近くても一年と、要するにタイムラグがあって、逆に言うと不適切な教員が十年も残っていてもらったら困るわけですから。要するに、不適切教員、不適格教員の排除の議論と更新制の議論というのが、どうもこれはメディアが勝手にそういうふうに結び付けているんだと思いますけれども、やはり、やや誤解に基づいて国民世論が引っ張られるということは、これは不幸なことですから、それは私はしかるべきタイミングできちっと整理をしていただいたらいいんじゃないか。まあ、僕は中教審の理解でいいと思っているんですけどね。 国務大臣(伊吹文明君)これは、しかし再生会議に物を言うなってわけにいきませんからね、物を言うために集まっておられるわけですから。 しかし、先ほど来、午前中の大仁田先生、そして西岡先輩とのやり取りでもありましたように、いろいろなことは、御意見は御意見でたくさん出していただいて、有益なものたくさんありますよ。しかし、最後に決断するのは内閣が決断するわけです。で、内閣がそれを法律として出しますから、法律案として、それは正に国会のその法律案の審議の過程で、また鈴木先生が御質問になって、きちっときれいに整理をなすって、それを国権の、国民の代表として整理なすったことを国民がなるほどと納得するわけで、私が何か言論統制を再生会議に対してしくというわけにはいきませんのでね。 鈴木寛君これは言論統制というか、閣僚の中で最も教育制度に通じた、かつ、その今少なくとも政府の解釈権限者ではいらっしゃることは間違いないわけでありまして、その大臣が少なくとも事実関係といいますか、制度論の解説を、解説を積極的にメディア、世の中に対してしていただいたらいいんではないかということでございますので、そのようにお受け止めをください。 ということで、認識を一緒にしますと、実は大事なのは指導が不適切な教員の人事管理の厳格化の方ですよね、世の中も心配しているし我々も問題だと思っているし。今も既に地教行法四十七条の二で、そうした指導力不足教員、ちょっと時間がありませんから、不適切な教員と指導力不足教員と、まあちょっとごちゃごちゃにしますけれども。その不適切教員を、一般職員への配転というのは平成十三年のここの場で議論をしてそういうふうになりましたと。結局それがうまく機能をしていない。 聞くところによりますと、全国に百万人の教員がいらっしゃって、研修受けた人が五百人ぐらいで、配転した方が数名程度と、こういうことですから。そうすると、国民の皆さんが考えておられる、まあ不適格というか不適切というか、という教員の割合と、この一般職員への配転措置、四十七条の二に基づいて行われたものと、余りにも期待値と結果において乖離があるということから問題が発しているんだろうというふうに思います。 それで今回も、任命者が審査会の意見を聴いて認定をすると、そして研修をして必要がある場合には免職をするという、まあフレームワークとしては、最後の免職か配転かというところは違いますけれども、それからその認定のところが審査会の意見ということになりましたから、もうその部分が非常に手厚くなっているということで、そこがうまく深化していることは私も認めているんですけれども。 そもそも、なぜ四十七条の二の一般職への配転のスキームが動かなかったのかと、ほとんど動かなかったのかと。その原因はどこにあるというふうに認識しておられますか。そこの原因を絶たないと、せっかくスキームをより改善させても結局同じことになってしまうおそれがあるということを私は懸念しているんでこういうことをお伺いしているんですけど。 政府参考人(銭谷眞美君)平成十三年に制度改正をいたしまして、教員が他の職に転任できるように規定を整備をしていただいたわけでございます。ただ、現実の問題として、指導力不足の教員の認定を受けた方で転任、他の職に移った方というのは、これまでそれほど多くはないというのは、ただいま鈴木先生がお話をいただいたとおりでございます。 その背景としてやっぱりございますのは、教員として指導力が足りないあるいは不適格とされた方が、教職以外の職とはいえ、それぞれやっぱり必要な職として公共団体の中に置かれているわけでございますから、なかなかその受入れ側と話としてまとまりにくいといいましょうか、そういうこともあったのと、意外と他の職というのが、あるようでないと言うと変な言い方でございますけれども、教員の方が、これまで教員だった方が行く職というのが意外となかったと、職そのものがですね、そういうこともあったのかなと思っております。 国務大臣(伊吹文明君)これは先生、最終的には任命権者である教育委員会、具体的に言うと教育長の腕次第なんですよ。私の地元のことを言うといけませんが、京都市は割にうまくやっているんですね。 ですから、そして教育長が当該自治体の中でどの程度のヒエラルキー、横文字はいけないんですね、その組織体の中の尊敬を受ける、ポジションもいけないのかな、その地位にいるかということも影響するんですよ。それから、首長がそのことに関心を持っているかということにも左右されます。そして、最後に、ほかの役職に、ほかの職に転職できないから公務員を辞める、公務員資格を、もう公務員を離れるという人も中にはいるんですよね。 その辺までのきめ細やかなやはり人事上の管理をしっかりできる体制がないと結果的には、我々は直接の介入権がありませんので、問題点の所在は分かっているんですが、いよいよこの免許更新制が動き始めたら、少し具体的な成功例だとか何かをもう少し地方自治体に伝達をして、共有してもらってやっていかなければいけないと思っております。 鈴木寛君私も大臣と全く同じ現状認識なんですよ。私も門川さんと大変仲よくさせていただいて。逆に言うと、京都ぐらいです、うまくいっているのは。いや、私も本当に全国いろいろ見させていただきましたけれども、だからそれだけ僕は名教育長だと思いますし、それをきちっと支援されている市長さんもいて、非常にいい本当にモデルケースですよね。それと、政令市ですから、人事権が京都市にもあるしという、いろんな要素が重なって京都は本当にうまくいっていると思いますが、東京は大失敗しています。首長は物すごく熱心なんですけれども、不適格教員の排除について。でも、熱心過ぎてまた動かないということにもなっているんですけれども、東京の場合はですね。 大臣おっしゃったように、正に人事管理の問題だと私たちも思います。結局、やっぱりそこのところに、だから、これはこれで私は本当にいろんなお知恵を絞られて、こういうフレーム、枠組み、枠組みならいいですね、を深化させられたことは非常にいいと思うんですけれども、結局また同じことになりやしないかなと。人事管理体制が整わなかったときに、あるいはいい教育長を得なかった場合に、あるいは首長が関心がなかった場合に、あるいは過剰な、ちょっと偏った関心だったときに動かなくなるということを私は心配するんですよ。 それで、更に申し上げると、今、配転、私、昔、労働法をやっていまして、配転と解雇だったら、解雇の方がやっぱり大変なんですよね。これは免職ですから、より難易度は上がるわけでありまして。そうすると、これ一番大事なポイントなんだけれども、これが本当に動くだろうかと。私どもが、これ改めて申し上げますけれども、なぜ去年の臨時国会のときに、もちろんいろんな議論はあるのは承知しておりますけれども、首長に任命権をということと、それから、結局、首長だと、配転先の任命権者、人事権者も首長なんですよ。そうすると、同じ任命権者が教育現場から一般職員にということも考えて我々は同じ首長を任命権者にしたと、まあその議論はいいんですけれども。 しかし、我々と同じふうにしてくださいとは言いませんが、何かやっぱりきちっとリーダーシップを発揮して、不適格・不適切教員の問題に取り組む人が任命権者になるように、あるいは任命権者に座った人がそういうことに前向きに、門川さんのように取り組むような枠組みを用意しないと、引き続き京都だけもっともっとうまくいって、残りのところはうまくいかないということになってしまったのでは具合悪いなと。 それからもう一つは、思っていますのは、任命権者のリーダーシップの問題と、もう一つは、ここで言うところの審査会への認定申請者の問題もあると思うんです。結局、四十七条の二はその審査のこの、済みません、スキームにのっけて、もうちょっとこう口がぐちゃぐちゃになりますから許していただいて、そこにのっけるときに、基本的には校長ですよね、校長がその審査にのっけると。で、なかなかやっぱりのっけないですよね。 門川さんのすばらしいのは、そうした校長先生とか教頭先生とかもう全部お知り合いで信頼関係ができていますから、そこをうまく相談して、そこをうまく校長に、妙な恨みが残るとか人間関係が気まずくなるとかという、そういうところまでケアされているから京都はうまくいっているわけで、そうでないところは、やはり一緒に毎日仕事をしているチームの一員である教員を校長が、いや、これは不適格ですということを審査会に認定申請をするというところがボトルネックになっているんですよ。だから五百件なんですよ、と私は思っているんです。 だから、そこの部分を変えないと、だから我々はどう考えたかというと、もちろん校長、学校側もその認定申請者であっていいんですけど、加えて学校理事会がその認定者になれば、もちろんパラレルにやるということですよ、これはね。いろんな道を厚めにつくっておくと、ここのスキームにのっていくケースが多くてこれがうまく回るかなという判断なわけです、我々はね。 ですから、何かそこにそういう、その点についての手当てというか方策がないと、結局私はまた同じことになってしまうということを懸念しているんですけど、そこはどういう御議論なんでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)民主党案であった地方自治体の長に教育権を渡すということについては、その面についてはよろしいですけれども、先生がおっしゃったように、他にいろいろ問題があるということはおっしゃっているとおりだと思います。 それで、今般、安倍総理が私と菅総務大臣におっしゃった、法律はこういうふうに変えてほしいということの後言われたことは、教育委員を任命し、それに同意を与える地方議会というものが、本来地方自治の本旨にのっとって地方自治の在り方をよくフォローをすると、これが地方自治の本来の役割であるので、その由を促すようにということを菅大臣に言っているんですよ。 それで、今先生がおっしゃったことは、私は、これは文部科学大臣やってみて、まあ本当に何か靴の上からかいているようないらいらいらいらした気持ちで、心情的には、かつて西岡先輩がおっしゃったように義務教育の教員はみんな国家公務員だということであったら、先生の言っておられるようなことは一発で私やったっていいんですけどね。 現実には、地方自治というやはりもっと大きな、そして政治の不介入というもっと大きな建前があるから教育委員会というものを動かしているんですから、そこに何らかの手だてを、私どもももちろん、成功事例だとか何かを現行の法律の下でお示ししたりして、地方の教育委員会に要請をいたしますよ。要請というかお願いをいたしますけれども、指示はできないわけですから。 だけれども、本来は、おたおたしている教育委員会、教育長の行政上の、何というか、不満足さをしっかりと指摘すべきは本来は地方議会なんですよ。地方議会がしっかりした機能を果たさなければいけないんですよ。未履修の問題にしろいじめの問題にしろ、今、地方議会が何か具体的に自分たちの任命した教育長や教育委員がうまく学校を管理していないということについて積極的にどういう関与をされたのかということが分からないから、今、指示の問題だとか何かが出てきているわけで、もう少し、今度地方統一選挙がありますから、しっかりその点も踏まえてみんなが地方統一選挙に臨みたいと、私はそんなことが本当の地方自治の在り方じゃないかと思います。 鈴木寛君私もおっしゃるとおりだと思います。地方議会がもっとしっかりすればワークすると、それは私も同意です。 しかし、私も県庁の勤務がありますが、ワークしなかったわけですよね。お言葉ですが、少なくとも五十年間。お言葉ですが、地方議会における自由民主党の議席のシェア率というのは大変な高さです。だから、そこにお任せを、だからこういうことですね。中教審といいますか現政権は、もう一回地方議会に覚せいを促して、お願いをしてやってみると、そこにもう一回ワンチャンス与えてみようと、こういうことですね。 だから、我々はそこの認識が、もう五十年やって無理だから、だったらもう住民の、要するにどこかで民主的統制を利かさなきゃいけないんですよね。方法は二つあって、文部省が上から介入をすると。しかし、これ三万校ある本当に全学級をというのはなかなか難しいから、これだけでは無理だというのはもう皆さんお分かりになっている。最終的な手段として残そうという、大体大臣と我々は同じ、少なくとも個人的な大臣の見解と我々はそこは大体同じようなことで、今回の最終的な是正要求というのはそういうことで出てこられたと思いますが。 しかし、それをもっても、三万校の日常を文部科学省が管理することは、文部科学省だけで管理することは難しいですから、どうしてもどこかに民主的統制を掲げなきゃいけない。それの一つは地方議会だというのは、それは賛成です。しかし、地方議会がワークしない、あるいはワークしてこなかったという認識の下で、我々はそこに学校理事会というのを設けて、正に一番の子供の代弁者である地域の方とか親の方のお力もかりよう、そういう部分もかなり入れていただいていますから、そこの合わせ技で、まあとにかく今回は頑張ってみようということかなというふうに理解したんですが。 それと、結局、教育委員会と教育長というのの仕事を少し切り分けて、今まで何でも教育委員会、非常勤の委員会の人たちでしたけれども、教育長にかなり権限も寄せて、そこを教育長が動かない場合にはやっぱり教育長の責任をきっちと問えるということに整理されたんだと思いますが、教育長の任命権者はどうなるんですか、今回の中教審答申では。 国務大臣(伊吹文明君)それは従来どおりでございます。そして、であるからこそ、我々は任命する首長と任命を承認する地方議会の役割が大切であるから、本来の地方自治の役割を果たすように促すべしという総理の総務大臣への指示が付いていると。ですから、先生の方で学校評議会だとかあるいは監査委員会的組織をつくるというのは、それは一つの提案として結構ですよ。しかし、事、地方自治の一つの組織である教育委員会については、ダブルスタンダード、ダブルスタンダードはいけないですね。地方議会ともう一つつくるということは、これは多分私はよほど国民的議論を経ないと、地方議会の否定論につながりかねないおそれがありますから、ここはやはりしっかりと詰めてから、我々ももう一つ何かかまそうかなという考えはあったんですけれども、これは憲法上の大問題を招来しますよ。 鈴木寛君本当にそこが悩みどころですよね。ですから、私たちは結局そういういろいろな、これは何でも作用と副作用ということだと思います。我々は、やっぱり国民の皆さんが一番願っておられるのが教育現場から不適切な教員を排除するということが現場の保護者のニーズからすると高いんですね。それに一番効く薬というのは我々の考え、もちろん副作用があるということもこれは比較考量しなきゃいけませんが、まあそういう判断をしました。 逆に、民主党が考えておりました監査委員会的教育委員会にかなりなっていますから、そういう部分は我々のお知恵も取り入れていただいたのかなと。だから、教育長がかなり専権的にできて、しかしきちっと教育委員会はそれを監査というかコントロールするし、それから主要なビジョン的な話というか大きな枠組みは教育委員会が議論するという、こういう整理をしていただいたのかなということですから、我々の提案も三割ぐらいは入れていただいているんで、これで走ってみていけるのか。我々はちょっと地方議会に期待するというところが──それは分かりました。四月の二十二日のときにそれを、伊吹文部科学大臣はそういうことを地方議会に、いや、僕は健全なことだと思いますよ、我々もそういうことは日ごろ言っておりますから、それをめぐって各地元地元でいろいろ考えていただいたらいいなというふうに思います。それは別に率直にそういうふうに思います。 それで、あと、済みません、やっぱり指導不適切教員のところなんですけど、判定基準ですね、ガイドライン、これはどういうことになりますかね。これ、これまた結局不適切教員とかって難しいですよね、これは。結局、一律の何か基準があって、これはペーパーテストとかをやるわけにもいかないし、しかもやっぱりこれ人の身分にかかわる話ですから、そこでの客観・公正性ということは、当然これは確保しなければいけないということになると、このガイドライン果たしてできるかなと。そういうこのスタンダードで難しいときは、やっぱりプロセスをきちっと決めて、この人たちがちゃんと議論を尽くして、やはり不適切だと、あるいはきちっとした審査の委員会に上げていこうという、行為で無理なときはもう手続で縛るしかないですよね。 ということで、学校理事会での十分な審議、そして審査会での、この審査会は京都でやっておられるやつを参考にして、あれは非常によく僕もできていると思いますし、お医者さんとか臨床心理士とか、あるいは人権委員とか入って、あれを取り入れられるというのは僕も大賛成なんですけど、そういう中でガイドラインのお話もこれはなかなか難しいと思うんですね。 ですから、私、これは今日ずっとというかこの間の、十二月までは毎日のように大臣と席を並べさせていただいたんですけれども、それ以後しばしごぶさたをしていたんですが、文部省の枠組みの中でできることについてはよく考えられていると思います。しかし、全国三万の学校現場を文部省の努力だけでというわけにはやっぱり難しいと思うんですね。そうすると、やっぱりどれだけ現場の力というか、それは教員であり保護者であり地域の方であり、そういう方々の良識とか、あるいはそういう方々の御努力、献身というものを引き出すガバナンスというものを必要なんじゃないかなというふうに思っていまして…… 国務大臣(伊吹文明君)ガバナンス駄目だよ。 鈴木寛君私、さっきあきらめましたから、時間がなくなってきましたので。 そういうやっぱりガバナンスをつくるというところの一工夫がないと教育現場は良くならないし、やっぱり一九五六年の地教行法以来の大改正ですよ、だって教育基本法を改正したわけですから。だから、その改正教育基本法に見合う教育現場のガバナンス、あるいは教育行政のありようということにまでやっぱり踏み込まないと、そのことが文部省と相まって、その一つ一つの極めて、結局難しい話だから残っているわけですよね、不適切教員とかの話というのは。というふうに私は思いますが、ガイドラインの話と単に地方議会にのみ任せるのではなくて、もう一歩踏み込んで、現場の現場力を引き出すための枠組みをもう一ひねりといいますか、もう一工夫必要なんではないかという私の御意見でございますので、それをどういうふうにとらまえていただくかあれですが、法案作成の際に御検討いただければ有り難いなというふうに思います。 委員長(狩野安君)よろしいですか。 鈴木寛君ガイドライン。 政府参考人(銭谷眞美君)先ほど来、先生がいろいろお話をされておりました、校長だけがまず不適格教員の申出ができるのかといったような点とか、それから判定基準をどういうふうに作るのか、それから言わば不適格教員の認定のシステム全体の運用、過程をどういうふうに押さえていくのか、そのためのガイドラインをどうするのか、これらいずれも答申におきましても制度設計の留意事項として今後詰めていくべき事柄として示されておりまして、直接法にどこまで規定するのかということとは別に、実際の運用に当たりまして、私どもそういう点はやはりよく心掛けて検討していかなきゃいけない事柄だと思っております。 鈴木寛君ありがとうございます。 やっぱり最後のだるまに目が何か入っていないなという感じがありますので、そこを入れてまた立派な法案を御提出いただいて、御議論を深めさせていただければと思います。 どうも今日はありがとうございました。 |