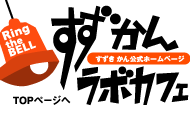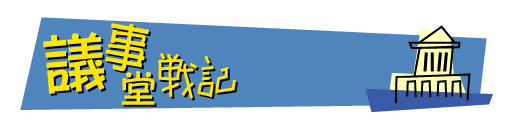2006年12月14日 文教科学委員会鈴木寛君民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。 著作権法の一部を改正する法律案の質問をさせていただきたいと思います。 まず、火曜日にも提案理由説明を承りましたけれども、改めましてというか、時間も少し削られましたので、今回、百二条の三項を改正をといいますか、三項ということで追加をしております。今回の改正法の第一条でありますが。これは放送同時再送信の円滑化のための法改正だと、こういうふうに聞いておられますが、この概要について御説明をいただきたいと思います。 政府参考人(加茂川幸夫君)お答えをいたします。 御指摘の改正法の中身でございますが、いわゆるIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について必要な手当てをするものでございます。このIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信は、地上デジタル放送への全面移行に当たりまして、難視聴地域において放送が受信されるための重要な手段として期待をされておるわけでございます。しかしながら、このIPマルチキャスト放送は著作権法上のいわゆる自動公衆送信に該当いたしまして、原則として実演家等の許諾が必要な利用形態となるわけでございます。 今申しましたように、この同時再送信は平成十八年末に開始される予定でございますから、この円滑な実現を図るため、一定の範囲内におきまして実演家等の事前許諾等を制限するなど速やかな制度面の整備が必要でございまして、このような規定を設けようとするものでございます。 鈴木寛君地上波デジタルが進むにつれて、その補完路としてIPマルチキャストを使うと。その際に必要となる著作隣接権について、従来の放送と同様の、何といいますか、例外措置といいますか、恩恵措置といいますか、優遇措置といいますか、そういうものを及ぼすと、こういうことであります。 今の、何といいますか、制度改正の目的、趣旨については、私は何ら異存を挟むものではございません。正に全国津々浦々まで情報が行き渡ると、そこで正に地デジと、それからITあるいはインターネット、インターネットプロトコルを使った通信、これをベストミックスでもって届けると、こういうことであります。 しかし、今日御議論をさせていただきたいのは、ちょっと条文を読みますと、そのようになっていないというか、分かりづらいというか、いう条文になっております。率直に言って、もう少し違う書き方があったんではないかなというのが私の率直な感想でございます。 もちろん、いろいろ御苦労されて、法制局もお入りになってお作りになったということなんですけれども、私は、ちょっとその書き方、正にこれは立法技術の、姿勢の問題ではなくて技術の問題なわけでありますが、について若干の疑義といいますか、懸念がありますので、その点についてお伺いをしていきたいというふうに思います。 先ほど次長は、これは同時再送信について手当てをするんだとおっしゃいました。私も、同時再送信の限りにおいてその手当ては妥当だろうと思いますが、これはちょっと言い方をどうしますかね、新百二条の三項と言った方がいいのか、ちょっと言い方があれですが、いわゆる今回のその規定、どこで同時再送信だということを限定しているのかというのが分かりづらいんですけれども、そこをちょっと教えていただけますでしょうか。 政府参考人(加茂川幸夫君)お答えをいたします。 御指摘の百二条三項の改正案でございますが、この条文をごらんいただきますと、「著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、」と書いてございます。この「放送されるものは、」という表現が、その放送されたものではないという比較において、これは同時再送信だという私どもは解釈をしておりまして、十分法制局とも詰めておりますし、現行の規定が、他の規定もこれに倣っておるわけでございまして、特に問題はないのではないかと、分かりづらいことは事実でございますが、そういう解釈に立っておるわけでございます。 鈴木寛君これは確認ですが、そうすると、ビデオ・オン・デマンドは入らないということでよろしいですね。これは恐らく、正に今日の議論を基に著作権法改正のコンメンタールを作るということになろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。 政府参考人(加茂川幸夫君)そのとおりでございます。 いわゆるビデオ・オン・デマンドは、過去に放送されたものを蓄積いたしますので、その放送されたものに当たりまして、ここでは入っていないわけでございます。 鈴木寛君それと、これは私の私見で申し上げますと、やっぱり電気通信役務放送というふうに書いた方がすっきりしたなというのが私の意見であります。 というのは、新百二条第三項を、ちょっとくどいですが、今何の話をしているのか各委員の方々がお分かりになりづらいと思いますので御説明申し上げますと、著作隣接権の目的となっている実演放送であって放送されるものはと、ここが今同時送信だということをおっしゃいました。「専ら当該放送に係る放送対象地域」、こう云々、こういろいろありまして、「放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化を行うことができる。」と、こう書いてあるわけですね。 これだけ読みますと、主体がはっきり書いてないものですから、個人でも、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として送信可能化した場合には、この正に例外が適用されてしまうという懸念が生じてしまうと、こういうことなわけでありますが、なぜこういう書きぶりにしなければいけなかったのかということをちょっと再度御説明いただきたいと思います。 政府参考人(加茂川幸夫君)委員御指摘のような懸念があるということについては、否定できないといいますか、御指摘の趣旨がよく分かるわけでございます。すなわち、今回の改正では、自動公衆送信による放送の同時再送信につきまして、原放送の放送対象地域内に限って実演家等の権利が制限されることとしておりまして、その主体者については明定されていないからでございます。個人も含まれるではないか、御指摘のとおりだと思っています。 ただ、ここでポイントとなりますのは、原放送の放送対象地域内に限定をしておりますので、個人がインターネット等を使ってマルチキャスト放送と同じ事業等を行おうとする場合に、それが可能かということを私ども検討したわけでございます。ところが、通常のインターネット放送も、形では自動公衆送信に含まれるわけでございますが、現在の技術レベルを前提とする限り、個人が行うインターネット送信については、今申しました、くどいようでございますが、原放送の放送対象地域内に限定して送信することは困難であると私ども理解をしておりまして、実際問題として個人がここにかかわってくることはほとんどないのだと理解をしておるわけでございます。 鈴木寛君今の条項は少し括弧書きが一杯あって皆様方も分かりにくいと思うんで、同じようなことを目的とした要するに書きぶりが三十八条の二項の改正案にもあるんで、是非ごらんをいただきながら、今何をやっているかといいますと、結局IPマルチキャスト放送による補完路としての同時再送信について隣接権の例外を認めると、その書きぶりの、書き方を議論をしておりまして、三十八条の方がちょっと分かりやすいと思いますけれども、要するに、専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信を行う、要するに、ということがこの同時再送信だと、IPマルチキャストによるということなわけでありますが、で、それについては例外を設けてもいいと、こういう話をしているんですけれども、私が主張しているように、電気通信役務放送事業者というふうに書いてないものですから、別に、例えば私個人でインターネットテレビ局やっております。それは非営利でございまして、料金もいただいておりません。そうすると、例えば東京の皆さんから、ビルの陰で難視聴のところがあって、そういうところに、例えば地デジで送られてきたものをもう一回見やすくして、しかしこれは放送対象地域というふうに限定されていますから、東京の人しか見ないでくださいときちっと目的をうたって、しかし東京の人でしか見ないでくださいと言っても埼玉の方が見るかもしれませんから、インターネットですから見るかもしれませんから、そのことを担保するために、例えば住所と名前ときちっとお届けをいただいたらこのサイトを見るかぎを、電子暗号かぎをお渡ししますと、こういうことのサービスを無料で始めるということがかなり読めてしまう。これをすごく懸念しているわけで、やろうとしていることはいいんですけど、結局いつも大臣がおっしゃるサイドエフェクトをどういうふうに最小化というかこれはゼロにしないと、権利設定の問題ですからゼロにしないといけないということの今確認作業をしているわけでありますけれども、今のような解釈が成立し得るわけですね。 で、そういうことを個人でおやりになる。まあ、インターネットの世界は本当に個人がいい意味でも悪い意味でも創意工夫を最大限に発揮して、そしていろんなことを本当にボランタリーに、かつ善意に始められるということもありますので、この条文を見た方がそういうことをおやりになっても全然不思議じゃないというふうに読めてしまうんですけれども、それはこれで、今の私があるいは個人がそういうことをやろうとしている分はここでこういうふうに読むんだと、あるいは解釈するんだと、あるいは逆に言うと、いや、それは漏れてますということになるともう一回審議やり直しと、これこそ出し直しという話になるわけですが、ちょっとここの解釈を教えていただけますでしょうか。 政府参考人(加茂川幸夫君)繰り返しになりますが、この同時再送信の事業等の主体者としては、個人が排除はされておりません。一応、法文上は、理論上は対象になるわけでございますが、権利制限の要件として地域限定ということを掛けてございますので、個人がインターネットの手段を通じて同時再送信する場合には地域限定が掛かりません。無方向、無定限にその送信がなされるわけでございますから、この地域限定の要件をクリアできないためにこの改正法案の対象にはならない、ほとんど技術上その限定ができないために不可能であり、対象にならないと考えておりまして、問題はないんだと、こう思っております。 ただ、委員御指摘の、電気通信役務利用法を引いて何か限定ができないのかというその法的な手段については私どもも十分検討させていただいたわけでございますが、今回のIPマルチキャスト放送による放送の同時再送信につきましては、この役務利用放送法に基づく事業者が行うことを私どもも期待をしておりますし、期待されておるわけでございます。個人よりもこういう事業者が期待されておるわけでございますが、その範囲が異なる放送法制上のいわゆる放送概念を、そのまま概念が違っております著作権法に導入することが適切ではないのではないかという判断基準が一つございました。 また、著作物の利用形態が同じであれば、著作権法上はその電気通信役務利用放送法か否かで扱いを異ならせる必要がないのではないかといったまた判断基準もございまして、今御提案申し上げている法案になっておるわけでございます。 鈴木寛君今の御説明は、現行のIT、IP技術によると、専ら、要するに当該地域だけに限定するということを専らということで言っているんだと思いますが、限定をして情報のディストリビューションをするということが不可能なので、専らできるのはIPマルチキャストしかありませんと、こういう御説明で、IPマルチキャストをやれるのは、今のところはそうした事業者ですと、こういうお話でありますと。 しかし、それは現状においてでありまして、このITの世界というのは日進月歩でございます。それで、事業者だからとか個人だからというところをよりどころとする差というのは実は非常に薄い。だからこそ、ベンチャー企業がどんどんどんどん出てくるわけでありまして、しかも今特許だけで見てみますと、そうした配信先を限定して、コントロールして配信をするという技術は、既に幾つかの特許があります。それが正に事業化されてないだけのことであって、今でも要するにそのバーチャル・プライベート・ネットワーク、VPN網みたいなところでその配信先限定をしていると、こういうことで、それはマルチキャスト事業者しかやっていませんよと、こういう話なんでしょうが、そこを事業者しかやらせてないというか、やれない、その根拠というのは法制的にどこにあるんでしょうか。どちらでもいいですよ、総務省でも。 要するに、文化庁は、そういう技術を駆使してそういう事業ができるのはIPマルチキャスト事業者しか今のところないとおっしゃっている、今のところないことは事実ですと。だけど、技術ですから、それを駆使できる人は、個人だろうが事業者だろうが、技術は駆使(発言する者あり)いや、私も、私の友人はそれ駆使できますので。それをしかし、技術によって法律の伸縮があるというのは、これ法律論というか法律の立法の在り方としては不適切ですね、技術が日進月歩になるところ。なぜならば、権利が確定しませんから、そうすると、その法的安定性と予測可能性が揺らぐという話ですから、それは法制としてよろしくないと。 したがって、これは法制論としても、正に地デジの補完路として同時再送信をやる者だけに限っているんですという法制上の担保というのが必要だというのが私の主張で、それはどこにどうなっていますかという質問です。 政府参考人(加茂川幸夫君)委員がおっしゃいました、特許としては確立しているけれどもまだ事業化されていない技術があるんだということについて、残念ながらその詳細は承知をしていないわけでございますが、仮にそのような技術が事業化になって、何度も申しますが、原放送の放送対象地域を限定してインターネット送信ができるという事態が生じた場合、それは個人であってもそういう事態が生じて活用して同時再送信をしようとしました場合には、この法改正の範囲に入ってまいります。すなわち、権利制限の対象になってまいります。私どもはそれを想定をしております。ですから、技術が進んできて地域限定ということがきちっと掛かるんであれば、現状ではそういう事態はあり得ないと理解をしておるわけでございますが、将来そういうことがあるんであれば、権利規制、権利制限の対象になってくると思っています。 ただ、同時に考えなければなりませんのは、そういった事態が仮に生じたときに、その送信のその態様にもよるわけでございますが、その権利者への影響が大きい、権利者への不利益が無視できない状況が生じてくるという、そういう状態にまた加えてなった場合には、改めてその法制度をどうすべきかといった見直しの議論が検討課題になってくるんだと私どもは認識をしておるわけでございます。 ただ、現時点ではどこまでその技術が進み、それが事業化できるのかという見通しが立たないものでございますから、こういった形態で法案審議をお願いをしておるわけでございます。 鈴木寛君これ、実は今月末にも、これも提案説明のお話でありましたけれども、こういう実態といいますか実験というかですね、が始まるので、このような異例な審議日程といいますか、教育基本法の審議の合間に、休憩中でございますので、今やっているということで、もちろん私も日本のインターネット社会の発展のために寄与したいという思いで、二十分前に質問せよと言って、させていただいているわけでありますが、これ厳密に言うと少し危ないというか、これはもう大臣うなずいておられますが、だからこのことはやっぱりきちっとシェアしておいた方がいいと思うんですね。 既に、研究というか特許ではそういう技術が開発されていますと、それがもうあるわけですね。で、じゃ今次長は、権利関係の見直しの要否を再度検討する必要があると。これは私も必要があると思います。なぜならば、今回はその補完路としての同時再送信だと言って提案しているわけですから、その前提が崩れたらもう一回議論し直しだ、まあだから議論し直しますというふうにおっしゃっているわけだけれども、その一方でその技術はもう既にあって、いつだれが事業化するかどうか分かりませんと。 で、そのときに一人が事業化した場合、複数事業者が事業化した場合、あるいはその事業のそのユーザーというものが何人になった場合、十人の場合、百人の場合、千人の。しかし、法的に言えば、一人が一人に、まあ一人が一人ではマルチキャストじゃありませんけれども、一人が複数者に行った瞬間にそこは発生してしまうわけで、これで合法的に、一時的ですけれどもね、要するに次の改正がなされるまでは一時的にそういう状態が発生してしまうわけで、そしてそれをまた後に議論をし直してできなくしますと、こういう話で。 御存じのように、著作権法というのは別に国と事業者の規制の問題ではなくて、正に民民の、民法上の権利関係を整理しているという重要な法律でありますので、この法律はそういうものを含んでいる、それを常に認識しながら、常々その実態を、何というか、吟味していかなきゃいけない。で、もしもそこを怠るならば、同時再送信の円滑化の補完路だということで提案理由を言うからそういう問題が起こってくるわけで、そもそもこういうものについてやります、しかしそうなると今度また権利者が違う意見が出てくるということでの調整の中での、まあ正直妥協の産物というか、その現実を見据えた上での妥協の産物なんですけど、民法規定においてそれをやるということのリスク、リスクというか危険性、サイドエフェクトということも、まあ私は強く指摘をさせていただくとともに、これはやっぱりある意味で、まあだましているとは言いませんけれども、その前提が変わりますから、個人がやり始めた場合には、個人がやり始めた場合には。だから、そこは本当にちゃんと権利の見直しということは、やはりちゃんとやっていただきたいと、こういうことで思います。 何か総務省で、この論点に付け加えることありますか。 国務大臣(伊吹文明君)立法論としては、先生のおっしゃっていることはよく分かります。 現時点では、先ほど政府参考人が申し上げたように、一つはこれもうそろそろ総務省が始めるということですから、実験的に、文化庁というか、当省の立場からすれば、著作権の権利を新しく始める中で守っていく、あるいは阻却してあげなければいけないんで、まあこういう極めて異例な、今御指摘のような事態でお願いしていると。同時に、技術的には特許権等もありますから、将来、先生が御指摘になったようなケースが生じ得るのは、これはもう当然のことなんですね。 そのときに、この事業を特許権を持っている人が始めるかどうかというときは、当然総務省がかんでくるわけですから、その著作権の方を野放しにして、総務省が、その先生の言っておられる新しい技術に、特許権に裏打ちされた事業に個人が入ってくる場合に、これは、今度だってこれはまあ率直に言えば総務省が新しい仕事、新しいジャンルに入るからこうしてお願いをしているわけで、今度先生がおっしゃっているような事態が生ずれば、当然権利を守るまでは許可をしてもらっちゃ困るわけですから、そこはよく連携をしてやっていきたいと思います。 政府参考人(中田睦君)お答え申し上げます。 今、大臣から御説明ありましたように、私ども総務省の立場といたしましては、今地上波テレビを二〇一一年の七月までに完全にデジタルに移行するということで準備をしております。平成三年に東名阪でスタートいたしまして、最終的に二〇一一年の七月に完全にデジタルに移行するということでございます。 その中で、順次、中継局等の整備を進めておりますけれども、電波で届かないエリアにつきましては、現在でもCATVによりまして再送信がなされております。さらに、それに加えまして、新しい技術でございます、新しいプレーヤーでございます電気通信役務放送事業者によりまして再送信がなされるということは、この地上波デジタルへの完全移行に大きく寄与するものであるというふうに考えております。 そういう意味で、現在、CATV事業者による再送信につきましては、著作権法上の処理等が既に手当てされていまして円滑に進んでおるということでございます。それに対しまして、役務利用放送法につきましては、既に技術的にはこのIPマルチキャスト方式によりまして役務を提供できる状況になっております。そういう中で、自主放送はできますけれども、この再送信ということになりますと、どうしても権利処理の問題がクリアになりませんと円滑に進みません。そういう意味で非常にお願いをしているということでございます。 それで、将来新しい技術等が出た場合という議論でございますけれども、IPマルチキャスト方式以外に新しい同時再送信ができるような技術ができた場合には、その場合には電気通信役務放送法の事業者として登録をするという手続がございまして、そういう中で文部省さんと連携を取って進めてまいりたいというふうに考えております。 鈴木寛君これは、ある意味で文部科学大臣が総務大臣に貸し一の話なんですよね。いや、本当そうなんですよ。これは、だから文教科学委員会としてはちゃんとシェアしておかなきゃいけない大事な情報でありまして、本当にそうなんですよ。なので、総務大臣によくお伝えをいただきたいと思うんですが。 今、審議官から、IPマルチキャストをやる人が出てくれば登録しないといけないと、電気通信役務利用放送事業者として。もしも登録しないでやっていればそれはアウトと、こういうことになりますね。これはあれですか、個人であってもこの事業者登録はできるんですか。 政府参考人(中田睦君)電気通信役務利用放送事業者としての登録につきましては、法人に限定しているという規定はございません。 鈴木寛君分かりました。 それでは、先ほどの次長のお話にもありましたけれども、結局、著作権法で何で電気通信役務放送事業者と書けなかったのかという理由は、正におっしゃったように、法律によって放送という定義がばらばらなんですよ。だから、電気通信役務放送事業法で定める放送のデフィニ、定義と、それからもちろん放送法で定める定義と、有線テレビジョン放送法で定める定義と、これは総務省の所管している法律の中でもばらばらですと。さらに、文化庁が所管される著作権法の中での放送というものもこれまた違うので、引っ張ってこれませんねと。法律の世界の理解では法律ごとに定義は変わってよろしいということなので、別にそれは法制的にはそれでオーケーなんですが、しかし、こういう問題が逆に生じているという話でありまして。 さて、じゃ、そこで改めてお伺いしますけれども、総務省と文化庁に両方聞きます。放送の定義をしていただきたいと。総務省から。 政府参考人(中田睦君)お答え申し上げます。 情報通信分野におきましては、国際電気通信連合の定める定義に基づきまして各国内法制を整備するということになります。 具体的に、我が国では、放送法におきまして、放送は公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信というふうに定義されております。 政府参考人(加茂川幸夫君)著作権法上におきます放送の定義でございますが、放送とは公衆送信のうち、公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいうと、こう定義されてございます。 鈴木寛君総務省は今、放送法の定義をおっしゃいましたが、放送法では無線という要件が入りますね。しかし、電気通信役務利用放送とか有線放送とかは無線という要件は入りませんが、その場合に、引き続き、放送としての要件というのをもう一回おっしゃっていただけますか。 政府参考人(中田睦君)御指摘のとおりでございまして、放送法は無線を前提にしておりますので、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信というふうに定義をされております。それに対しまして、有線テレビにつきましては、公衆によって直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信と、無線と有線電気通信というふうに分けて書いてございます。それ以外の点は同じ定義になっております。 それから、今お話がありました電気通信役務利用放送法の放送の定義でございますが、これにつきましては、有線と無線を両方含んだ概念でございまして、両方あり得るということでございます。そういう意味で、電気通信役務利用放送法では、公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信というふうに定義をしておりまして、有線、無線を含んだ概念である電気通信の送信というふうに定義をしているところでございます。 鈴木寛君これ、総務省の定義をひっくるめて言うと、共通しているのは何かというと、公衆によって直接受信されることなんですよね。で、伝送路はいろいろあるわけですよね、というふうに総務省の説明はできるわけです。一方、文化庁のおっしゃっているのは、それに加えて、同時という、同時、同一内容ということが。だから、ここの違いが結局、電気通信役務利用事業者という条項をこの著作権法改正法の中で使えなかった理由なんです。 私は、その総務省の、公衆によって直接受信されるということをもって放送としている定義、要するに文化庁の言うような同一・一斉放送性といいますか送信性というものを必ずしも要しないという放送の定義は、やや広過ぎるというふうに思っております。 それで、例えばギャオというインターネットテレビ局ができております。今、インターネットテレビ局がどんどんどんどんできています。これテレビ局と言われていますから、皆さん放送だと思っておられる方も大勢いらっしゃると思いますが、これはIPマルチキャスト放送ではありませんね。それで、ギャオも時々同時中継に類した、まあこれはユニキャストっていうんですけど、マルチキャストではなくてユニキャストという放送をやっていることはあります。これは別に大した技術じゃございませんで、私も毎週水曜日、すずかんドットTVというテレビ局をやっておりまして、これは基本的にはディレーは一秒以内。これを、一秒以内を同時かどうかというのはありますが、ほぼ同時。ほぼ同時のインターネットテレビ局を私自身も主宰をしています。しかし、これは同時ではありません、技術的に言えば。 放送でいったって、〇・〇〇何秒はそれはずれるわけでありますが、これ難しいんですよね、何が同時か同時でないか。地上波電波によるものはこれは同時だろうと、まあこれはいいでしょうと。それから、マルチキャストという一対多で、少なくとも送る瞬間は同時で送っている。これ、だから今の放送の定義は、放送法の方もそうですけど、電波で発信する瞬間とかIPマルチキャストを発信する瞬間の発信側の同時性が担保されていればこれは同時だという解釈に今立っているわけでありますと。 これは文化庁は、文化庁はというか、だから次長はよくうなずいていただいていてあれなんですが、総務省は同時というのは関係ないんですよね。そうすると、これはユニキャストも入るんですかと、ユニキャスト入ったらVODも入るんですかと。これ、どこでどういうふうに線引くんですか。これ分からないんですが、これどう考えておられますか。 政府参考人(中田睦君)先ほどの定義については御説明申し上げましたけれども、私どもの方のこの放送の定義の解釈といたしまして、まず委員の方からギャオについて御指摘がございましたけれども、ギャオの配信方法というのは、生中継でございましても、その受信者の方の個々のアクセスに応じまして、そのアクセスした者に対してギャオの映像配信元のサーバーから個別に送信をしているという形態でございます。それに対しまして放送というのは個々の者に個別に送信をするという概念ではございませんで、一つの送信、一の送信によりまして複数の者に送るという概念でございます。 そういう意味で、ギャオは放送ではないというふうに解釈しております。 鈴木寛君これ、非常に重要なポイントなんで。 総務省は今、この放送概念の拡大という野望を抱いているんですね。それは、通信と放送の在り方懇談会で、そもそも放送は、こういう今回の提出のあった地デジの補完路としての隣接権の例外のみならず、著作権法上広く放送が享受している著作権法上の権利処理をあまねく広く放送に及ぼしてほしいという報告書が出ているんですよ。したがって、私がこの放送概念、まあここでまた伊吹大臣が総務大臣に貸し二にするのか三にするのかあれですけど、これ非常に重要な問題なんで、別にどっちの肩を持つという話じゃなくて、これ全体としての権利設定をどういうふうなところにウエルバランスさせるかという話なんで。 もう一回確認しますけれども、これから技術がどんどんどんどん進んでいきますと、技術的な方式として見れば、オーディエンス、見る側が、見る側が取りに行くと言っても、別に手で取りに行っているわけじゃなくて技術的になんですけど、見る側がわざわざギャオのサーバーにアクセスして、そしてそこからその情報をダウンロードして見ているわけですね。しかし、それが技術的には一つ一つやっているんですが、それがもう余りにも高速で、一見すると同時再送信に近い。このディレーはどんどんどんどん縮まっていきます、これから。今でも相当縮まっていますけれども。そうなった場合にでも、そうなった場合にでも、引き続きそれは放送でないという考え方を貫かれますねという確認です。 政府参考人(中田睦君)放送概念自身は、これは先ほど申し上げましたように、国際的にも国際通信連合というところで定義をされておりまして、各国とも同じような形で定義をしているということで、放送の概念自体はこれはもう定着したものだというふうに考えております。 それで、先生御指摘の点は放送には当たらない従来の通信の世界でございますけれども、こちらは、通信の世界は従来はほとんど、電話のように秘匿性を有する個人対個人の通信が圧倒的なボリュームを占めていたと。それが、昨今ネット上で流れる情報というものが、公然性を有する情報というものが非常に大量に出てきたという事態に変わってきたということでございまして、そのような新しい事態が生じてきますと、そのような公然性を有する通信が頻繁に出てくることによる社会的影響等をどうとらえていくかという問題がこれは国際的にも問題になっておりまして、いろんな検討が進んでおります。 そういう意味で、新しい事態が生じましたら法制度も新しい対応をしていくということはある意味当然のことであると思いますけれども、そういう意味におきましても放送概念自身を変えていくという必要は必ずしもないんではないかというふうに思っております。 鈴木寛君今のは非常に重要な答弁でありますので、私も心に留めたいと思いますが。 放送事業者になると、あるいは放送を行う者になると、先ほどは、著作権法上の適用除外といいますか優遇ですね、権利処理の、事業者の側からすれば少しは手間が省けているわけですから優遇措置と言っていいと思うんですが、一方で、放送事業者であるがための様々な規制が掛かってまいります。通信事業者であれば、これは憲法上も通信の秘密等々がありますから、ほとんど内容に関する規制というのはありません。しかし、放送法ではその放送内容に関して一定の規制が掛かっております。それから、昨今は、命令放送といった議論もこの国会で非常に重要な議題の一つだったというふうに思いますが。 そもそも何で放送事業者がある特典、著作権法上の特典を得たり、あるいはそうした放送法上のある種の義務を課せられたりするかといえば、地上波については有限な公共の社会資源である電波、これを特権的に利用させてもらっている、あるいは利用しているのでそこにその事業の公益性というのも出てくる、したがって様々な義務も一定程度掛かるという法律体系になっているわけでありますと。 私は、放送事業者に様々な諸規制、諸義務を課すリーズニングというか根拠というのは、有限な社会公共資源である電波を特権的に使っているからだというところに求めればいいと思っていますが、学説にはいろいろありまして、総務省は、今のことは通説なんですね、プラスアルファの部分が、その幅が学説によってあるわけでありますが、どういう見解を取っておられるんですか、その点については。 政府参考人(中田睦君)今委員御指摘のとおり、放送の規律の根拠について学説が諸々ございますということは、そのとおりでございます。 それで、私どもとしましては、放送法の規律の根拠ということになりますと、一つは社会的な影響力が極めて大きいことということ、それから有限希少な周波数を占有するものであることということから、公共の福祉に適合するように放送を規律をするということであると、そういうことで放送ができているというふうに考えております。 鈴木寛君今さらりと社会的影響が大きいということをおっしゃいましたけれども、これ極めて重要なポイントでありまして、学説の争点もそこだと理解をしております。社会的影響が大きいから規制をする、あるいは逆に言うと、緊急時などは緊急放送とか様々な災害情報の放送をお願いをするという、もちろん私も一定程度、特に災害時における放送事業者のそういうふうなことをお願いをするということについては妥当だということは思っているんですよ、思っているんですけど、社会的影響があるから規制するんだという粗っぽく議論をしてはいけないんだと。それはやっぱり相当きちっと切り分けて、社会的影響があれば、じゃ規制していいのかと。 放送法の規制内容は、明らかにコンテンツ、表現の自由、表現内容にかかわる規制をしているわけであります。あるいは、表現内容というものには、表現のタイミングとか、あるいはそれをコミュニケーションする、伝える、放送する相手方とかということもこれは当然に表現の自由あるいは報道の自由の中に入るわけで、ここがみんな悩んでいるわけでありまして、だからこそ国会で、どこが一番きめ細かく、境界線というんでしょうか、場合分けをして、それが社会正義に照らして妥当なのかどうかということを一つ一つチェックしていくということが必要だということを申し上げたいので、社会的影響とざくっとくくるだけでは議論は足りませんよということを指摘させていただいているわけであります。 国務大臣(伊吹文明君)まず、総務大臣に貸しを持っているのは私じゃなくて今日御審議をいただいている参議院の文部科学委員会の先生方でございますので、その点は間違いなく確認をしておきたい。国会が今おっしゃったようにどうするかということを最後に決めなければなりません。 今御指摘のあったことは二つの意味を含んでおりますね。社会性というか公共性という言葉でもって著作権若しくは著作隣接権を制限されるということからくる影響が一つありますね。それから、まあこれは私は口を出すことじゃありませんが、放送法、通信法上のいろいろな一種の規制というものが良質な情報の伝達をどこまで担保していけるかと、あるいはそれを阻害するということになるかということだと思います。 したがって、我々の立場からすると、著作権若しくは著作隣接権を基本的にはやはり守ってあげると。そして、守ってあげるんだけれども、公共の目的のためにはそれを制限するということをやらねばなりませんから、どこまで制限するかということは、これは国民の権利義務に関することでございますので、最終的には、これは総務省だけでもちろんお決めいただく問題ではありませんし、ありていに言えば、権利義務にかかわることは一つ一つ、先生がおっしゃっているように、立法機関において審査の上措置をしていくと、これはもう当然のことだと思います。 ですから、放送の概念その他について、今のような背景がありますから、常に同じ内閣の中にいるんですから、常に緊密に連絡を取って、国民の権利が阻害されないように、また良質な情報が伝達されるように私どもも心を配っていきたいと思っております。 鈴木寛君ありがとうございます。正にそういうスタンスで、これ大事な問題ですから、議論をしていかなきゃいけない。 で、やっぱりここを、今日このことを是非質問させていただかなければいけないなと思ったのは、やっぱり通信と放送の在り方に関する懇談会報告というのが今、伊吹大臣のおっしゃったような配慮がやっぱり少し欠けていたというか、丁寧さがですよ、という、これはまあ前内閣のときに前大臣同士の中での議論でありますので。是非、今おっしゃったようなことで、改めて安倍内閣全体としてこの問題を議論する上でのこの重要性といいますか、どこに慎重な配慮と熟慮をもって臨まなければいけないのかというのは、これは是非御確認をいただきたいということでございます。 で、実はこれは、これ権利義務というのは別にだれの肩を持つものでもないんですね。いたずらな放送概念の拡大というのは、実は放送事業者の首をも絞めかねないというお話を少しさせていただきたいと思いますが。 今、WTOという条約があります、枠組みの中で、要するに、基本的に物の取引というのは自由でなければいけないと、こういうことであります。しかしながら、昨今、サービス貿易というものが非常に規模が拡大をしておりまして、サービス貿易については様々な留保がなされております。とりわけ、放送とかあるいはオーディオビジュアルといった、国民の、まあ何といいますか、文化的生活あるいはいろいろな生活様式に対して影響力の強い放送とか映画とかあるいはそうしたデジタルコンテンツというものについては、相当、各国ともいわゆるWTOの一般ルールの適用を留保しているといいますか、まだそれはちょっと早いですよというスタンスを取って、で、WTOの加盟国であっても、その放送とかデジタルコンテンツとか映画については独自の国内法制でもってある種の規制を行われているのは、これは事実、現実でございます。特にヨーロッパなどはハリウッドの映画ががんがん入ってきてもらったら困るとかいう、いろんな理由とかございます。これは、例えば中国とかアジアの国においても同様のことがあるわけであります。 じゃ、翻って我が国はどうなっているかといいますと、我が国も放送についてはWTO一般ルールの適用を留保しているわけであります。で、今これはビジネスチャンスだけではなくて、日本とアジアが一体になっていこう、仲良くなっていこうという中で、政府も推進をされていらっしゃると思いますが、日本初のデジタルコンテンツを広くアジアの方々に楽しんでいただこう、あるいは日本初の情報をアジアの方々にお届けをするということは、これは知財本部中心に一生懸命推進されているわけで、これは非常に望ましいことだと思います。 そういう大号令の下に、様々ないい情報を作りそれを発信しようという志のある方々が、対アジア向けのサービスを企画したり、あるいは一生懸命既に開始されようと準備をされたりしていらっしゃいますが、これ、放送概念というものがどんどんどんどん日本がそうした放送に関する規制とかというものを広げていきますと、結局アジアの諸国が日本初の様々な情報発信を中国とかASEAN、アジアの国々が受けるところで規制をするということに対して、ある意味での口実と言ったらおかしいですけれども、これはまあ大臣も御承知のとおり、これはレシプロカルですから、基本的には。 そうすると、日本だってやっているんだからということで、もちろんそれだけがそのすべてを決めるというわけではありませんが、今、全体としては日本発のコンテンツをアジアに広めようということに、その少しでも障害は取り除いていくというのが、これは日本のデジタルコンテンツを発信するという政策でありますから、それの例えば障害になる可能性というものもこれあるという懸念を私は思っております。 現に、そういうことを心配をしておられる放送事業、一見便益を受けるであろう放送事業者あるいは放送事業者にいろいろなコンテンツを提供されているクリエーターの方々からもいただいておりますので、是非総務省には、やっぱりこういうこともきちっと見据えて、だからやっぱり権利義務を確定するというのは、本当にいろんなところに思いをめぐらして制度設計していかなきゃいけないんで御配慮をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 政府参考人(中田睦君)御指摘ございましたように、日本発のデジタルコンテンツを世界に流通をさせていく、日本のデジタルコンテンツの作成能力、流通能力を高めていくという非常に重要な課題であると、私どももそういうふうに認識をしております。 そういう中で、いろんな御指摘、今いろんな点の、論点の御指摘がございましたけれども、私どもとしては、そういうことも含めまして、その制度の在り方そのものは常に社会の動きを踏まえまして検討していくことは必要だろうというふうに考えております。 先ほど御指摘がありましたように、通信・放送の在り方に関する懇談会の議論、引用されましたけれども、その後、政府与党合意ということで、通信・放送法体系の抜本的な見直しということも検討していこうと。それは、ある意味、従来型の放送というものと従来型の通信というのは非常に分かりやすかったと、それがだんだん技術の進歩に伴って類似のような形態も出てきたと。 そういう中で、通信と放送に分けている現在の法体系の中で新しいサービスを適用していく、出てくることに支障がないかどうかとか、あるいは、消費者、新しい時代における消費者なりユーザーの保護という点に欠ける点がないかどうかと、いろんな点を議論をして、国際的にも同じような議論を進められておりますので、そういうところも含めまして全体的な検討を常に行ってまいりたいと、そのように考えております。 鈴木寛君是非それはやっていただきたいと思うんです。 なぜここまで私が申し上げるかというと、きちっと国際的な条約のフレームワークの中で放送の定義がありますと。しかし、例えば電気通信役務利用放送法における放送は、そうした国際的な理解である同時一斉、同報通信、同報の配信ということの要件抜けているんですよね。「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であって、」ということですから、これ相当放送を超えているんですよ。 これは、総務委員会で平成十三年とか十六年のときに御議論されたので、私はそのときも文教科学委員会におりましたのであれだったんですが、これ国会もある意味でちょっと見落として、これは私も含む国会議員の責任だと思いますけれども、国際的な放送の理解よりもかなり踏み込んだ放送定義になった法律になっていると。 だからこそ、今回、この電気通信役務放送は、これはある意味では内閣法制局参事官の見識だと思いますが、ここで放送と書いてあるけれども、これは国際理解で言う放送じゃないよということで、著作権法の方にここの放送定義を引っ張ってくるのには余りにも無理があると、こういうことがあって、冒頭私がいろいろ限界事例、やっぱり白黒きちっとしておかなきゃいけないんでややくせ玉を投げさせていただきましたけれども、結局こういうことになっているんだと。 その元凶は、やはりこの電気通信役務放送のときの定義の仕方が甘かったというか、少し放送概念をやっぱり逸脱していた。そのことが引き続き通信と放送の在り方懇などの基調にあることに私は懸念を持っております。 やはり、もう一回きちっとこうした議論を総括をして、放送概念を広げること、これは放送事業者にとってもいいことと悪いこととあるわけで、もちろん著作権者あるいは著作隣接権者にとってもその放送概念を余りにも広げ過ぎるということは、いわゆる創意工夫を発揮して、そしていい著作物を作ろうというインセンティブを、これディスインセンティブになっているわけですから、そしてその放送概念を広げるということは、いいコンテンツがあったときにそれをより多くの人たちに普及しよう、何がいいコンテンツか悪いコンテンツかはこれ議論が難しいところでありますが、いずれにしても、そこに情報流通の規制を放送になれば一定程度掛けられる可能性というのはこれ出てくるという議論を、総務省はきちっともう一回私はやり直していただいた方がいいんじゃないかなと思うわけなんですが、いかがでしょうか。 政府参考人(中田睦君)御指摘のとおりだと思います。 従来から比べまして、技術の進歩によりまして、放送と言っていたものの種類も非常に増えております。電波の地上放送だけではなくて衛星放送もございますし、衛星の移動体向け放送といったものも出ておりますし、最近ではワンセグ放送といったものも出ております。他方、通信の分野と言われるところも、電信や電話といったものから、メールでございますとか、最近ではいろんなブロードバンドに乗ります映像の配信等、いろんな形が出てきている。そういうふうにサービスがいろいろたくさん出てくるという中で、従来からの法体系、規律の在り方といったものを総合的に検討していくということが非常に大事なことということで、現在、中央大学の堀部先生を座長とお願いしておりまして、通信・放送の総合的な法体系に関する研究会というものを開催をしておりまして、これは政府・与党合意に基づいて具体的な作業でございますけれども、今年の夏に発足をいたしまして、来年一年、来年の年末までに検討結果をまとめていただきたいということでお願いをしているところでございます。 鈴木寛君今、私の指摘をそのとおりだとお認めいただいたことに非常に敬意を表したいと思います。 先ほども申し上げましたけれども、本来、表現の自由というのは何の条件もなく認められる憲法上の極めて重要な権利でありますが、現実問題、放送法においては一定程度の、もちろんこれは相当な高いハードルの中で、その公益性、社会性の中で現行放送法については認められ、その運用が時々問題になっております。 私どもは、これは私どもだけじゃなくて、やはり民主主義の原点がこの表現の自由、報道の自由でありますので、そこと本当に密接不可分な関係を持つ放送概念のこの定義といいますか、概念の拡大問題ということは極めて重要な課題だというふうに思っておりますので、その点も十分に留意されて総務省における御検討をしていただきたいということを重ねてお願いを申し上げておきます。 最後に大臣、これ、もちろん総務省が放送概念の拡大についてもう一回きちっと議論し直すと、こういうお話がございましたが、これは内閣全体として、あるいは国会全体として放送概念を広げる、あるいはどういうふうに深めていくのかと、これを再定義し直していくのかということはもうこれ民主主義の根幹にも直結する話でありますし、それから、本当に優良なコンテンツを創意工夫をもってどんどん作っていただいて、そしてそれをどんどん世の中に普及されて、そしてそれが再活用されてという、正に文化立国といいますか、知的立国といいますか、それの根幹の活動を促進するのか、そこに一定程度の歯止めを抑制的に働くのかということにもつながるという、いろんな意味で極めて重要なこの放送概念の取扱いの問題、非常にこの分野にも御見識のあられる伊吹大臣に内閣全体のリードをお願いをしたいと思いますが、その点いかがでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)やはり、権利の制限とそれから権利の行使というのは、二律背反であっては、公益を目的とする限りはいけないんだと思います。ですから、今先生がおっしゃったように、私たちの立場からすると、著作権あるいは著作隣接権を守ってあげるということの方が強く出がちですが、同時に良質なものについてしっかりとした通信の、そうした放送の特にグレーゾーンのようなところを、私たちも積極的に議論に参加をしながら、その中で権利をどうするかということは常に問題意識を持って対処させていただきたいと思います。 鈴木寛君くれぐれもよろしくお願いを申し上げたいと思いますし、もっと国会を含めてこの問題の重要性というものを、今日議論を皆さんと一緒にさせていただきました、これをきっかけに、メディアの方々も含めて意識をしていただき、そして国会のみならず全国津々浦々でこの問題がいろんな多角的な観点から議論が沸き起こっていくことを期待をいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。 |