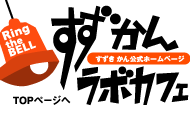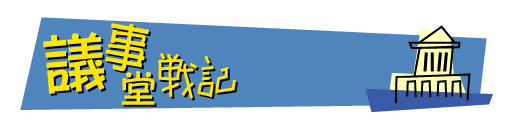2006年12月14日 教育基本法に関する特別委員会鴻池祥肇君ありがとうございました。 先ほど申し上げましたように、私はやっぱり子供は大人の判断でたたき込まなきゃいかぬときはたたき込まなきゃいかぬという、これをやっぱり世の親、大人が考えなきゃいかぬというふうに思います。教育というのはどういうものだろうかといろいろおっしゃいますよ、みんな。しかし、未熟な子供を立派な大人にするためのことが教育だと思うんですよね。それが何か、すべて子供を楽しますために、嫌なことはさせないために教育、これは私は間違いであると思います。 そこで、せっかく座っておられますから、ちょっと民主党の鈴木寛先生に、第十七条ですね、教育振興基本計画。これが民主党案では、比較的、まあよその党のを褒めたらいけませんけれども、これがこのまま独り歩きして、またぞろ官僚の手のうちに入って教育がどうなっていくかというのは、僕は心配なんです、政治家として。これについて、鈴木寛先生、どのように考えられますか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私ども民主党が提出をいたしました日本国教育基本法案でも、第十九条で教育の振興に関する計画というのは盛り込んでございます。 ただ、今委員も御指摘のとおり、今まで私も五年半、文教科学委員会におりますけれども、学習指導要領とか定数改善計画とか極めて重要なことが文部省の告示、あるいは文部科学省と財務省との間だけで決まってしまうと、これは非常に遺憾なことだと私は思っております。 したがいまして、今回は、教育基本振興計画の主語を私どもの案では「政府は、」といたしまして、そして国会の承認を得て、それでしかも国民の皆さんに公表しなければいけないと、こういうふうに盛り込んでおります。正に国会の場で、子供たちに何を教え、どういう体制で臨むかと、こういうことを多くの国民の皆さんの代弁者である我々がきちっと議論をしていかなければならないというふうに考えておるところでございます。 中略 内閣総理大臣(安倍晋三君)労働分配率の問題につきましては、今後、経営者側も現在のこの経済の状況にだんだん自信を深めていくことによって労使間でのお話合いが進んでいくのではないかと、このように期待をしているわけでございます。 そしてまた、先ほど申し上げましたように、教育のそれが現場に及ばないようにしていくためには、やはり先ほど申し上げましたように奨学金をしっかりとこれは充実をさせていく必要もあるでしょうし、私学の振興も必要なんだろうと、このように思います。 また、いわゆるフリーターと言われている方々がなかなか正規の仕事に就けないという状況にあって、私どもの政府としては二十五万人の常用雇用化プランを進めてまいりたいと、こんなようにも考えておりますが、また、先ほど申し上げましたように、何度でもチャンスのある、機会のある社会をつくっていくことによって、またその中で職業訓練を受けたり、また学び直しをして、自らの意欲において新しい段階にステップアップしていくことができる社会をつくっていくことが私は重要ではないかと思います。 櫻井充君それは、お金があればできるということになっていくんじゃないかなと。これは小泉内閣メールマガジン、少子化アンケート、平成十七年の七月に行ったものですが、少子化に歯止めを掛けるのに必要な政策の中の実に七〇%が子育て支援、子育て世帯に対して経済的支援を充実すると。先ほどお示しした四百万円以下の世帯ですと、子供さん、学校に通っている子供さんがいらっしゃった場合、何と所得の半分が教育費なんですよ。ですから、それだけの負担を強いられれば、最終的にはなかなか難しくて、結局は学校に行けなくなるような子供たちも出てくるんだろうと思います。 その点について、民主党の方として何か対策があれば御答弁いただきたいと思います。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私どもも、日本国教育基本法案を提出する際に、何をしなければいけないのかあるいは我々は何をしたいのかということは、正にこの格差社会においてきちっと機会の平等を保障していく社会を絶対に実現するんだと、こういう思いでございます。 私どもが提出をいたしました六条におきましては就学前教育の漸進的無償化、そして第八条におきましては高等教育についての無償教育の漸進的導入と奨学制度の充実、こういったことを盛り込んでおります。 これは、正に我が国は教育費、GDPに占める公財政支出でございますけれども、OECD加盟三十か国中最低でございます。正に、高等教育だけで申し上げましても〇・五%、全体で申し上げても三・五%。せめても、アメリカが高等教育一・二、それから全体で申し上げると五・四でございますから、ここのレベルには速やかに教育基本法でこうした方針を打ち立てることによって実現をしていきたい。正にコンクリートから人づくりへの第一歩として日本国教育基本法案を提出をさせていただいているということでございます。 櫻井充君まさしく、教育にお金を掛けないと変わっていかないんじゃないかと。小泉総理は米百俵とおっしゃっていたんですね、どこに消えたのかよく分かりません、もうなくなってしまったのか。 やはり、まずきちんとした形で教育費を増やしていくべきだと思いますし、それからもう一つは、先ほど総理は格差を是正するような政策を打ち出しているというようなお話をされていましたが、これは平成十三年から十八年にかけて、これ小泉政権時代ではありますが、サラリーマンの所得別に見たときの負担増です。そうすると、四百万、六百万世帯では負担割合は何と一六%なんですが、三千万円ぐらいの世帯だと七・五%しか増えていないんですね。つまり、つまり、格差を是正する是正すると言いながら、税負担、社会保障負担はむしろ所得の低い人たちの方に重くなっているというのが実態なんですよ。障害者自立支援法にしたって、なぜあの障害者の方々に対して一割負担を強いなきゃいけないんでしょうか。そして、株式の配当は、結局は財界から押し切られて優遇税制をそのまま継続するような形になりました。 つまり、格差を是正する是正するといいようなことを言っているけれども、実際にやっていることは全く逆なんじゃないでしょうか。格差を是正するよりも何よりも、むしろ今やっていることは、大企業を優遇するとか、それから所得の多い人たちを優遇するだけの政策ではありませんか。違いますか。いや、大臣ですよ。 国務大臣(伊吹文明君)いやいや、ちょっと。委員長が御指名をされておりますので答弁させていただきます。今日はテレビが入っておりますから、誤解を受けるといけませんので。 確かに、先ほど、民主党の提案者、そして質問しておられる先生御自身も、教育にお金を掛ける、私も今、予算編成のために教育にできるだけ予算を集中していただくべく最大限の努力をしているところです。その結果は補正予算にいずれ現れてくると思います。しかし、テレビの前でそれだけお金を掛けるべきだということであれば、民主党が今議論しておられる新しい政策の中で消費税を上げないと言っておられるわけでしょう。どこを減らしてその財源を持ってきて、どこの税を上げてその財源をはっきりと確保されるかを……(発言する者あり) 委員長(中曽根弘文君)御静粛に願います。 国務大臣(伊吹文明君)国民におっしゃらなければ、それは政策論争にならないんじゃないんですか。(発言する者あり) 委員長(中曽根弘文君)質疑者以外は静かにしてください。 内閣総理大臣(安倍晋三君)今、櫻井委員は格差、格差と、このようにおっしゃっていますが、しかし、この五年半、我々は改革を行うことによって、いわゆる失われた十年から力強いこれは成長軌道に乗ることができたんです。やはり経済が成長していくことによってこれは税の自然増収も出てきたわけであって、今このグローバル化した世界の中で、日本は競争に勝ち抜いていかなければ成長もしないし、そしてその成長の果実をみんなで分けることもできないということであります。 そういう政策の中にあって、しかし、いかに格差を感じないそういう社会をつくっていくかということが難しいわけでありますが、しかし大切なことは、何回も申し上げておりますが、だれにでも何回でもチャンスのある社会をつくっていって、しかしそれは決してお金持ちしかできないということではないわけであって、一回失敗した人も、あるいはまた、努力をしてもう一度勉強しようという人たちに対していろんな支援ができないだろうかということを今我々は総合的な再チャレンジ支援策として取りまとめをしているところであります。 櫻井充君それでは、民主党の、どうやってその予算配分するのか、概要だけちょっと教えていただけますか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 先ほどコンクリートから人づくりへということを申し上げましたが、我が国の公共事業支出対GDPはほかの国に比べて二%ぐらい高うございます。これを削ることによって教育でありますとか医療でありますとか人づくりに回していけば、必ずしも増税する必要はないという、こういうふうなことを提案をさせていただいております。 更に申し上げますと、今年の通常国会におきまして我々民主党は、民主党としてきちっと予算の対案を出させていただいております。総額においても、文教科学予算総額においても政府案よりも八千億高い予算を計上して、なおかつ、全体像として国債の発行高を四千億削減をするという案をきちっと国会にお出しをさせていただいているということも併せて御説明を申し上げたいと思います。 中略 櫻井充君それでは、その構造改革という手段を用いて本当にこの国そのもの自体が変わってきているのかどうか。それからもう一つは、その構造改革そのもの自体が日本の意思で行われているのかどうかということが私は極めて大きな問題だと思っています。 例えば、これは一九九六年の十一月十五日に日本政府とアメリカ政府と、行革、競争政策に関しての要望書でございますが、そこの中で、雇用政策として、アメリカからの要望書として、できれば、日本の場合には、労働者は、労働者の移動を妨げるある種の特徴を持っているから、それを変えてくれという要望書が来ているわけですね。結果的に、それに沿って平成四年の三月から、改正労働者派遣法が施行されてから労働者の分配率も下がっていますし、それからもう一つは、非正規雇用の人たちがどんどんどんどん増えてきていると。 つまり、構造改革のときに僕は竹中大臣や小泉総理と随分やりましたが、結果的には、その対日要望書というものがございます、その対日要望書そのもので要望されている社会にどんどんどんどん変わってきているんですよ。ですから、そういう点でいうと、この国の構造改革がもし手段であるとすれば、だれのためにそういう形で変えていっているんでしょうか。 先ほどの労働者の分配率のところをもう一つ申し上げておきますが、日本の最大の企業の今最大の株主はもう外国人になっています。外国人の株主が二六%もいます。つまり、その人たちを優遇して、そして日本人の労働者の賃金を低く抑えて、結局は日本人が一生懸命働いた対価はほかの国に流れていっているというのが現状ですよね。 だれのための改革なんでしょうか。対日要望書についてどうお考えですか、総理は。 内閣総理大臣(安倍晋三君)ただいま委員が指摘をされました対日要望書というのは、日米規制改革及び競争政策イニシアティブのことであろうと、このように思います。 日本は正に資源のない中で貿易によって立国をしていると言ってもいいんだろうと、このように思います。日本が輸出をして、あるいは輸入する中において富を得て、日本を豊かにしているわけであります。自由な貿易によって日本は大きな利益を得ている。日米間における貿易の量が増えていくことは当然日本の利益にもなりますし、海外から大きな投資があることは、その投資によって当然雇用も生まれますし、日本の活力にもつながっていくんだろうと思います。 そういう中で、スムーズにこの日米の経済関係が発展するようにするためにはどんな障害があるかということをお互いがお互いの国に対して意見をこれは述べるというのがこの日米規制改革及び競争政策イニシアティブであって、これは、米側も日本に対して要求を出しますが、日本側も米側に対して要求を出しているわけであります。また、例えば米国は、それはヨーロッパとの間で行っておりますし、日本はヨーロッパとの間でも行っている。それぞれの地域同士がそういうことを行いながら、ある意味では紛争の起こる前に事前に調整をしていると言ってもいいのではないだろうかと。 そういう意見を我々がすべて聞くわけではありませんし、当然自主的に判断をしていくということは申し上げておきたいと、このように思います。 また、先ほど海外からの投資がまるで間違っているかのようなお話がございましたが、それは決してそんなことはないわけでありまして、むしろ私は、海外からの投資をもっと増やしていきたいと、こう考えています。 櫻井充君海外からの投資は、いい投資と悪い投資があると私は思っています。 つまり、企業が成長するために持続的に投資してくれる、そういう投資は、本当にこれはウエルカムですよ。ところが、今はそうじゃないんですね。そこの企業のところをMアンドA、乗っ取るとは言いませんが、ある種そこの企業のところからキャピタルゲインを得るとか、それから、資産が多いからその資産を売却してそこで利益をすぐ出せとか、そういう形で、ただ単純に利益を搾取するような形になっていっているのは、私は、これは投資と呼ばないんだろうと思っています。 ですから、その中で、長期間の投資なのか、それとも短期の利益を目的としたお金なのか。今のお金の動き方を見ると、短期の利益を目的とした、投資と言うべきものではなくて、むしろ投機と呼ぶべきようなものが多くなっているというところに私は問題があるんだろうというふうに思います。 済みません、時間に、もうすぐ時間なので、ちょっと最後に、別な観点から民主党の発議者に質問させていただきたいと思いますが、うちの死んだおやじが生前言っていたのが、おけがあって、そこに水をためて、その水を自分のところに寄せるとどうなるかというと、おけのへりを伝わって向こう側に行くんだと、むしろ、おけの水は向こう側に押した方が最後は自分の方に戻ってくる。つまり、要するに、人のためにやれば最後は自分のためになるんだからというようなことを言っていて、まあ立派なおやじだなと思っていたら、どうもお釈迦さんの教えだったようなんですね。 それから、医者としてホスピスなどのかかわりを持ってまいりましたが、日本と外国とのホスピスの違いというのは一体何かというと、宗教観、宗教家がいるかいないかということで全然違ってきています。 そういう点からすると、日本で宗教教育というのは一体どういうふうにしていくべきなのか、その点について民主党の発議者から御答弁いただきたいと思います。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 民主党提出の日本国教育基本法案の第十六条におきましては、「生命及び宗教に関する教育」という条項を新たに盛り込んでおるところでございます。恐らくこれが政府案との最大の違いの一つだというふうに思っておりますが、私どもは、これまでの公立学校におきますいわゆる宗教に対して過度に慎重になり過ぎていたというふうに認識をしております。これだけ命をめぐる大変深刻な事件が続発をしている中で、やはり子供たちに、この十六条の一項で書いておりますが、生きる意義と死の意味というものをきちっと考察をしていただき、命あるすべてのものに対する尊ぶ態度、これを養っていきたいということを盛り込んでございます。 さらに、サムシンググレートといいますか、大いなるものに対する畏敬の念でありますとか、自然を大切にする心とか、あるいはすべての生きとし生けるものを慈しむ心とか、こうしたものを宗教的感性と私どもは定義をいたしまして、これを涵養していくことに教育現場は何らためらうことなく前向きに取り組んでいただきたい、そのための規定をきちっと盛り込まさせていただいているところでございます。 これは、イギリス等々におきましても、ブレア政権があらゆる世界の主な宗教をきちっとその基本的知識については教えるように、こうしたことも参考にさせていただきながら、この「生命及び宗教に関する教育」の重視をする方向へ、この六十年のきっかけに大きくかじを切っていきたいと、こういう思いを込めてこの条項を盛り込まさせていただいております。 櫻井充君ありがとうございました。 時間になりました。 その教育基本法その中に、僕は個人的に申し上げると、やはり目標などを掲げる、国がこういった形の人を育てなきゃいけないという、法律上に、理念法なのにこういう目標を掲げてここまで行かなきゃいけないような定める内容という法律は、私は決して認められるものではないと。 そしてもう一つは、様々な観点でまだまだ議論を尽くすべきところは一杯ありますから、十分な審議をしていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 |