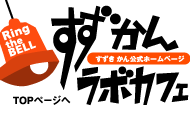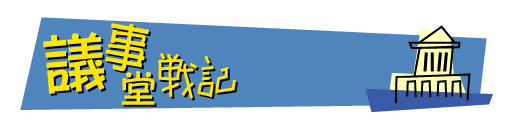2006年12月12日 教育基本法に関する特別委員会公聴会鈴木寛君民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。公述人の皆様方、貴重な御意見を本当にありがとうございました。 私どもも、民主党といたしまして日本国教育基本法案という法案を今回出させていただいております。今日、大勢の公述人からお話がございましたように、今回なぜ六十年ぶりに教育基本法を作り直すのかと。私どもも作り直したいと思っているわけでございますが、その大きな理由の一つに、この戦後五十年のこの教育行政の在り方ということをやっぱり変えていく大きな契機にしていきたいということ。それから、残念ながら、先進国の中で非常に低水準にあるこの我が国の公教育、公財政、教育に対する公財政支出、これを、ああ、あのとき教育基本法を作り直して、あそこからこのV字反転回復をして教育予算が増えていった、そのことによって真の教育立国日本がつくる、そのきっかけになったなと、こういうことを目指して我々もこの考え方を法案という形にさせていただいたわけでございます。 そうした意味で、今日は多くの公述人からやはり教育投資、二十一世紀に最も重要であるというお話をいただきましたことを大変心強く思わせていただきました。 安西公述人にお伺いをしたいと思いますが、私どもも安西公述人から御指摘がございました、やはり教育振興基本計画、教育振興計画を政府案でも私どもの案でも作るということになっておりますが、とりわけ私どもの案の第十九条では、正にGDPに占める比率というものを一つの指標として、まあこれを国民の皆様方に、今こういうことになっていますよと。そして、もちろん税金は、その使い道は最終的には国民の皆様方のこの世論によって決めていくわけでありますが、その材料として、あるいは議論の指標としてこうしたものを御提示をするということが、その教育立国のために、貴重な税金を使っていくということに資するのではないかということで、先生の御提案も入れさせていただいているところでございます。 実は、先生も御承知のように、ちょうど六年前ほど、私は慶應義塾大学で教鞭を執らさせていただいておりまして、大変に有意義な日々を送っておりました。したがいまして、この永田町にお誘いを受けまして、まあ正直迷ったというか、残りたかったとかですね、まあ正直なことを申し上げると、永田町に来るのはどうもなと逡巡をしていたのが正直なところでございます。 しかしながら、この最後、私が永田町に挑戦をする決意を固めたのは、田中耕太郎先生が教育基本法の立案に貢献をされたことは大変有名でございますが、実は慶應義塾の理財部長をされておられました高橋誠一郎先生が教育基本法を審議をしたときの文部科学大臣であり、五月三日公布をされたときの文部科学大臣も高橋誠一郎先生でありまして、慶應義塾で正に一番責任あるこの学部長をお務めになった先生が、そこでの御経験、そこでのこのお知恵というものを踏まえて、正に教育行政の最高責任者として戦後日本の教育の礎をおつくりになったということ。まあ、私はもちろん高橋誠一郎先生には足下にも及びませんけれども、やはりそうした思いで日本の教育を立て直そうと現場で頑張っておられる先輩、同僚の皆様方の代弁者なっていくということも生きる道かなと思ってまいったわけであります。 一貫いたしまして、私は正にそのコンクリートから人づくりへこの税金を使っていくんだと。とりわけ、今日、安西公述人もお話がございましたように、今格差社会といったことも言われております。ここで今、日本が一番必要なのは、正に福沢先生の教えをもう一回思い起こすことでありまして、人は生まれながらにして一生は決まっていないというお話がございました。正に、学問によってすべての人々に人生の可能性が開けていくんだということで、福沢先生が「学問のすすめ」を著されたと思いますし、実は民主党の日本国教育基本法案の解説書も「教育のススメ」とさせていただきましたのは、そうした福沢先生の精神に少しでもあやかりたいと、こういう思いでもございます。 そこで、お尋ねをいたしたいのは、私はこれ国会にいる限り、奨学金の問題というのはライフワークにして頑張ってまいりたいというふうに思っております。 残念ながら、我が国の奨学金というのは諸外国に比べますとまだまだ十分とは言えない。とりわけ、奨学金というのは給付と貸与とこれ両方あるわけでございますが、給付といった奨学金制度については極めて貧弱な状況にございます。その結果、我が国の高等教育に占める家計比率は、これは先進諸国中最高水準の六割ということでございまして、アメリカなどと比べましても、アメリカは三割程度でございますので、はるかに高い。このことが、正に学ぶ、学問をする機会の平等ということが損なわれているという極めて本質的かつ根源的な問題だというふうに思っておりますし、この知的社会に向けてこの点を克服しなければ正に後世に申し訳が立たないと、こういうようなことを思っているところでございますが、この奨学金の充実等々について安西公述人の御意見をお聞かせを賜りたいと思います。 公述人(安西祐一郎君)今、特に福沢諭吉のことに言及していただきましたけれども、本当に今は教育のすすめ、また新学問のすすめの時代だということであります。そういう中で、奨学金の問題につきまして、やはり人にはそれぞれいろいろな能力があって、それを人生のあらゆるところでもって生み出していく、見付け出していくことができる。それは学校の先生もできれば国会議員も一生の中でいろいろにできる、そういうことを見付け出していってもらいたいと、人は。 ただし、そのためには、セーフティーネットといいましょうか、人それぞれその一生の中でいつでも勉強ができるためのサポートのシステムが絶対に必要であります。その大きな一つが奨学金であって、しかも給付の奨学金が非常に大事であります。この給付の奨学金の原資について、これがやはり先ほど申し上げた教育予算とのかかわりが出てくるんでありますけれども、日本は余りにも貧しい。このままでは、大学レベルになれば、それこそほかの国の大学で学んだ方がましだと、そういう人たちが出てくる、そういう状況にもあるかと思います。 その原資を講ずる手だてというのは基本計画の中できちっとやはりセットしていただきたいというふうに思いますけれども、今は本当に日本の学生が学びにくい。また、社会にいったん出て、また学校に戻りたい、一時的に戻りたいと思っても一時的に戻ると職がなくなる、一時的に戻ろうと思っても教育費を負担しなければならない、その教育費が例えば所得控除云々の免除にもならないと。そういう状況では、またもちろん育児あるいは障害を持った方々のそういった人生設計、そういうことのサポートをきちっとやっていただくことがやっぱり政治の一つの大きな役割だと思いますし、私どもの方でもそれに向けてもう万全の努力をしていかなければいけないと思っております。 鈴木寛君ありがとうございます。 これ、教育基本法を作り直す、これはもっともっといいものに私どもしていきたいと思っておりますが、当然学校教育法あるいは私立学校法といったことについても六十年ぶりに再点検をし、再構築をしていかなければいけないというふうに思っております。 私も、国立大学法人化のときに文教科学委員としてかかわったわけでありますが、お聞かせをいただきたいのは、私学と官学といいますか、これどういうふうに役割分担あるいは連携をしていったらいいのか。安西公述人おっしゃるように、日本の特に高等教育は明らかに私学に頼っているという現状がございます。そういう現状を踏まえて、私どもも九条の中で、建学の自由はこれは最大限保障されるということと、私立学校への助成及び私立に在籍する者への支援ということを明記をさせていただいているわけでございますが、これは本当にいろいろ悩ましいのは、例えば先ほど奨学金のお話がございましたが、ハーバード大学は四百万円以下の年収の御子弟が約一割ぐらいいらっしゃるそうでありまして、そういう方々に対してきちっとその大学、もちろん国家がそれをサポートしている、あるいは税制でサポートしているということでありますが、大学がきちっとそうした方々にも十二分な支援をすることによってそうしたことが可能になっております。 一方で、これはいろいろな調査がありますので俗説の部分もあるかもしれませんが、東京大学の御家庭が一番年収が高いということが言われております。事実は確認されておりませんが、そのような傾向は私もあろうかと思います。 それから、更に申し上げますと、現段階で申し上げますと、慶應義塾大学の文科系の大学院の学費と国立大学の大学院の文科系の学費は慶應義塾大学の方が安いという現状がございます。これは慶應義塾大学の経営努力と教育に対する大変前向きな姿勢の表れだというふうに思っておりますが。 国立と私立、じゃどうやって役割分担をしていったらいいのかということと、それから、私どもこれ憲法の議論にもかかわるわけでございますが、憲法八十九条がありまして、私学には公金を二分の一しか入れられないと。これは全然、まだ十分の一ぐらいしか入っておりませんから枠はまだあるわけでありますけれども、しかし、そういう制限の中で、私学助成金というものについての一定の制度的なキャップというものがあります。その中で私立大学に対して支援をしていこうということになると、学生に対して直接補助と、こういう合わせ技、そういう中でさっきの九条の設計になってくるわけでありますが、そうしたことが入り乱れて、国立大学は今度は国立大学法人になっていくという中で、この高等教育の主体の在り方について御示唆を賜れば有り難いなと思います。 公述人(安西祐一郎君)私立学校、特に私立大学とそれから国立大学法人の違いですね、これは国立大学が法人化されて以降、私の見解でははっきりしなくなっているというふうに思います。そのことが言わばタブーと言うといけませんけれども、議論されないままに来ているということが非常に大きな高等教育における今問題であると。国立大学の方はやはり国費からの投入分が相当にある、もちろん運営交付金が徐々に減少しているという面はありますけれども、私学の方も減少しつつある。そういう状況の中で、私学、それから公立の学校、それから国立大学法人の役割というのは一体何なのかということは全く議論がされないままに来ているということを是非先生方には申し上げておきたい。 恐らく、私はこれからの日本では、私学のような個性を持って歴史を持って教育研究に携わる、そういう教育研究機関が言わばベースになっていくのではないかというふうに思っております。これは日本が成熟した民主社会になってくるにつれてそういう方向に行くのではないかと思いますが、一方で、国立大学法人の役割も、これもやはり基礎的に重要であると思います。ですから、併存していくというふうには思っております。 それから、手短に申し上げますけれども、私学と国立の学費の違いでございますけれども、今、鈴木先生が慶應の方が安いのではないかと言われましたけれども、それは授業料を比べるのと、それからそれプラス入学金とかいろいろな周りの附帯経費を足して比べるのとでは違いまして、やはり慶應の方が高いのではないかと思われます。 また、理工系、医学系等々については、私学は国立と違ってその大学の中で違いがありまして、私の手元の資料では、特に理工系のたまたま資料があるんですけれども、学部においては、国立大学は標準で五十三万五千八百円、慶應義塾の場合は百三十三万円でございます。早稲田が百三十九万円、立命館が百三十三万六千円。大学院におきましても、国立は五十三万五千八百円、慶應義塾は百十七万円というのが理工系の数字でございます。文系はもっと私学も安いんでありますけれども。 ただ、私、国立大学が安い安いということを申し上げたいわけではない。国公私立を通じてやはり教育への支出が余りにも貧しい、それがいろいろな問題を生み出しているんだということは申し上げたい。 あと一つだけ。ハーバードにつきましては、二兆円以上の運用資産を持っていると言われておりまして、二兆円以上の運用資金をアメリカの利回りで回せば、恐らく年に一千億円程度の利息が入ってくると思われます。これは、そういうことを人件費、施設等々に使っていけば、それはうらやましいほど幾らでもいろんなことができるわけで、ハーバードがそれを積み上げてきましたのは、やはり寄附の文化、やっぱり民に根差した教育を民でもって草の根的に持ち上げていこうという、そういう文化があったからなんですね。日本も恐らくこれからは一つ一つ着実にそういった文化の方へ、寄附税制の改正もいろいろにやっていただきながら進めていくべきだろうというふうに思っております。 鈴木寛君私が申し上げたかったのは、国立大学と私立大学の差を広げていいということではないんだと思うんですね、恐らく。私立に通おうと国立に通おうと、同じように学習権はやっぱり保障すべきだという方向化の中で、しかし国立大学がどんどんどんどん、一方で国立大学というのは非常に経済的に奨学の必要な、就学機会保障の必要な若者に対する機会の提供という任務を負っているにもかかわらず、そこを負い切れてないんだということも一方では非常に難しい問題でありまして、これは私学経営の問題と、それから学ぶ権利の保障の問題というもので非常に難しい制度設計の中で、また是非御指導をいただきたいというふうに思っております。 それから、時間もなくなってまいりましたので、山岡参考人にお伺いをしたいと思いますが、山岡参考人は特別支援教育の理念や障害のある人に対する支援を政府案の教育基本法の中にやっぱりきちっと条項を立ててと、我が党案で言う十三条のようなことを想定されているんだと思いますが、御要望をされました。 何というんでしょうか、やはり北欧などにおけるこうした特別支援教育、あるいは障害教育における位置付けと、まだまだやっぱり我が国におけるそうしたノーマライゼーションのような、あるいはインクルーシブ教育についての国民的な理解、そういった理解を促進をしていく、あるいはそれを改善をしていくと、そういうことにやはり教育の最高法規である教育基本法の改正というのは非常に重要な啓発効果というものを想定しておっしゃったんだと思いますが、そうしたことについて御意見を賜ればというふうに思います。 公述人(山岡修君)先ほど申し上げましたけれども、我が国において特殊教育の対象というのは一・六%程度でございます。アメリカは約一一%ぐらいのお子さんがそちらの対象になっているんですね。またもう一つは、日本の文化の中で、単一民族でやや違うものを排斥したりというようなちょっとカルチャーがありますね。その中で障害を持つお子さん、あるいはちょっとクラスの中ではみ出てしまうお子さんに対して、周りのお子さんからいじめの対象になったり、差別があったりということが実際にございます。このLD、ADHDとか高機能自閉症というお子さんは一見してよく分かりにくい障害でございますが、そのお子さんがクラスの中にいてちょっとはみ出た行動をして、そのことによっていじめられたり、あるいは教員の方から叱責を受けたり、また実は御家族からも、お母さんとか保護者も気付いてないようなケースがあります。そうしたことによって自己有用感を失ったり、そしてそういったものが二次的な障害や不登校につながるケースがあります。 日本の中でちょっと違いがあることを認めるような文化あるいは考え方というのが教育を通して醸成され、クラスのみんなや周りの保護者の方、そして社会一般で見てあげられるというような社会になっていくためにも、この基本法にこの障害に関する文言が入るということは非常に価値があるというふうに思っています。 鈴木寛君どうもありがとうございました。 もう時間がありませんので、それでは終わりたいと思いますが、本当に公述人の皆様方、ありがとうございました。 |