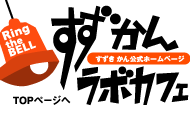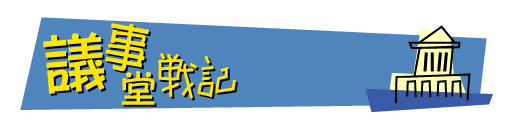2006年12月11日 教育基本法に関する特別委員会鈴木寛君三人の参考人の皆様方、本当に今日はありがとうございました。 私ども、以前より、やっぱり国会に教育基本問題調査会というのをつくって今日のようなお話を十分にいただく機会をつくりたいなということを主張してまいりましたし、これからもやはりその重要性を今日改めて痛感をいたしました。 今日は、本当にわずかに十五分ずつということでございまして、それぞれの参考人の皆様方に一時間でも二時間でもお話を聞きたいなと本当に率直に思いました。やっぱり、それだけそれぞれの県あるいはそれぞれの市で直接に子供の人生を預かっておられる最高責任者のお言葉、そしてそうした毎日、日々の中からわき上がってこられるお知恵、お考えというのは、我々もっともっと勉強させていただかなければいけないなということを感謝をもって聞かせていただきました。 加えまして、今回のお願いは先週の末という、極めて社会常識的に申し上げますと失礼なタイミングで、今日そういう中にかかわりませずお越しをいただきましたことを、おわびとそして御礼を申し上げたいというふうに思います。 それで、質問をさせていただきたいと思いますが、私ども民主党も今回、日本国教育基本法というものと、それから参議院におきましては教育行政と教育財政に関する改革案ということで新地方教育行政法と教育振興法という法律を併せて出させていただいております。 今回の教育基本法を作り直すという、六十年ぶりに作り直すというその意味は、特に、先ほど加戸参考人から御説明がございましたように、一九五六年以降の地方教育行政法の中で五十年間教育行政が行われてきておりまして、それがやっぱり少し、少しというかかなり時代に合わなくなっているというか、やはり総点検、再点検をこの実情に応じてする必要があるのではないかということで、正にそういう議論を深める場にこの国会の審議あるいは教育基本法の作り直しということを行っていかなければならないと、こういうふうに思っているわけでございます。 それで、お三人の方にお伺いをしたいと思いますが、我々の案は、一言で申し上げますと、ほとんど穂坂参考人のおっしゃった現状認識と御提案にかなり近い制度設計にさせていただいておりまして、それから私どもは品川区の若月教育長とは日ごろからいろいろお勉強をさせていただいて、御指導をいただいているところでもありまして、品川区のそうした実態という、この濱野参考人と穂坂参考人の御意見にかなり近い案になっているわけでございます。 それで、まず加戸参考人に御質問をさせていただきますが、もちろん、これは教育というのは制度だけではございません、一番重要なのはやっぱり現場におけるリーダーシップだというふうに思いますし、それから現場に一番近い基礎自治体における首長さんと教育長さんが力を合わせてリーダーシップを発揮されておられるところは品川区、志木市を始めすばらしい改革が行われておりますし、そういう地域は品川区、志木市を始め最近は各地にかなり出てきて、これは大変喜ばしいことだなというふうに思っております。 加戸参考人のおっしゃるように、運用でかなり、現行でもそこまで頑張っておられる首長さんあるいは教育長さんがいらっしゃるということでありますから、運用でできるというお話は私もよく分かってはおりますが、せっかくこれ五十年ぶりに地方教育行政制度も一から点検をし、そして議論をし直して、そしてこれから二十一世紀に向けてこういう教育のガバナンスで臨もうではないかという、非常に千載一遇のチャンスだと思うわけであります。そのことを穂坂参考人もおっしゃったと思いますし、私どもも余りにも動線が長過ぎるという現在の教育行政法の問題点ということは、恐らく加戸参考人も共有をされていらっしゃると思います。 その中で、私どもは是非、今国会、さらには次の国会で地方教育行政法についての抜本改正というのはこれは与野党を挙げてやっていきたいというふうに思っておりますが、加戸参考人には具体的には地教行法、どこをどういうふうに変えていったらいいのかということについてのお考えをお聞かせいただきたいと思いますし、濱野参考人から先ほど、やっぱり首長にももう少し権限をというお話がございました。では、具体的にどういう権限を更に、特にこの現場市区町村の首長にお与えをしていくという制度設計がよろしいのかということをお聞かせをいただきたいと思います。 それから、穂坂参考人におかれましては、ほとんど私どもが参考にさせていただいた御意見でございますので、そういう意味では、中身についてはもう全くそのとおりだというふうに私どもも思っているわけでありますが、この度、内閣府の方で、参考人が当時の鴻池大臣に御提案をされた教育委員会必置義務についての報告書へ盛り込むということになっていたのが見送りになっております。 こうしたことについて今どのような御意見、御感想を持っておられるか、それぞれお答えをいただきたいと思います。 参考人(加戸守行君)現在の教育委員会制度五十年たちまして、それぞれ制度疲労等の問題が大きいと思います。 ただ、現在の制度を改めるとした場合に、改めた場合のもちろんメリットがあるでしょうけど、私はデメリットも大きいと思い、そのメリット、デメリットの比較は慎重にすべきだと思います。 基本的な一つは、教育の政治的中立です。首長の選挙でいろんな公約を掲げて戦います。そして、当選したがために自分が選挙戦で戦った公約を教育の場で実現しようとするとがらりと変えなきゃいけません。逆に、四年たった後、また知事が交代した、市長が交代した、またがらりと変わる。教育は、そんな形、四年スパンで変えるべきものだとは私は思いません。そういった点で、変化というのは、いろいろな民意をくみ上げながら修正に修正、十年、二十年たってみたら変わっていたなという結果が教育の世界では正しいんではないかと、そういう点を思います。 それからもう一つは、実は人事権の問題をこれから市町村へ移行していくんであれば別ですけれども、人事権を首長が持つことは教職員に関して極めて危険なことだと思います。先生も御承知かと思いますが、戦前は、官選知事の下に土木部長、農林部長と並んで学務部長、それが人事をやっていました。役人が人事をやるんです。正に上の機嫌を取っていなければどこへ飛ばされるか分からない、そんな恐怖心の中で勤務する姿がいいとは思いません。それやはり合議制とは言いながら教育委員会、まあ別のシステムがあればいいんですけれども、それが公正公平な視点からの首長の圧力といいますか、そういった気持ちはまあまあ待ってくださいよ、この辺でとどめましょうよというようなブレーキ役、クッション役は私は絶対に必要だと思います。 参考人(濱野健君)何というんでしょうかね、法律条文上どうやって明示するのかということはちょっと私も法律に詳しいわけではありませんからあれですが、やはり先ほど申しましたように、次代の地域を担う人材をはぐくむという、そういうやっぱり首長の役割というのはあるんだと思います。したがって、教育委員会と連携してというような感じで、何らか首長が教育の問題について関与できるということを法律の中に示していただきたい。 先ほども加戸参考人がおっしゃったように、首長が直接教育行政を仕切るということはそれはあり得ないことでしょうし、また実際にそれは行き過ぎだというふうに思いますが、教育委員会に対して何らかの働き掛けができるということ、まあこれ実際には先ほど皆さんもお話しになっているように、実態的にはそれやっているわけですね。実態がそうならそれでいいじゃないかというと、やっぱりそういう問題でもないんだろうというふうに思っていまして、教育委員会との連携というようなことがどこかに盛り込まれないだろうかということを感じています。 教育は学校だけで行われているわけではないわけですね。先ほど申しました親の教育力を高めなければいけない、あるいは地域の学校に対するかかわりも強めていかなくちゃいけないというようなことでもって、総合的な観点から学校というところにかかわってくるはずですので、そういう点でも何らかの明示というものが必要ではないかというふうに思っています。 参考人(穂坂邦夫君)見送ったことに対する感想みたいなものなんですが、やっぱり一つの改革というのはメリットとデメリットと必ずあるんですよ。だけれども、デメリットが怖いから改革に踏み込まないという姿勢は私は良くないと思うんです。 それは、今の義務教育に問題がなければいいですよ。いじめの問題にしても、落ちこぼれの問題にしても、それから先生方がばたばた病気になっちゃうことも、いろんな意味でもう山積しているんですよね。ですから、それは事象面で検討すると同時に、私は、根本的な制度にメスを入れてそこもやっぱりしてみる、そこからどうするかを考えてみるという姿勢が私は必要だというふうに思います。 鈴木寛君ありがとうございます。 私どももやっぱり今の教育現場を見ていますと、特にいじめの問題とか不登校の問題とか、要するに想定をされないといいますか、要するに正常な状態から逸脱している状態というのが続発をしているということでありまして、結局それに対して、穂坂参考人もおっしゃいましたけど、マニュアルで幾らいじめマニュアルを作っても、あるいは不登校マニュアルを作ってもこれは難しいわけですよね。正にそれぞれのケース、ケースに応じてきちっとそのタイミングを逃さず、そしてケースに応じたきめ細やかな対応をリーダーシップを取ってやっぱり果断にやるということが私は今の教育行政の制度に最も欠けているんだろうと思います。 その中で、非常にリーダーシップと見識のある首長と教育長さんがいるところは、法律の枠の中ではありますけど、それを最大限に裁量権を発揮してやっておられるところはかなりうまくいっていますが、通常の場合は、この法律の枠の中で正にマニュアルに従っていればそれで責任が全うされているという、こういう悪循環が行われていて、ここをどういうふうに断ち切るかと、こういうことだと思います。 やはりその制度設計とそしてこの裁量と、こういうところのバランスだと思いますけれども、じゃ裁量というのは、正に教育長という方々が発揮できる裁量の範囲と、やはり民主的な選挙あるいは民主的なプロセスを経て市民あるいは子供本位の、学習者の代弁者である保護者、そうした方々からやっぱり信託をされて、そして子供たちのために、あるいはその地域のためにより良いことをやるためにどういうあんばいにしていくかというところが非常に私は重要だというふうに思っておりますけれども。 その一方で、加戸参考人がおっしゃる政治的中立の問題というのはこれ出てきて、我々もここを正に悩んでいるわけであります。穂坂参考人にお伺いをしたいのでありますが、もちろん政治的中立、我々重要だと思っています。したがって、教育委員会を教育監査委員会ということに改組して、そして教育監査委員会によって政治的公正性とか中立性というのは確保しようということを思っています。しかし、一定程度やっぱり首長に、これも濱野参考人も基本的に同じ方向だと思いますけれども、やっぱりある程度の権限を付与して、緊急事態に対しては、あるいは緊急事態を予防するためにはやはり迅速に相当な権限を持って対応できるということが我々は必要だというふうに思っております。 ここを、一方で、実態としてはもうかなり影響を被っているではないかと、影響力を行使しているではないかと。行使しているところがいいリーダーシップでもあるわけで、ここが悩ましいところなんですが。穂坂参考人に、この政治的中立性の問題と、それから脱マニュアルで現場本位、子供本位の教育行政をこれ実現するためにどうしていったらいいのかというよくある政治的中立論に対するお考えをお聞かせをいただきたいと思います。 参考人(穂坂邦夫君)私も政治的中立性は絶対守るべきだと思っているんです。 ただ、その政治的中立を守る手段が今の合議制で、しかもあやふやで責任者がいなくて、何かぬるま湯みたいで、それで本当に守れるのかということ、それがいいのかということなんです。ですから、ある意味では私は首長が学校の先生の人事にまで口出すようなシステムはいけないと思うんです。ですから、それは、ただ予算を握っていますから、全体的な総括的な責任というのはあってしかるべきだと思うんですね。ですから、それは制度の中で私はきちんとするべきだと思うんです。 例えば、今度の改正法がいろいろ言われておりますが、教育の中立性というのはもう本当に法律できちんと明示しているわけですよね。ですから、こういうことはやっぱりしっかりしておかないといけない。その中で、さて現場の政治的中立を守るのにどうかというのは私は制度の中で十分できる。例えばさっき言った、どういうやり方でもいいんですが、例えば教育委員会制度の中に教育長がもし合議制でなくて責任者になれば、現場の、教育行政のですよ、そうすれば牽制機能やチェック機能をきちっと持たせればいいと思うんです。あるいはまた、首長もそういう専横だとか横暴さがあれば、その辺をきちっとチェックをするのが必要です。あるいはまた国が、私はそういう関与、政治的中立を、現場の政治的中立を守る国の責任だってあってしかるべきだと思うんです。それはそれぞれがそれぞれの役割の中でしっかり担保する制度を私は補完作用として作るべきだと、こう思っています。 鈴木寛君濱野参考人にお伺いをしたいと思いますが、穂坂参考人もお時間があればお聞かせいただきたいんですが。 かなりリーダーシップを持って品川区も志木市もやられました。しかし、それに相当やっぱり障害がおありになったというお話をお二方からいただいたわけでありますが、具体的にどういうところでどういうふうに引っ掛かっていって、それが取り除かられたならば、品川とか志木は極めて強力なリーダーシップを発揮される首長さんがいたんでその障害を乗り越えられたと思いますが、そのバーが下がれば、より多くの市区町村で教育改革が生まれてくるだろう。我々はそういうことを期待して制度設計をもう一回作り直そうと思っているわけでありますが、例えば、こういうところがやっぱり非常に困るんだと、ここを何とか変えてほしいんだというところで、事例に即して御紹介いただければと思います。 参考人(濱野健君)品川区が教育改革を進めていく中で、いわゆる隘路というか障害になったということは、例えば小中一貫校をする、学校選択制を取るということで、やはり地域住民に十分な説明が行き渡らなかったということもありますが、やはり戸惑いはあったのは事実だと思います。地域と学校との関係とか、あるいは小中一貫でうまくいくんだろうかとかという、そういう、何というんでしょうかね、漠たる不安みたいなもの、これはやっぱり丁寧に丁寧に説明をしていくことが必要だと思います。 私は小中一貫校の必要性というのは、やはり公教育が、私立にかなり進学が行っていく中で、公教育が果たす役割をきちっと行うために必要なことだということで、あらゆるところで、教育長ももちろんですけれども、私も丁寧に説明をしております。やはり区民に対してしっかり説明をするということが一番重要じゃないかと。 もう一つは、教員自身がやはりこの改革に対して前向きに取り組んでもらう必要がある。これはちょっと前にもお話出ましたけれども、やはりある程度スピードというものが必要だと思うんです。改革をしているということが実感できるのは、ある程度のスピードがあって、ああ、今改革の中にあるんだなということが体感できるような程度のスピードというのが必要ですので、余りゆっくりゆっくりというのも、それでは改革が進まないんだ、一定のスピードを持ちながら、しかし区民に対しては戸惑いが起きないような十分な説明をしていくということが必要だというふうに思っています。 参考人(穂坂邦夫君)私ども一番困ったのは、都道府県が同意すればいいということになっているんですが、都道府県は駄目だと言うんです、二十五人程度学級のときに。なぜかというと、機会均等が壊れると言うんです。機会均等が壊れているのは、例えば複数担任制だって壊れているんじゃないかと、山の中と都会とはやり方違ったっていいじゃないかと。駄目なんですよ。 ところが、結局、なぜ駄目かというのが怖いかというと、教育委員会はやっぱりさっき言った人事なんですよ。市長ね、こんなことして盾突いたら、もし悪い先生ばっかり集められたら志木市の教育どうするんですか、こう言うんですね。ですから、そこのところが、私は県会議長とか県議団の団長なんかもやっていましたから、そんなことあったら表向きから大げんかしようやと言って、やっと教育委員会の人たちは納得をしてくれたし、まあ、たまたま私の同期が教育長だったものですから、そういう運もあったんですね。 しかも、それでも志木だけいいとは言いませんね。埼玉県全域でやるということで許可をしたんですよ。なぜそんなことをする必要あるのか。秩父の山の中と、志木市は東京から三、四十分のところなんです、何でそれと一緒にしないといけないのか。今でも、やっぱりそこが県のぎりぎりの許可条件だったと。全県でやるという形を取って許可してくれた。やっぱりその辺の何か裏側でのおそれというのはやめた方がいいですね。余り健康的じゃないと思います。 鈴木寛君ありがとうございました。 穂坂市長のような強力でなく、そこまでスーパーマンでなくても、真っ当な教育改革がやっぱり行われるための教育行政制度の構築に向けて、これからも私どもも頑張ってまいりたいと思いますので、引き続き参考人の皆様方の御指導をお願いを申し上げたいということと、それからやっぱり、今日お見えいただいた三名以外にも本当にすばらしい実践をされておられる県、市区町村一杯おありになりますので、是非そういう方々の御意見も伺ってみたいなということを申し上げて、今日の御礼に代えたいと思います。 どうもありがとうございました。 |