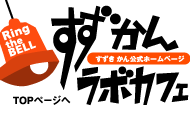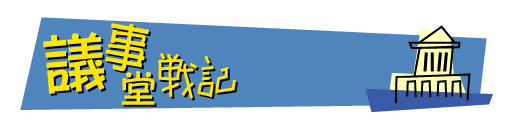2006年12月07日 教育基本法に関する特別委員会鈴木寛君四人の参考人の皆様方、本当に今日は貴重な御意見、大変ありがとうございました。 まず高倉参考人にお伺いをしたいと思いますが、民主党案におきましては、教育委員会を教育監査委員会ということに改組していくと、こういう案を提示をさせていただいているわけでありますが、私どももこの過程で、今日は四人の参考人、それぞれ非常にすばらしい的を射た御意見をいただいていまして、そのようなことを我々も十分参考にしながら党内で、そして党内外の方々からの御意見もいただきながら議論させていただいたんですね。 それで、高倉参考人には二つのことについてお伺いをしたいと思いますが、私どもも、やはり杉並区あるいは品川区、それから犬山市、この事例を、私は議員になる前から相当御一緒にやらせていただいたということもあって、明らかに首長のリーダーシップというものがその地域の教育の活性化に直結をしているということは、これはもう実感として感じておりますし、それは実態だというふうに思います。 しかしながら、なぜその首長でリーダーシップを発揮する人がかくも少ないのかという原因の一つに、政治的中立性というものの解釈に幅がある。例えば、犬山の石田市長は、これ学校の教員と保護者と、そして今日の参考人を始めとする専門家が入った大集会といいますか、本当のタウンミーティングをその犬山市教育委員会が主催されて、これ私も参加させていただいたことあるけれども、すばらしいこれはもうタウンミーティングが行われているんですね。そこに自ら出席をされて、そして御自身も御意見を言っておられるわけであります。こうしたことは私、大変すてきなことだと思いますし、いいことだと思っているんですけれども、政治的中立性の立場からすると、ややグレーゾーンに近いことをやっておられるということも事実だと思います。 それから、品川区長あるいは杉並区長、御本人を前に申し上げるのは少しあれですが、藤原和博さんのようなすばらしい方をなぜ杉並区だけがオファーをし、そして校長に据えたか。先ほど民間から、別にそれはビジネスからということではありませんけれども、広く世の中の教育の運営について志と情熱とそして能力を持っている人を起用すると、これができたのはひとえに、やはり現杉並区長のリーダーシップと情熱があったからだと思います。この行為もかなり政治的中立の観点からするとグレーゾーンに近い行動をされていたということ事実だと思うんですね。 したがいまして、この政治的中立というものをもっともっと首長が存分に市民、有権者の御意向を受けて発揮できるように私はすべきだろうということの観点から、首長にもっとその権限を集中し、そして今現在においては首長こそが民主的な選挙によって、正に民主的統制に服する、先ほど古山参考人からもお話がありましたが、ラインの中で保護者、住民に信任を問われないわけでありますから、今の制度の中では首長だけが、あるいは議会だけがその信任を問われると、こういうことになっております。 一方、しかしながら政治的中立性の確保というのは重要でございます。したがいまして、私どもは、教育監査委員ということで、正にオンブズパーソン制度を設けて、そしてオンブズパーソンである教育監査委員の構成については正に現行の教育委員の選考における政治的中立性、あるいは選挙管理委員と同様の選考過程を設けることによって教育監査委員は政治的中立性を持たせ、そして教育監査委員が正に首長の行う教育行政に関する政治的中立性をチェックをするという、こういうスキームを導入をしたわけでありますが、この二点について、要するに監査委員ではなぜ不十分なのかと、二点目についてはですね、それから一点目は、政治的中立条項が首長のリーダーシップの発揮を阻んでいるのではないかと、この二点について御意見をお聞かせいただきたいと思います。 参考人(高倉翔君)中立性の議論というのは、教育をめぐる議論の中で一番難しいようで、例えば公教育というものを考える場合に、義務制、無償制、中立性と分けて、みんな義務制と無償制のところまでは研究をさっさと進めていくけれども、中立性のことになるとどうもブレーキが掛かってしまう。そして、結局は逃げ込むところはどういうことかといいますと、コンドルセの第四権というような話になってきまして、教育権を司法、立法、行政のほかの外側の第四権として考えていくべきだというような話になっていって、それ以上なかなか議論が進んでないというようなところも現実にはあろうかと思います。 これは、行政における中立性どうするかということとは別に、教育学あるいはこういった教育行政を考えるというような立場にある者が何かその辺りで一つブレーキになっているというようなことがあると。私自身、そのことは深く反省しておりまして、そこから一歩踏み出すためにどういった研究の手法というものが必要なのかということを非常に強く感じております。 それからもう一つは、監査委員のことでございますが、これが監査をするというような、ある意味での厳しさというものを前面に出すシステムなのか、それとも見守る、ドイツ語でバッヘンという言葉がございますが、見守るというようなそういった意味合いでの監査委員なのか、その辺りの何といいますか、その性格付けによりまして、この監査委員会というものの実際の機能というものもかなり分かれてくるんではなかろうかというように考えております。 したがいまして、この監査委員会の議論というものも、その機能というものに求められる一体機能というのは何なのかということを明示して、あるいは類型的に示して、その一つ一つについて議論をするというようなことが必要なんではなかろうかというふうに感じております。 鈴木寛君ありがとうございます。 中嶋参考人に御質問させていただきたいと思います。 私どもも、教育委員会の公選制といいますか、正に住民の教育意思というものをきちっと反映するスキームに改変をしていくということは、中長期的な課題としては非常に興味を持って研究、検討をしているということは事実でございます。 私どもは、さらにいろいろな実践例を見ますと、やはり人口規模で申し上げますと五十万程度、杉並区が五十万程度でありますので、それぐらいが教育行政の適正規模としては非常に望ましいのかなと。ですから、それに満たないところは市町村連合とか事務組合みたいなことで、そうしたいわゆる市町村の、地方自治体の一般行政区とは異なるそうした教育行政のサイズというものができた暁には、そこにおける住民意思を反映させるという意味で、基本的には中嶋参考人のおっしゃっていることについては我々も興味を持って勉強しているところなんですが。 ただ、過去なぜ教育委員会が公選制が廃止をされたのかと。もちろん当時の時代状況ということ等もありますけれども、行政制度論からすると、首長とか議会と、このレジティマシーをめぐっての競合関係があったということ。アメリカは、すなわち、もう先生御承知のとおり、一般行政区と教育特区といいますか、は別ですよね。それから、さらにそこが徴税権まで持っているという、完全に教育委員会が、一般行政区とは地域割りも違うし、徴税権、予算執行権もこれは完全に独立した形態になっていると。 しかし、日本の場合は、徴税権あるいは予算編成権を首長に残したものという中で競合関係が存在してしまったということがあって、今の地方教育行政法になっているんだろうというふうに思いますが、この点は公選制ということを考える上でどういうふうにクリアしていくというふうにお考えかをお聞かせいただきたいと思います。 中略 参考人(中嶋哲彦君)どうもありがとうございます。御質問ありがとうございます。 今委員がおっしゃったとおりで、アメリカにおいては教育行政区とそれから一般行政区というのが区別されている場合がある、一緒の場合もありますけれども。これについては、では、その行政区それぞれの関係なんですけれども、先ほど委員がおっしゃったのは、教育行政の適正規模としては五十万人ほどだということがおっしゃられたんですが、教育行政区の設定としてはむしろ逆で、教育行政区の方が狭く設定される場合が多いと思います。例えば、ニューヨーク市のように大きな市の中で考える場合には、その中をまた分けていくということなんですね。つまり、教育行政というのは、やはり地域の、それぞれの地域の違いがありますし、学校の違いがある。それぞれに対応していくためには可能な限り身近なところに教育行政を行う組織が必要であると。その意味では五十万というとかなり大きいんですね。 まあ犬山のことばかり言ってしまいますけれども、犬山というのは七万人の人口です。人口七万人規模というのは比較的いいんじゃないかと思っています。ですから、私がもし政策をそのようにつくるとすれば、一つの市の中を更に分けて教育行政区を設定し、そこに教育委員会を置くと。ただし、そこには財政的な補助というのは必要ですから、それはもう少し大きい行政区の中で考えていくという、そういう考え方があるんじゃないかと思います。 鈴木寛君私どもも、おっしゃるとおりで、そういう意味でのレーマンコントロールとか、地域住民とか保護者の正に教育意思を反映させるためには、極力学校に近い方がいいと。我々が学校理事会あるいは地域立学校制度を導入しているということは、正にそこを教育委員会的にしてしまおうと、こういうアイデアでございます。一方、五十万と申し上げたのは、教員の採用とか研修とか人事異動ということで考えると、それぐらいの規模がないと、小さ過ぎるとなかなか難しいということなんですが、まあよく分かりました。 それで、藤原参考人にお伺いをしたいんでありますけれども、教育委員会が現状として、委員の方はですね、実態として名誉職であるということ、あるいはやはり首長のリーダーシップが重要であるということで、今現職の校長でいらっしゃいますので、制度論についてはコメントはということでございますが。 私、お伺いしたいのは、私どもも、まあ元々私はコミュニティ・スクール構想の提案を前職の慶応大学助教授時代にさせていただきましたし、正に和田中学校は地域本部というものが、私どもが念頭に置いていた文字どおりのコミュニティ・スクールだというふうに思っております。今文部省が言っておられるのは、我々は、一番最初にコミュニティ・スクールという言葉を作り出した者からするとまだコミュニティ・スクールになっていないということで、和田中こそがコミュニティ・スクールだというふうに思いますが、やっぱりそこで極めて重要なのは、もちろん学校理事会によるガバナンスということもありますけれども、やっぱり地域の皆様方の参画、そして正に老若男女の斜めの関係がそこに投入をされるということだと思っております。 それで、私が伺いたいのは、運営会議で、ここは学校関係者とその地域本部の事務局長さんですか、そういう方が入って、正にそうしたことを日々、この学校にとってプロが何をやり、ボランティアが何をやり、保護者が何をやるということの正にマネジメントをここでやっておられるんだと思いますが、その辺りをどういうふうにうまくコラボレーションをしていくのかというところの工夫を、そして何か制度論的あるいは予算的な支援の方法があれば教えていただきたいというのと。 それから私、いつも思いますのは、藤原参考人のお話は、まさしく現場のマネジメントが大事なんだということ、もうそのとおりだと思います。しかし、杉並区になかなか、あるいは東京都に、まあ私も「よのなか科」につきましてはいろいろのお手伝いをさせていただき、立ち上がりのところからこんなにすばらしいものはないというふうに思っていますが、思ったほどは広がっていないということはあろうかと思います。それから、地域本部も思ったほどは広がっていないと。であれば、ある程度やっぱり制度論として地域本部的なものを位置付けることにしましょうと、こういう教育行政制度といいますか学校教育制度というものをその枠組みとして用意をすると、それが正に学校理事会あるいは地域立学校制度なわけでありますが、今の二点についてお話をいただければと思います。 参考人(藤原和博君)地域本部という組織ですね。地域のお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさん、おじいちゃん、おばあちゃんが、言ってしまえば生徒の直接の利害関係者ではない大人が斜めの関係をつくるという。この人たちが大体六、七十人プールされて、そして機動的に動いているわけですね。これをまとめているのが元のPTAの会長の地域本部の事務局長となります。この人は、今もう二代目になっているんです。 和田中の特色は、学校を動かす職員の組織ありますね、ここに、その主任格が全部集まる運営会議というのがまずほとんどの学校にあるんです。大体平日のある曜日の一時間、一こま分けて主任格が全部集まって、校長、教頭、事務も含めて、そこにこの地域本部の事務局長が出ているんですね。言ってしまえば教務を預かる教員の組織と、それから放課後と土曜日の生徒たちの生活を豊かにする地域本部の長が一緒になって、平日の昼にミーティングをしているんです。この懸け橋ができている。言ってしまえば二枚歯になっているというようなことです。これが非常に大きいです。 今まで三年間、立ち上げてから三年間ほとんど、まあ有償といってももう本当に交通費程度のボランティアでやってきていまして、この事務局長というのは百日ぐらい恐らく学校出てくると思うんです。それで、去年振り返ってみましたら、杉並区の学校サポーター制度というのを使いまして、一日出てきますと、何時間であろうと交通費程度の二千二百円という、これで計算しましたら二十万円出ていませんでした、百日のすばらしい働きでですね。ですから、これが広まるためにはその予算的なことにつきましては私はちょっと期待するところがございます。 和田中のような三年間たった地域本部、図書室の運営、土曜日寺子屋の運営、それから部活で顧問のいないクラブへのコーチの供給、それから緑の全体の維持ですね、しば刈り含めて、それから英語の特別コースというような五つ、六つの活動をやるには、大体人件費にして、本部の事務局の人件費で三百万ぐらいあればいいと思っています。 そして、あと七十人からいるボランティアにその都度払うボランティアの運営費ですね。ごめんなさい、これは事業費と言った方がいいかもしれません。要するに、運営人件費と事業費というふうに分けますと、運営人件費に三百万ぐらい、中心になる実行委員会にちゃんと仕事として有償でお金を渡すということです。それから、ボランティアの人たちは、二千二百円の掛ける何口という形になりますけど、これがやはり三百万。合わせて六百万ぐらいが、例えば各中学校に行けばすべての中学校でこのような地域本部組織、学校支援組織が組成可能だと思います。 でも、いきなり和田中が今やっているところには到達しないでしょうから、百万ぐらいからでいいと思いますけれども、今、和田中がやっているものを維持しようとすればそれぐらいの予算。こういうものが新しい公共事業になるんじゃないかと私は思っているわけです。 それを制度的に裏付けていただけるんであれば非常にうれしいし、もう一度言いますけれども、いじめのあの自殺までの根幹ですね、あの問題の根幹には、とにかく先生、生徒、それから親子という直属の関係ではほとんどもう処理できない部分が七割なんですね。この斜めの関係をもっと豊かにつくること。 ここにいらっしゃる皆さんも見学している皆さんも全部含めて、地域社会が豊かにあった時代に育っていますから、今の子供たちの苦しさが分からないんです。斜めの関係、利害の関係のないお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさんに何となく勇気付けてもらうとか、そういうことが絶対あったはずなんですね。それが今の子にはない。それを学校の中につくり出すことが大事だということです。 もう一つの条件は、そういうことをやる場合、学校の職員会議の教員の組織とそれから地域本部の組織、両方をマネジメントするという技術が要ります。これ、私はネットワーク型の教師若しくはネットワーク型の校長と言っていて、ネットワークという感覚がない校長には経営不能です。ここは非常に大事なところなんです。今の教頭先生がほとんど事務長になっちゃっている今の現状では、その教頭先生が校長になってもほとんど無理じゃないかと思うんですね。中にはそういうふうに一皮むける人もいますので、そういう人たちと合わせて、どうしても十年間で三千人ほどのネットワークという感覚が分かる人ですね、これを大量に国策として導入して、まず中学校を何とかよみがえらせるべきだと思います。そうしなければ、学校が信じられる学校にならないんじゃないかとさえ思います。 以上です。 鈴木寛君今の、正にネットワーク型経営を実現し、今日は古山参考人、済みません、時間がなかったんですが、古山参考人がおっしゃったことを正に実現するのが我々主張している学校理事会制度、地域立学校だということを申し上げて、感謝の言葉に代えさせていただきたいと思います。 今日はどうもありがとうございました。 櫻井充君最初からそのようにお答えいただきたいと思います。本当であれば責任を取れと言いたいところです。 それは、何回も申し上げますが、一二・五%の人たちが退学に追い込まれているという実態がある。入学金だって支払っているんですよ。そして、その間、結局は辞めなきゃいけなかったら、もう一度大学に入り直さなきゃいけない。無駄な人生を送っているんですね。だから、僕は、さっきから何回もこのことが重いんだと言っているんですよ。しかし、文科省の今の答弁を聞いていると、そこまでその責任を感じているとはとても思えない。その人の人生をめちゃくちゃ軽く扱っているような気がしてなりませんよ。 そういう点で、何回も申し上げますが、文科省そのもの自体が教育行政をやるにふさわしいかどうかというのは、僕は甚だ疑問です。そして、こういうところが、先ほどのような目標というようなものを掲げて、その先どういうことにしてくるのかが極めて不安なんですよ。だから、こういうところに関して目標みたいな形で書いてほしくないというのが私の思いでございます。 もう一点、これとはちょっと離れますが、法文上、ちょっと民主党案との違いでもう一度きちんと読んでみると、教育の権利というのが書き込まれているか書き込まれていないかという点で、僕はすごく大きな違いがあるんじゃないのかなと感じています。 なぜそう感じるかというと、まず一つは、義務教育という言葉がふさわしいのかどうかなんですね。法文上の、これは民主党の案にも義務教育というふうな文言は書かれています。その義務というのは、教育を受ける側の義務ではなくて、教育を受ける人たちの保護者に課している義務ということになっています。ですが、本当にそれは保護者の義務なのか、若しくは国や地方自治体が背負うべき義務なのか、それとも、義務教育という言葉ではなくて、社会に自分たちが出て生活ができるようになるために教育を受ける権利を有しているからその期間は教育を受けることができるのかとか、併せてきちんとした議論が僕は必要なんだと思うんですね。しかし、その教育の権利ということに対して国会で余り議論されていなかったような気がしております。 そこで、まずお伺いしたいのは、今回の改正案の方に、教育基本法案の方にその権利そのもの自体が明確に書かれていない、その理由をまず教えていただけますでしょうか。その上で、民主党案の方には教育権というものをうたっておりますが、なぜその点をうたっているのか、御答弁いただけますか。 政府参考人(田中壮一郎君)先生御指摘のように、憲法二十六条で教育を受ける権利が規定されておるところでございますけれども、教育基本法におきましては、この教育を受ける権利を実現するために、一つには、生涯学習の理念を新たに書かしていただいておるところでございますし、また四条では、これは現行法にもあるわけでございますけれども、教育の機会均等ということで、ここには、すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならずという形で、国、地方公共団体がこういう国民に対して教育を受ける機会を与えなければならないという規定も引き続き置かしていただいておるところでございます。 また、義務教育に関しましては、これは保護者に対する義務、それからそれを国として、具体的な義務教育を、国、地方公共団体の責務も規定しておるところでございます。これは、先生今おっしゃられたように、日本国憲法二十六条で保障された子供たちが教育を受ける権利を、それを実現するために保護者に義務を掛け、また国、地方公共団体に責務を負わしているものだと考えておるところでございます。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 民主党の法案では第二条で明確に、学ぶ権利の保障ということで、権利を有すると、これは何人も権利を有するということを明記させていただいておりますし、それから第三条におきましても、何人も、その発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育の機会及び環境を享受する権利を有するということ、それから七条でも、普通教育を受ける権利を有すると、これも何人もという主語で権利を明記をさせていただいております。 加えまして、例えば三条の三項におきましては、国及び地方公共団体は、すべての幼児、児童及び生徒の発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育の機会及び環境の確保及び整備のための施策を策定し、及びこれを実施する責務を負うとか、四条の第一項におきましても、国及び地方公共団体の責務を規定させていただいているということでございます。 これはどういうことかといいますと、権利というのは、正に学習者の権利というのは、すべての人に権利があることを主張することができます。したがいまして、例えば学校法人等においても、あるいは学校法人の理事者あるいはそこで教鞭を執る教員に対しても権利は行使することができると。そのために権利規定と、そして、もちろん国及び地方公共団体というのは最も率先してすべての人々の学ぶ権利の実施に努力をする責務があるわけでありますから、そのことも両サイドからきちっと明記することによって実質的に学ぶ権利をきちっと保障していくということが民主党案の最大の眼目であるということで、このような規定を重層的に置かせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 櫻井充君ありがとうございました。 大臣はどうお考えでしょうか。 私は、例えばこの今の政府案の四条のところも、機会を与えられなければならずという極めて受け身の表現になっている。何か、どこからか何かが来るみたいなそういう格好で権利の保障がされるということそのもの自体、私はおかしいんじゃないのかなと。 憲法の二十六条のところは、ひとしく教育を受ける権利を有すると、これは国民がちゃんと主語になっていて、しかも能動的になっているわけですが、ここの文章でいうと、結果的には受動態みたいな形になるんですね。 ですから、能動的な権利というものが本来こういう基本法の中に書き加えられるべきではないのかなと、そう考えますけれども、大臣、いかがでございましょう。 国務大臣(伊吹文明君)憲法の規定をいかにこの基本法において具現していくかということでしょうから、権利を先ほど民主党の提出者がおっしゃったような形で書くという立法形式をお取りになるということは何ら否定しませんが、我々が、先ほど政府参考人が申し上げましたように、三条、四条、五条という規定を置いて、それをこの基本法の下位法及び予算で補完をしていくということで、私は憲法上の国民の権利は十分守られるという立法意図でこの法案を作成しているということです。 櫻井充君どういう形に表現するかということはいろんなやり方があると思います。ですが、申し上げたとおり、この文言の、この条文の書き方だとあくまで受け身の形であって、自分たちのところから発生してきているような権利とはちょっと思い難いところがあるんです。 つまり、与えられなければならずという言葉なんですね。その与えられなければならずという言葉ではなくて、憲法上きちんと書かれているような教育を受ける権利を有するという、何回も繰り返しになりますが、能動的な表現にした方が私はいいんじゃないかなとそう思いますが、じゃ、民主党の発議者から今手が挙がっておりますので御答弁いただきたいと思います。 鈴木寛君憲法二十六条に定めます学習権は、プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説が存在いたしておりまして、これがどの説を取るかということについてはまだきちっと確定をいたしておりません。 今回、私どもが教育基本法を作る際には、こうした憲法上の解釈の疑義を正に憲法附属法であります教育基本法において確定をさせる、正に具体的権利として学ぶ権利を確定するために先ほど御説明を申し上げたような諸規定を置かせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。 |