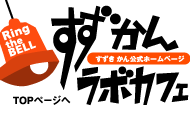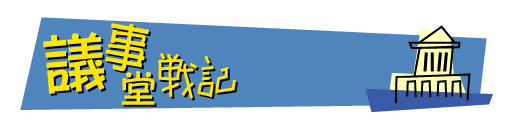2006年12月05日 教育基本法に関する特別委員会蓮舫君民主党・新緑風会の蓮舫でございます。 今日は、政府提出の教育基本法案、そして民主党提出の日本国教育基本法案について、比較をして、そして質問をさせていただきたいと存じます。 まず、その前にいじめ自殺について大臣にお伺いをさせていただきたいんですが、理念法を変えるだけではなくて関連法を変えて、あるいは教育行政の在り方、教育行政に携わる大人の感性の在り方をどのように整備していくのか、これもとっても大切なことだと思うんですが、いじめ自殺の中でも、私は連鎖して一か月に三件も起きてしまっていることに大変危惧を抱いております。 大臣のお考えでは、このいじめ自殺の連鎖についてメディアの影響はどのようにお考えか、お聞かせいただけますか。 中略 蓮舫君伊吹大臣は大変民主党案に造詣が深くておられますけれども、今、第十七条で情報文化社会に関する教育を民主党は日本国教育基本法案で条文化しております。 民主党提案者に伺います。あえて理念法の中にこの情報教育を導入したのはどういう意図からでしょうか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 委員御指摘のように、民主党が提出をいたしました日本国教育基本法案におきましては、第十七条で情報文化社会に関する教育という条項を盛り込んでございます。 これは、正に今回の、まあ大きく申し上げますと二つあります。今回の教育基本法を新しく作り替える意図というのが、明らかにこれ、モダン社会からポストモダン社会、正に産業社会から情報社会への移行期、その移行期にあって、情報社会で生きていくということが、これから生きていく力を身に付けるということが教育の本質でありますので、情報社会についてきちっと理解をするということは極めて重要な、今回の教育基本法を作り直す極めて重要な時代的背景があるという中でこの条項を盛り込んだというのが一つ。 それから、昨今の教育現場を見ますと、明らかにインターネットに伴って光と影、双方極めて色濃く影響いたしております。例えば、いじめの問題などを取り上げましても、携帯あるいはウエブサイトによるいじめという従来にはなかった新しいいじめの様相を呈しておりまして、そのことが極めて深刻な影響を与えているということも事実でございますし、それから、ある調査によりますと、子供の約五分の一が正にリセット、命すらリセットできるという極めて深刻な報告などもございます。 私自身は実はこの情報教育というものの旗を振ってきた人間ではございますが、であればこそ、正に情報洪水の中で子供たちがきちっと正しい情報とそうでない情報を見極めていく、正にメディアリテラシー、情報リテラシー、加えましてインターネットには正にもろ刃の剣でございまして、光と影、これをきちっと教育において教えていく必要がある。 今、授業時間は約八百時間から九百時間でございます。これを三百六十五で割りますと二・二時間。それに対しまして、子供たちがインターネットやテレビに向いている時間は四・二時間ということで、子供たちの学びに対して、授業時間の二倍、実時間で見てもインターネット、テレビ等を通じたいわゆるバーチャルな情報というものが極めて重大な影響を与えているという実態にもかんがみまして、この条項をあえて、幾つもある教育にとって必要な事項の中でとりわけ重要なものだということで教育基本法に盛り込んだということでございます。 蓮舫君大臣にお聞きいただきたいんですけれども、私の子供は双子で今小学校三年生なんですね。小学校三年生にもなると、やっぱり学校の中で子供たちの社会ができて、そこで自分が持っている情報が足りない、メディアに触れていない、知らない、見たことがない、サイトにアクセスしたことがないということが、一歩間違えるといじめられるというかグループの中に入れない、そういうなかなか難しい年ごろになっているんですが。 最近、子供たちの間で大きなうわさとなっているのが、インターネットのあるサイトが大変人気になっていまして、帰ってきてどうしても見たいと、話題に入れない、だからアクセスしてくれ。うちでは子供にパソコンは触らしていませんから、それは駄目だと。で、夜、子供たちを寝かし付けた後に見たんですが、このサイト名というのは日本のみならず世界じゅうの大人も子供も知っている大変有名な絵本をもじったサイト名で、アクセスをすると一番最初に大変有名なその絵本の絵が出てくる。で、どこかをクリックする、ボタンを押す、あるいは数秒そのまま放置をしておくと何が出てくるかというと、怖い映像と写真と物すごく心臓を圧迫するような効果音が瞬時のうちに何度も出てくるんですね。ほかにも、何と、幾つかのサイトを見たり全部アクセスをしましたけれども、恐怖心をあおるいわゆるホラーサイトです。これはもう大変な人気になっていて、見ていないと仲間外れにされるというようなことがあるんですが。 専門の会社に今はお金を出したら、ある特定のサイトへのアクセスを制限できるフィルタリングサービスを行うことができるから、自宅で子供にパソコンを渡すときにこのフィルタリングサービスを行ったものを渡すことはできるんですが、友達の中で自宅でそれを保護者がしていない場合ですとか、あるいはネットカフェですとか、あるいは公的なところでもアクセス制限をしていないところがありますから、自分のうちを守ったとしても、一歩外に出たらこういう怖いサイトとか、ある種いろいろな恐怖心を植え付けてしまうようなインターネットの世界に入ることって今可能なんですね。 総務省にお伺いしますが、こうした子供へ悪影響を与えるサイトを出している業者に有害サイトを掲載しないようにすることはできるんでしょうか。 政府参考人(中田睦君)お答え申し上げます。 基本的に、今の法体系の中で直接的に禁止することは困難でございます。プロバイダー等がその協会によって自主的にガイドライン等を作って対応しているということでございます。 蓮舫君今御答弁あったように、なかなか法的には取りこぼされているところなんですが、つまり業界の自主的取組に任されている。今、これ、総務省もこの取組を支援して、今年四月から総務省と通信業界が協力して、子供たちのインターネットの安全利用のための保護者、教職員向けの講座を、これ実は文科省とも連携して行っているんですね。文科省としても子供のインターネットの安全利用は大切だということの行動の表れだと思うんですが、実施期間は三年間で、目標はわずか千講座なんですよ。大臣も御案内のとおり、小中高、国公立入れると四万校ある中で千か所でしか、しかも三年間という長い期間を掛けて。 ネットの世界ってもう本当に一日一日変わっていきますので、人気がなくなってはなくなるサイトですとか、新しい要請に応じて、いわゆるいじめ自殺をあおるようなサイトとか、あるいは自殺ネットとか、今いろんなものがあるんですけれども、懸念されるのが、こうしたサイトに自主的取組でしか制限することができないと。じゃ、子供はどういうふうにこの情報を自分の中で親がカバーできないところを自制できるのかなと。 そこで、民主党提案者が先ほど言った、今のこのITの時代において、メディアリテラシー、子供が自分にとって必要な情報だ、そうじゃない、これは有害な情報だ、それを自分の力で判断できるやっぱり教育環境というのを国として私はつくる必要があると思うんですが、いかがでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)子供のしつけ、あるいは家庭での教え方というのは、それはいろいろ御家庭での特色、考え方がありますが、子供さんにパソコンをいじらせないというのはうちの孫の教育方針と全く同じで、大変心強く聞いておりました。 今おっしゃったことは大変大切なことでございますから、単にパソコン、インターネットでの情報以外にも、それはもう有害図書その他ありとあらゆるものが全く同じなんですよ。情報関係のものはすごいスピードで今伸びているということも私よく分かります。ですから、先生のおっしゃっているお考えを実現していくということは、私は全く異論はございません。今日のお話も多分、この国会中継という情報網を通じて文科省の連中も今これをリアルタイムで見ておると思いますから、その方向で努力をさせたいと思います。 そのことと、基本法にそれを書き込むかどうかということは、これはいろいろな考えが私はあると思うんですよ。図書の問題についても同じようなことがあるでしょうし、あるいはそれ以外の情報の伝達についてもいろいろなことがあると思います。そういうことは、やはり学習指導要領その他において、今おっしゃっていることをきちっと学校に伝達をしてやらせるというのが私は正しい方向じゃないかと思っております。 蓮舫君民主党発議者にお伺いしますが、今、伊吹大臣が御答弁された学習指導要領で十分事足りるという政府のお考えなんですが、民主党発議者としてはいかがでしょうか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 正にこの有害情報ですね、今、伊吹大臣から、ネットのみならず、いわゆるリアル空間といいますか、通常の子供を取り巻く環境の中にも有害情報が満ちあふれていると、そのことは私たちも全く同じ認識をいたしております。 今回、民主党案の十七条の三項では、「すべての児童及び生徒は、その健やかな成長に有害な情報から保護されるよう配慮されるものとする。」という条項を盛り込みました。あえて教育基本法にこの条項を盛り込んだのは、むしろ教育基本法でないとこの手の条項は盛り込めないという判断をしたからであります。すなわち、この教育基本法より具体的な規制法において、これはメディアも含むすべての主体に対してこうした努力を求めるという規定でございますから、規制法にこういう条項を盛り込むことはできないわけですね。それは、先ほどの報道の自由、表現の自由との関係でございます。 教育基本法というのは正にその基本法であり、世の中すべての主体が子供の教育にとって望ましいことを努力していこう、そういうことを確認したり宣言したり、そういうふうな教育宣言的な要素も教育基本法というのは含んでおります。 したがいまして、教育基本法であれば、このような努力条項を盛り込むということはこれは一定程度許されるだろう、あるいはそういうことが望ましいであろうということで、様々な議論を経た結果、正に教育基本法にこうした有害情報についての訓示規定を盛り込むということにしたところでございます。 中略 蓮舫君民主党発議者にお伺いをいたしますが、今の一連の質疑、大臣と私の質疑を聞いて、改めて私は教育基本法の理念というところ、大臣はそこに載せるまでもないとおっしゃっていますけれども、私はやはり載せるべきだという姿勢はこれ崩せないと思うんですが、改めてそこを強く今のお気持ちを聞かせていただけますか。 鈴木寛君今の点、ちょっとお答えをする前に、先ほど大臣から十七条についてのコメントがございまして、一項、二項について、促進ということでございましたが、私どもは、インターネットを利用した仮想情報空間におけるコミュニケーションの可能性、そして限界及び問題について、その双方について的確に理解し、適切な人間関係を構築する態度と素養を修得するよう奨励されるものというふうに一項で盛り込んでおります。 先ほど大臣もおっしゃいましたように、大臣は立法技術というふうにおっしゃいましたが、これは正に立法姿勢の問題だというふうに私どもは理解をいたしております。私どもは、このインターネットの革命を発端とします正に情報革命の中で、明らかに情報というものが極めて重大な影響を与える時代に差し掛かっております。六十年ぶりに改正をするというのは、新しい時代にふさわしい、子供たちに生きる力を身に付けるということがやはり必要であるということで、この条項は外せない極めて重要な条項の一つだということで盛り込まさせていただいているということであります。 それから、先ほどこれは通信の方でやったらいいのではないかというお話がございましたが、私どもはそうした立場を取りません。なぜならば、通信ということになりますと、通信の秘密あるいは表現の自由に正に抵触する可能性がございます。我々は、子供の教育という分野であれば、訓示規定という限りにおいてはその有害情報について一定の条文を盛り込むことに妥当性があると思っておりますが、一般の国民をも対象とした通信法の中で、しかも規制法の中で有害情報についての規定を盛り込むことは憲法上も不適切であるという立法姿勢を取っておりますので、これはあえて教育基本法の中で盛り込むことが妥当であるという結論に至っているということで御理解をいただきたいと思います。 蓮舫君続いて、民主党案にあって政府案にはない条文についてお伺いをしていきますが、まず御紹介をさせていただきたいのは、去年大きく報道されたんで記憶にある方もおられると思います。おととし六月に長崎県佐世保市の小学校内で同級生同士の女の子が加害者、被害者になるという大変痛ましい事件がありました。このきっかけも、交換日記のみならず、ホームページ、子供たちがつくっていたホームページ、そこへの中傷、誹謗という、インターネットがやはりここにも密接に不可分にかかわっていたんだという、だからこそ私はITを問題意識を大変強く持っているんですけれども、この事件の家裁の最終審判の決定要旨で、加害女子児童が死のイメージが希薄であると報告されたんですね。 それを受けて長崎県が、「児童生徒の「生と死」のイメージに関する意識調査」を行いました。対象は小学校四年生、六年生と中学校二年生。「死んだ人が生き返ると思いますか。」という設問、はいと答えた児童生徒が一五・四%おりました。このはいと答えた理由の中には、霊として生き返るからとか、人間は死んでも生き続けると思いたいからという理由もあるんですけれども、それでも七人に一人が人は死んでも生き返ると考えていたと。大変衝撃的な私はこれは調査報告だったと思うんですが。 民主党案では、第十六条で「生命及び宗教に関する教育」を掲げているんですが、これはどういう意図でこの項目を掲げられたんでしょうか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 正に今御指摘のありました事例を含めまして、本当に昨今、起こっております子供の教育現場をめぐる様々な事件というものは、死というものが子供と従来に比べまして身近ではなくなってきているという中で、我々がびっくりするような出来事が起こっているわけでございまして、教育の現場でこれ以上真剣に取り組んでいかなければならない問題はないというふうに我々考えております。 一方で、様々な教育現場におきましては、例えばデスエデュケーションという死をとらまえた教育につきまして、極めて真摯かつ真剣な、そして子供の生きる力を、そして成長にとりまして極めて有意義な教育実践が行われていることも事実でございます。そうしたすばらしい実践をこれだけ大変な事態にある教育現場に広めていくということもこれは極めて意義深いことでありますし、今起こっておりますいじめを原因とした自殺の問題等々にも極めて有効だというふうに考えておりまして、そういった意味で、生の意義と死の意味を考察し、命あるすべてのものを尊ぶ態度を養うという実践を、今こそこの新しい教育基本法を作ることによって広めていきたいという我々の決意を表したところでございます。 以上でございます。 蓮舫君政府案では、第十五条で宗教教育、宗教に関する一般的な教育を理念とすることで、大臣、今御紹介したような、命はリセットできる、死んでも生き返るんだと思っているような子供たちの認識を新たにすること、あるいは生きること死ぬことというものに対してきっちりと教育できるんでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)まず政府案では、二条四号に生命を尊ぶ態度というのが教育の目標に書いてあるわけですよね。その生命を尊ぶ態度というのは、自分の命も掛け替えのないものであるけれども、同時に相手の命も掛け替えのないものであると。さらに、正確にその条文を読ませていただきますと、「教育は、その目的を実現するため、」云々云々と書いてあって、「生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。」と、こう書いてありますから、自分の命、他人の命だけではなく大自然の中に存在する人間以外の生命、自然を大切にし、これをすべて大切にしていくことが教育の目標だということを明示しているわけです。 民主党さんの案にも、先生がおっしゃったように、十六条だけではなく前文にも大変美しい文章でそのことは書かれております。ですから、これはこれで民主党案も立派な案だなと私思っております。 どういうふうに書くかというのは、これは立法者の意図の問題ですから、理念法にどこまで書き込むかということ、そして書き込んだことを各法において具体的にどのように実現していくかということが、これ今後、行政権を預かる内閣に課された仕事だと思います。 蓮舫君政府案のこの第二条、教育の目標を今お話しになりましたけれども、やはりこの話になると、態度って何なんだろうかということになるんですね。その第四条で生命を尊ぶ態度を養うこと、態度は大切でしょう。 でも、大臣、例えば態度として、犬をかわいがるとか猫をかわいがる、これ態度としてあるかもしれませんけれども、でも、だれも見てないところでその猫をけったり虐待をしたり、いじめることもできて、態度って実はふりができるんですね。ふりができるものが教育の目標としてふさわしいんでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)それでは私から伺いたいんですが、民主党さん案の……(発言する者あり)いやいや、伺いながらお答えしますから。民主党さん案の十六条、生の意義と死の意味を考察し、生命あるすべてのものを尊ぶ態度を養うことは、教育上尊重されねばならないと。ここも態度じゃないんですか。ですから、態度とおっしゃったら同じことなんですよ。 ですから、態度を養うということは、当然そのような心を持たなければ態度も養えない。ただし、その内面に入っていろいろ心情的なものを強制するということになると、人間同士の命を尊重しなければならないというのは、これはもうほとんどの方が、というか一〇〇%の方が異議がないところでしょう。 しかし、動物の命を尊重するということになりますと、釣った魚はすべて食べることによってその魚の命を尊重したという考え方もあるわけですよ。釣った魚を放流することによって命を尊重したという考え方もあるわけですね。 ですから、そこのところに踏み込むということを避けているわけですね。ですから、命を尊重しなければならないというのは、それは民主党さん案も我が方も全く同じなんですよ、そういう意味では。 蓮舫君ほかのところでまたこの態度についてはお伺いしますが、せっかくですので、民主党発議者に、大臣が大変うれしそうに同じではないですかという御答弁がありましたが、違うというところをどうぞ御指摘をいただきたいと思います。 鈴木寛君お答え申し上げます。 私どもは、この法案を作る際に、心と書くべきところと態度と書くべきところを慎重に一つ一つきちっと吟味しながら書き分けさせていただいております。 生命につきましては、正に心ももちろん必要でありますし、それから本当に生命を大切にする態度ということもきちっと養わなければいけないというふうに考えておりますし、例えば十五条では、政治教育というところがございます。真の主権者として自覚と態度を養う。これは例えば投票に行くことの意義をきちっと認めるとかそういったことも、これは義務教育だけではございませんから、この教育基本法は投票権を持った人をも対象としており、そうした方々にはやっぱり態度ということ。 しかしながら、蓮舫議員のおっしゃりたかったことは、政府案の二条においては、一律にこれらの項目について態度となっていると。私どもはそれぞれ一つ一つきちっと吟味をいたしまして、そして心の涵養にとどめるべきところと、それから生命あるいは政治的な有権者としての態度のように、態度もきちっと、ある意味ではそのことを教え、そしてさらには、まあ何といいますか、かなり強く指導をするといったことにも踏み込むということで態度ということを使わせていただいております。 したがって、態度は指導の対象であるということを私たちは理解の上でこのような条文の整理をさせていただいているということであります。 蓮舫君よく御理解いただけたんではないかと思います。 続いて、このやっぱり宗教に関する、私、一般的な教養という条文に違和感を感じるんですね。一般的な教養とは何でしょうか。政府案で十五条です。 国務大臣(伊吹文明君)十五条のことをおっしゃっているわけですね。 蓮舫君はい。 国務大臣(伊吹文明君)民主党案の十六条に規定されております宗教的感性の涵養という言葉について政府案で考えていることは、やはり宗教的情操ということに立ち入ると、個別の宗教の教義にある程度立ち入って教えるというか、ことをしなければならない。私はそのことは別段構わないと思うんです、私自身はね。衆議院でもお答えしたんですが。ただ、その教える人の態度として、正に布教的な意識を持って宗教的教義を教えるということが出てきた場合は、これは宗教の、公教育の宗教的中立ということからはいろいろ問題が出てくると。しかし、蓮舫先生が、あるいは私自身が、例えば生徒に対したときに布教的意識を持っているかどうかはだれも分からないんですよ、率直に言って。その人の心の問題ですから。ですから、極めて慎重にすべきだという感じを、特に行政府にいる者としてはね。 ですから、このような言葉を使ったわけで、一般的教養というのは、例えば、もうこれは日本人にはそういう意識は非常に少ないですけれども、イラクがなぜあんな状態になっているのかとか、イスラム世界やキリスト教世界では比較的自殺については自己抑制的なあれがあるのはどうしてなんだとか、十字軍というものが何でああいう形で出てきたのか、それによって今アラブの人たちのヨーロッパ文化に対する感じはどうなのか。それはやはり、少しずつ教義は教えないといけませんね。それが一般的教養だと私は思います。 蓮舫君民主党発議者にお伺いをいたします。 伊吹大臣にも御理解いただきたいんですが、私どもは意識して布教教育を行うようなことを推奨しているわけではないんですが、民主党案では一般的な、宗教に関する一般的な教養としなかったのはなぜでしょうか。 鈴木寛君お答え申し上げます。 そもそも法律の用語の中で一般的という用語を使うと、これは極めて多義的なあいまいな部分も残ってしまいますので、私どもは、宗教的な伝統や文化に関する基本的な知識を修得してもらいたいということが正に教養の重要な要素の一つでありますので、そのことをそのとおりに明記することが望ましいであろうと。そして、加えまして、宗教の意義についてその理解をきちっと進めていくということでありますので、より明確に、何を教え何を教えないのかということを明確にするためにも今申し上げましたように具体的に書かせていただいたところでございます。 それから、我が方の十六条の四項では、いわゆる公立学校において特定の宗教の信仰を奨励し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないということを明記をしておりますので、先ほど大臣の懸念は、これによって条文としては払拭をしております。 ただ、この条項を、これは正に立法姿勢の問題だというふうに思っております。 私どもは、日本のこの六十年間の教育が余りにも宗教ということを避け過ぎてきたことによって、学校教育の場で健全な宗教教育がほとんど行われなかった、あるいは行われようとしたときに何か障害があるという事例が多発をしてしまったことは極めて残念だというふうに思っております。そういう中で、例えばオウム真理教のような、極めて教養があると思われている若い大学生がそうしたところに走ってしまったと。それはどこに我々の教育上の問題があったのかということを深く反省したときに、やはり宗教的なことについても避けることなく、必要なことはきちっと公教育の場で教えていくべきだということで、従来の路線とはここは明らかにかじを切っておりますけれども、それはそのようにすべきだという判断の下にこのような条文を明確に明記させていただいているということで御理解をいただきたいと思います。 蓮舫君先日行われた参考人質疑で、全日本仏教会の杉谷参考人が言われた言葉が大変印象的で、文化としての宗教、生きた学びをすることの大切さを教えると。今どうしてもそのマイナスで、死んではいけないんだ、あるいは死というものに対しての、いじめ自殺があるからなんですけれども、そういう話題がメディアを中心に、あるいはお母さんたちの間でも話になっているんですけれども、そうじゃなくて、生きた、生きることの教えというのは、私は大変大切なんだと思います。 そういう部分では、現行法の教育基本法でも、政治教育に対しては一般的な教養となっていながら、じゃ、今の若者の政治離れあるいは政治への無関心というのはなかなか担保されていないと思いますので、今生きた学びが必要なときに、新たに教育理念法を変えようとするときに、そこの生きる意味というものを一般的なものでいいんだとすることが、果たして私は本当に子供たちの心に涵養するような宗教的意識、文化を伝えることができるのか甚だ疑問なんですが、いかがでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)私も世界のすべての宗教について通暁しているわけではありませんが、一応西洋の歴史、東洋の歴史、中国の歴史等はかなりの程度自分じゃ学んだというつもりでおります。そこからしますと、宗教、今先生が正におっしゃった生きる姿勢というか命の尊さ、これはあらゆる宗教にその教義として、表現の仕方としてはいろいろなものがあると思いますけれども、命の大切さとかあるいは大自然に対する謙虚さとか、今生きているこの時代は悠久の流れの中では非常に短いものだとか、そういうことは大体ほとんどの宗教に共通していることなんですよ。 ですから、そういうものの態度を涵養するということは、私はそれでよろしいんだと思うんです。しかし、この民主党さん案の対案に示されている宗教的感性の涵養ということを具体的に教えようとすると、日本の場合は特に多神教というか、宗教心が非常に希薄な国民ですよ、諸外国と比べて。例えば、ドイツなんかは宗教の名前を冠した政党そのものが存在するわけですから。 ところが、日本は、先ほど鈴木先生が提案者としておっしゃったように、そこについては非常に憶病に来ているという事実は確かにあるんです。ありますが、その憶病であった事実がなぜあったかというと、いろいろな宗教が混在しているというか無宗教と言ってもいい状態であるだけに、一部のある特定宗教を非常に熱心に信仰しておられる教師がおられたとして、その宗教的感性の涵養に努めた場合には、自分の心の中にある意図が布教的な意図がなくても、と本人はおっしゃると思うんだけれども、周りの者から見ていると随分布教的な意図がある宗教教育をするじゃないかということが非常におそれがあるわけです。 ですから、是非私は先生のお口から民主党の提案者に伺っていただきたいんだけど、日本において宗教的感性の涵養というものがどういうものを指しているのか。一般論としての私の言ったような生命の尊重とか大自然に対する謙虚さとか、こういうものを指しておられるのか。いろいろあるキリスト教でも、プロテスタント、キャソリック、いろいろありますね。キャソリックの中にもいろいろな宗派があります。そういうものの中でのその宗教的感性の涵養ということになっているのか。もし後者であると、これはやはり公教育でこの立場を取るということは、かなり慎重でないと司法の場で争うような問題が出てくるということを恐れているわけです。 蓮舫君大臣の御指摘、大変よく分かります。 多分私ぐらいの時代までには、まあ育った環境にもよると思いますけれども、やおよろずの神ではないですけど、一木一草に神が宿って、それこそおばあちゃんからは、御飯粒にも神様がいるから残しちゃいけないんだ、だから御飯は大切にしよう、あるいは、いただきます、ごちそうさまの意味も含めて家庭教育、地域というものがあったんでしょうけれども、今はそれが全部がらがらっと音を立てて崩壊をしていって、じゃ宗教心というのが全く、無信教といいますか、生きるとか死ぬとかいう部分も極めて透明な中で、相手を傷付ける、あやめるということの悪い、なぜ悪いのか、なぜ人を殺してはいけないのか、そういう思いが出てきてしまう大変不安定な時代だと思うんです。だからこそ、一般的な宗教の教養だけではなくて、その命というもの、生きる、文化としての宗教というのは教育で大切だというのが私どもの姿勢なんですね。 大臣が御指摘された、その教える側がある目的を持ってその自分の心の中にある宗教を教えるのは望ましくない、それは当たり前のことで、それは適格かどうかという教師の資質の問題になってくると思うんですが、この件に関して民主党発議者、いかがでしょうか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 民主党案の十六条三項で言っております宗教的感性といいますのは、正に伊吹大臣もおっしゃった自然や万物に対する畏敬の念でありますとか命に対する尊さ、多くのこの世界で長年多くの方々に信仰されている宗教が共通的に持つそうしたものを指しているということでまず御理解をいただきたいと思います。 そこについては、伊吹大臣と私どもで大きな違いはないかと思いますけれども、その後に、それを教えることがどうしても宗派性が出てしまう可能性を懸念されているようでございますが、その懸念はまず私どもは第四項できちっと払拭をいたしておりますし、それから、これは更に申し上げますと、実は今でも学習指導要領の中には宗教的情操という言葉が盛り込まれていて、そしてその学習指導要領に基づいて長年教育が行われているんですね。であれば、そのことについては懸念がないのかと、こういうことになってしまうわけで、私どもは、学習指導要領の中で宗教的情操ということが盛り込まれて、そのことが特段の懸念なく今までに至っているという実態と、そして、しかしながら一方で、特に教育基本法ができた当時というのは神道指令というものが出まして、過度にそうした、もちろんあのときは執拗だったと、ある程度やむを得なかったというふうに思いますが、しかし、今日これだけ宗教というものが教育が必要な中で、そのことについてきちっと整理をして、そしてこの神道指令についてもきちっと決算といいますか、評価をし直して、そして今の我々の宗教教育というものについての意思というものをきちっと名実ともに確定をしていくということが新しい教育基本法を作る上で必要であると。そして、そのことが現場の混乱を解消していくんだと、大きな一歩になるというふうに考えております。 蓮舫君今の民主党発議者の答弁に対して、大臣はどのようにお考えでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)学習指導要領にはそのような言葉を使っております、確かにね。しかし、それは現行の教育基本法の九条があるから使っているんであって、九条なしにその言葉を使うということは、学習指導要領のようなことを書くということは非常に危険であるわけですよ。ですから、今回も、今と同じ例えば学習指導要領になることはないと思いますが、仮に今と同じ学習指導要領であっても、私の言ったようなことが阻却されるために教育基本法の文言を置いているわけでして、民主党さん案のまま、今、例えば今の学習指導要領を使うということになると、仮に宗教教育はしちゃいけないということが書いてあるから構わないんだという、その二つの間には二律背反的なことを同じ法律の中で書いておられるんじゃないかという気が私にはしますね。 蓮舫君二律背反的ではないと私は理解しているんですが、どうしても大臣はなかなか御理解いただけないんで、再度、民主党発議者の方に、今の大臣の御答弁に対して、違うんだという御答弁を明快に一言いただけますか。 鈴木寛君二律背反というか、どこできちっとこの線引きをしていくのかと、要するにバランスの取れたですね。これは二律背反というか、いずれも重要なことを盛り込ませていただいて、これは現行九条においても、私どもの提案している十六条においても、あるいは政府案の十五条についても同じことだというふうに思います。 ただ、その線引きの程度といいますか、どこまで宗教教育によるかということにおいて、現行の九条と政府の十五条と民主党の十六条でこのあんばいが違うことは、これは明らかでございます。で、どのあんばいにするかということは、正に国民の皆様方に御議論をいただいて、私どもは、今までの六十年間の日本の教育現場を総括したときに、こういうことが必要だということで十六条のこの条項を提起させていただいておりまして、そのことについては懸念なくこれからの教育現場において実施することは可能だという判断をいたしておりますが、大臣はそこについては懸念があると、ここが見解が分かれているわけでありますが、しかし、全国会議員の恐らく、自民党の皆様方にも聞いていただきたいと思いますけれども、民主党の考え方については過半数以上の、個別に議員の皆様方に問うていったならば、御理解と御賛同が得られるというふうに私どもは信じております。 蓮舫君次に、民主党案にあって政府案にないものとしては職業教育があると思うんですが、大臣は何度も御答弁をされておりますが、ニート、フリーターをつくらない教育をしていきたいんだ、だから教育基本法の理念の中でも政府案にはこういう思いを盛り込んでいきたいという御答弁をされているんですが、具体的には、ニート、フリーターをつくらない教育はどこに条文があるんでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)私は答弁をすべて覚えているわけじゃないんですが、フリーターというのは、やはり自分の意図を持ってある仕事を見付けられる間、定職に就かずにやっておられる方ですから、私は、フリーターとニートを一緒に御答弁したことはないと思います。 ニートというのは正に、職業にも就かない、仕事、それから学校にも行かないという人たちで、だから、それは単に職業ということだけを含んでいる概念じゃありません。 我々の御提案している政府案の二条二項では、勤労を重んずる態度を養うということをまず書いておりますね。そして、これ正確に条文を読まないといけませんが、教育の目標の中の二項に、個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を養い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うことということを掲げているわけです。ですから、これを受けて必要な措置をその他の法律あるいは通達、予算等で肉付けをしていくと。 先生、民主党案にはあって政府案にはないとおっしゃるけれども、それは条項を立てていないということなんですよ。ですから、これはないということではなくて、これは立法技術の問題で、特にそれを重視しておられるからお立てになっているということは十分私は理解しますが、我々がそれを書いていないということはちょっと適当じゃないと思います。 蓮舫君失礼しました。条項にないということでございます。 条項に立てているということが、いかに私たちがその条項を重んじているかということは御理解をいただきたいんですが、勤労を重んじる態度、これは先ほどの、我が国を愛する態度とはまたちょっと違うと思うんですが、この勤労を重んじる態度って何でしょうか。重んじる態度、ふりをすればいいということでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)他人の働いておられること、そして自らも勤勉で努力をし働くことを、これは当然尊重するということです。 蓮舫君民主党発議者にお伺いします。 民主党は条文で、第十四条で職業教育という条項を立てておられますけれども、この意図するところをお聞かせください。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 一条を立てるか条項に置くかと、これはもうおっしゃるように立法技術の問題でございまして、そこは、何といいますか、美的センスの問題と、それからいかにこの、感性といいますか、それを重要視していくかと、そういう姿勢の表れであります。 ただ、一点御理解をいただきたいのは、勤労の尊さを学びということを私ども言っております。その点については、政府案が言っております勤労を重んずる態度を養うことと、ここはほぼ同義で御理解をいただいたらいいと思いますが、加えまして、私どもは、政府案になくて私どもの案にある点について明快に御説明を申し上げますと、子どもの権利条約の第二十八条で、すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これを利用する機会が与えられるものとするということで、これは学習権の重要な一部であるという、私どもは理解をいたしております。そして、そのことを十四条で勤労の尊さを学ぶということと加えて、正に職業に対する素養と能力を修得するための職業教育を受ける権利を有し、そして、国及び地方公共団体は、そのことを振興することに努めなければいけないという義務規定、要するに、学習者の側の権利規定と国及び地方公共団体の義務規定まで踏み込んでいるというところが政府案と私どもの案の違いだというふうに御理解をいただきたいと思います。 蓮舫君伊吹大臣にお伺いしますが、今フリーターの方が二百一万人、ニートの方が六十四万人、大臣はよりニートの方の対策に重きを置かれたいということだと思いますが、二つあると思うんですね。 生涯教育という部分でこのニートの方たちにどうやって就業訓練をしていただくのか、自分の能力を上げていただくのか、そして仕事に就いていただく重さというものを感じていただけるのかが一つと、もう一つは、これから育っていくお子さんたちに仕事に就く夢ですとか、自分がなりたい職業を見付けるですとか、この二つだと思うんですね、職業教育というのは。これはどういうふうに整理をされているんでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)あえて言えば、先生がおっしゃった二つに加えてもう一つ、正に幼児期から始まって、働くことの価値、大切さ、これをまずしっかりと身に付けて、その上で生涯教育の中で、正に安倍首相の言葉をかりれば再チャレンジするような職業訓練その他の能力を付けていくということなんだろうと思いますが、これは今の申し上げた二条を受けて、あるいは社会教育の規定を置いておりますから、政府提出の法案には。いろいろな場面で今先生がおっしゃったようなことができるように、これは各法において準備をしていきますし、また学習指導要領において指導していくという形になると思います。 蓮舫君今お話しになられた再チャレンジという言葉、私余り好きではなくて、再チャレンジの前にチャレンジがあるんだと思います。そのチャレンジをするために、育っていく子供たちにどういう職業を見ていただけるのか。 恐らく大臣、二十二年入省と伺いました──違いましたか、昭和二十二年。恐らく大臣の幼少のころと私の子供のときと決定的に違うのは、大臣が恐らく小さいお子さんだった、利発的な頭のいいお子さんだったんだと思いますけれども、近くに仕事があったと思うんですよね。大人が働く姿を見ていたと思います。農林水産業ですとか個人事業主ですとかあるいは零細企業ですとか、本当に何もない時代から復興していこうと大人が頑張って、ゼロから始めた大人の働く姿、働く姿勢、仕事というものを子供が間近に感じて、そして自分は大人になったらという、極めて仕事という感覚が近くにあって育ってきた時代だったと思うんですが、それが高度経済成長時代を経て、みんなサラリーマン化して、会社人間になって、女性も働くようになって、家庭というものと仕事とが明快に分かれるけれども、家庭の中は随分と変わってきて、その結果、子供さんにとっては仕事というのが何かすごい遠いものになってきていると、ここは大きな違いだと思うんです。だからこそ、私たちは子供たちにもっと仕事を近くに感じてもらいたいんだと。 子供たちが学校を中心に、地域立学校に行って、地域の人たちも参加をしていただいて、子供たちが授業の一環、あるいは放課後、あるいは土曜日にその地域に出ていって教えていただいた、助けていただいた大人たちの仕事を見るという経験を実は重視して学校理事会というものを条文に入れさせていただいて、地域立学校、ここで地域を再生させるんだということを言わせていただいています。横文字で言うとコミュニティ・スクールということになるんですが、恐らくそういうふうに、毎日毎日地域の方たちと仕事が近づくようなそういう制度をつくっていかないと、今は地域を再生することも仕事を子供が近くに感じることもなかなか難しい時代だと思うんですよね。 ここはあえてお聞きをいただきたいんですが、民主党発議者に伺いますが、私たちが目指している日本国基本法案の先にある日本の子供たちが置かれる教育という環境をどういう姿勢を目指しているのか、これは御理解をいただきたいんですが、民主党発議者にお伺いします。地域立学校が目指している日本の子供たちの置かれる教育環境というのはどういう姿なのか、お示しください。 鈴木寛君お答え申し上げます。 今回、政府案と私どもの案でやっぱり基本的にコンセプトが違うということは何かといいますと、やっぱり依然として政府の案というのは、文部省の主導によるピラミッド型の、そしてその一番末端の現場としての学校があると、こういう構造はやはり引き続き踏襲しているのかなというふうに思います。 私たちは、やっぱり徹底した学習者主権といいますか子供本位、子供本位というのは決して子供の身勝手という意味ではございません、子供の人生トータルでその子供がより豊かな人生を過ごしていくための生きる力というものをきちっと身に付けていくということであります。正に子供を中心に、それを取り巻く非常に層の厚い、もちろんプロとしての教員、そして地域社会、そして家庭、さらには学生のボランティアというものが三百六十度温かく愛情で取り巻いて、そして子供の学びにとって最も望ましい学びの共同体、正にコミュニティーをつくっていくということを目指し、そのための制度設計をしているということでございます。 その中で、私どもがとりわけ重視をしておりますのは、今の教育で何が以前に比べて貧弱になってしまったかというと、これ斜めの関係でありまして、正に地域の社会のおじさん、おばさんとの関係とか、あるいは近所の、要するに兄弟が減りいとこが減るという中で、子供が悩みを打ち明けられたり、あるいはいろいろな進路の相談に乗ったりするという、そうした斜めの関係を再構築することによって子供たちに非常に取り巻く分厚い愛情の層をつくっていきたいと、そのための支援する枠組みをつくらしていただいているというのがコミュニティ・スクール、そして地域立学校推進の考え方でございまして、このことは既に五十校で極めてうまくいっております。そして、そのことを一挙に広めていこうではないかということが我々の立法姿勢でございます。 蓮舫君今回の参議院教育特別委員会で一連の大臣の答弁を通じて私が学んだことは、私が生まれていなかった時代、大臣が御答弁の中でせつな、せつな、その時代、時代にどういう教育の問題があって、どういうふうにクリアしていって、どういう時代背景だったのか学ばさせていただきました。是非大臣にはこの政府提出案の教育基本法の中でもっと重きを置いてもらいたいのは、今生まれて育つお子さん、これから生まれて育つお子さんが、情報化の時代の中で、環境が変わった中で、あるいは職業教育というのをあえて教えていかなければいけない時代で、もっと言えば、命ということを学校でまで教えなければいけないんだ。これは学校だけでは当然できない。家庭、地域、社会というものも出てくるんですが、どうぞその考え方を、私どもの法案にあるものを取り込んでいただいて、是非そこは修正する勇気を持っていただきたいと改めてお願いを申し上げ、私の質問に代えさせていただきます。 どうもありがとうございました。 中略 藤本祐司君大臣のおっしゃるのは、多分第一条、第二条のところでその辺りは担保できているじゃないかという、多分そういう御趣旨なのかなというふうには受け止められるんですが、民主党の方はここに職業教育という、そういう条項を設けておりますが、この職業教育というのを設けたその意図と、先ほど私が申し上げたそのギャップをどうするのかというところについてのお答えをいただければと思います。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私も藤本委員と同様の問題意識、特に民主党におきまして私は学力低下問題を一貫して調査あるいはそれの対応について取り組んでまいりました。 学力問題、確かに読解力が八番から十四番に下がってしまったということも問題でございますが、日本の教育現場における最大の問題は何かというと、学ぶ意欲の低下でございます。OECD各国の中で日本の子供たちの学ぶ意欲あるいは家庭などでの学習時間あるいは読書、そうしたことに対して最低の水準にあるということが私は最大の問題だというふうに思っております。私どもの日本国教育基本法案を考える上でも、このことを十分に憂慮しながら作成をさせていただきました。 じゃ、なぜ子供たちの学ぶ意欲がここまで低下してしまったのかということについては、今、藤本委員がおっしゃったことと私ども基本的に同じ認識を持っております。 では、どうしたらいいかということなわけでありますが、私どもは、前文におきまして新たな文明の創造を希求するということを言っております。正にそこは、今までは正に近代の時代でありまして、正に物質文明偏重主義、産業社会でありました。そこでは、正に富国強兵、GDP至上主義、経済・物質至上主義でございました。そこでの生きる力ということは経済的に富むということでありまして、経済的に富むということはどういうことかというと、大量生産、大量流通、大量消費社会の中で正に富を最大化していく能力ということが生きる力であったわけであります。 したがいまして、日本の戦後教育は、正に産業社会における生きる力であるGDPを最大化する、そのための工場労働者として非常に適した教育をやってまいったことによって、一九八〇年代に工業国家としては日本はジャパン・アズ・ナンバーワンと言われるように世界最高に達したわけであります。 じゃ、工業社会、産業社会における基本的な生きる力というのは暗記力と反復力でございまして、正に工場のベルトコンベヤーの中の分業の一翼を担う人間としてマニュアルを完璧に覚え、それを正確に高速に再現するという技術が非常にその工場の歩留りを上げ、その工場を持つ企業の一員であるということが人生においても幸福につながったと、こういうことでありました。 しかしながら、デジタル革命によりまして、大量に高速に反復するというのは人間の仕事ではなくて、デジタルテクノロジーにそこは取って代わられることになって、人間の仕事は正にゼロから一のオリジナリティーを、多くの人々と協力、協働をして、正に創造的で協働的、コラボレーションですね、要するに世の中に一つしかないものをつくり出すということが人間の仕事になりました。日本の教育は、いまだにこの時代の変化、価値観の変化、文明観の変化に対応していないというのが私どもの認識でございます。 したがいまして、前文におきましても、正にそうしたコミュニケーション、知恵、文化などのソフトパワー、これを目指す国、あるいはこれを担う国民として教育をしていくということが子供たちの生きる力を増進するということであり、そこは暗記力、反復力重視ではなくて、正にクリエーティブ・コラボレーティブ・アートワークと言っていますが、その一員として必要とされるコミュニケーション能力と真善美の判断能力を身に付けるということが学校教育のこれから目指すべき道だというふうに我々は判断をいたしております。 したがいまして、前文の中で「真理と正義を愛し、美しいものを美しいと感ずる心を育み、創造性に富んだ、人格の向上発展を目指す人間の育成」ということを盛り込みましたのも、正に真善美それぞれについての判断力を向上させるということを目指したものでありますし、それから、十七条の二項におきまして「文化的素養を醸成し、他者との対話、交流及び協働を促進する基礎となる国語力を身につけるための適切かつ最善な教育の機会を得られるよう奨励されるものとする。」と書きましたのは、正にコミュニケーション能力の強化というものを重視をしていく、このことは、特に世界で十四番に落ち込んでしまった読解力の向上ということとも符合するわけであります。 そのように、正に学校教育の中身、そのベースとなるコンセプト自体をこの際きちっと変えて、そしてそのことを学校教育法あるいは学習指導要領にこれから反映をさせていくことが必要だというふうに思っております。 加えまして、職業教育を十四条に盛り込みまして、正に学校教育それ自体が将来意味あるものにやっぱり変えていかなければならない。それが第一義的であり、そして将来の職業と学校教育というものをきちっと継ぎ目なくつなぎ合わせていくということが極めて重要なことだというふうに考えて、今回の条文を整理させていただいているということで御理解を賜りたいというふうに思っておりますが。 私どもは、私はたまたま原宿が地元でありますが、ここにはファッションとかお料理とかあるいはヘアデザインとか、大変に若くても一生懸命勉強して努力されて、世界に十代から活躍されている若い皆さんが一杯いらっしゃいます。したがいまして、そうしたこともきちっとその職業教育あるいは学校教育のスコープにむしろ入れていくということが重要だというふうに思っているところであります。 中略 藤本祐司君再度の繰り返しになろうかと思いますが、民主党の方には「情報文化社会に関する教育」という項目がございます。その意図と、私が今申し上げたことに対するお答えをいただければと思います。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 教育基本法というのは理念法であります。やっぱり、社会に対して重要なメッセージを発するという意味を持っているのが教育基本法だというふうに思っております。 そういう中で、先ほど来申し上げておりますように、学びの質というものが決定的に近代化のための教育をやっている時代とこれからの情報文化社会では違います。すなわち、今まで日本という国はこのキャッチアップということが極めて重要な国家及び社会、そして学校、教育の目標でございました。したがいまして、有益な情報は欧米にありと。したがって、英語教育も読解力中心であったというのは、いかに英語の文献を日本語に訳してそれをキャッチアップをするか。いい情報も悪い情報も基本的に枯渇をしていた、それをいかに入手をしていくかと、これが教育の大きな目標でありました。 しかし、これからは、いい情報も悪い情報も正に情報洪水、情報はんらんの中で生きていかなければいけない時代になったと。これは正に質的に極めて大きな転換だというふうに私どもは思っておりまして、したがって、これだけの時代の転換においては、教育の目指すべき理念、その基本的にある時代認識というのは決定的に質的に違っているので、この情報文化社会における教育ということにこれからなりますよというメッセージを教育基本法という宣言法の中で世の中に対して、そして教育現場に対して発することというのは非常に意味のあることだというふうに考えて、先ほど来の条項を盛り込まさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。 |