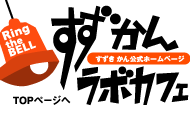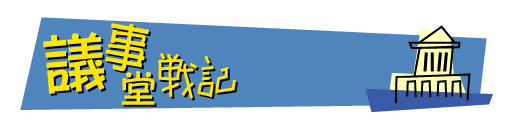2006年12月01日 教育基本法に関する特別委員会鈴木寛君参考人の先生方、本当に貴重な御意見、ありがとうございました。心から御礼を申し上げたいと思います。 まず杉谷参考人にお伺いをさせていただきたいと思いますが、先ほど時間が十分でなかったということもあって、少しはしょられたところもあろうかと思いますけれども、私どもは今、いじめ、まあいじめというのは昔からあったと思いますが、度を越したいじめ、そしてそのことを原因とする自殺という、本当にこれ戦後の教育の中でも極めて危機的な状況に今日ある。その中でこの教育基本法に関する特別委員会の審議を毎日させていただいているわけでありますが、そうした状況を改めて見ますに、やはりこの宗教教育といいますか、命を大切にする、これはもちろん他者の命もそうでありますし、そして自らの命も大切にすると、本当に大切にしなきゃいけないんだと、こういう思いを醸成していく上で、私ども、宗教教育を日本国教育基本法案の中で丁寧に勉強させていただいて、盛り込まさせていただいたんですが、その意義というものを改めて痛感をいたしているわけでありますが、その点につきまして杉谷参考人の御意見をいただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 参考人(杉谷義純君)ただいま宗教教育の意義と申しますか、いじめ問題等に象徴される命の問題、これ辺りも、命を大切にという道徳にちょっと毛が生えたような意識で、どうして命は大切なんだということに関しての導きがなかなかない。一方では、個を大切にするということは大変重要なところに据えられておりますけれども、個という、個人を大切にすれば、その自己決定権、自分の命の生殺与奪も自己決定権に属するのかどうかというようなことを一足飛びに行ってしまうと非常に危険な問題があろうかと。 そういうことで、宗教では、もちろんいろんな宗教の命のとらえ方がありますけれども、こういうとらえ方がありますと、仏教ではこのようにとらえている、キリスト教ではこうである、イスラム教ではこうだ、だからこそどれを選択するかは自由だけれども、実はどの宗教も命をこのように大切にしているというような導きの場、そこから一歩を踏み込むのは心の問題になりますけれども、そういう考える場を与える、そういう教育の場が今ないと。 そういうことで、悩んでいても壁にぶつかる、又は個の自由だということの、そういう言葉に誘導されて衝動的に命を粗末にしてしまう、そういうようなことがあろうかと思いますし、またこれは単に社会的な風潮の中で、非常に残虐な映画やいろんなことがあって、それに刺激されてということもあるかもしれませんけれども、それから残虐な犯罪ですね、それはいささか自分らと違う世界の人間であるというようなことは子供たち分かると思うんです。それよりも、例えば代理母の出産であるとか臓器の移植であるとか、いろんな科学技術の進歩の中で、命というものが十分議論されないままテクニックで新しい命が創造されたり、また転化されていったり、そういうような中で、命というのは一つの交換可能なものであろうかという、善意な中に命の軽さをいつの間にか受け取っていってしまう。 そういうことを考えますと、やはりこの宗教における命の問題、宗教教育の問題って非常に重要ではないかというように考えるわけでございます。 鈴木寛君ありがとうございます。 私どもも前文の中に、「祖先を敬い、子孫に想いをいたし、」というようなことを盛り込んでおります。正に若い命が失われるという現場、私たちもそこに直面をし、本当にその周りの家族はもとよりでありますが、友人そして教員、御縁のあった皆様方が本当に痛ましい思いにも駆られておられることを見てまいりました。 私どものころまでは、家に仏壇があり、神棚があり、あるいは盆踊りがあり、村祭りがありということで、日々の生活の中に宗教というものがある程度、何といいますか、普通に接することができたわけでありますが、やはり核家族化あるいは都市化という中で、地域社会もそうした子供たちの学びあるいははぐくみ、育ちの中でそうした機会が減ってきていると。そこをどうやって埋めていくかという中で、学校教育の現場の中にもそうした入口といいますか、きっかけといいますか、御縁といいますか、といったことが必要になってくるのかなという思いをしておりますが。 具体的には、逆に今、私立学校では既に宗教教育というものが行われていると思います。もちろん、私立学校で行われている宗教教育をそのまま公立学校に持ち込むということでは今後もないわけでありますけれども、私学における宗教教育実践というものがこういうふうに子供たちの成長に好影響を与えていると、そのことを参考にしながら、具体的に、例えば公教育の中で宗教教育をやっていくとすると、恐らく国民の皆様方は宗教教育を入れるということについてそんなに大きな反対は、まあ少なくとも私たちがお付き合いをしている方々はないわけであります。 また、諸外国を見ましても、イギリスではブレア首相なんかは四大宗教について全部教えると、こういうことになっておりますが、じゃ、この条項が入ると、例えばどういうようなことが今後行われていくと望ましいのかなということについての、少しイメージが共有をできたらなと思います。その点につきまして杉谷参考人、お話をいただければというふうに思います。 それから、山本参考人も家庭教育、生涯教育ということを言っておられますが、そういう観点から、今のようなことについて御意見があればいただければと思います。 参考人(杉谷義純君)まず、その前提として、公教育の場で宗教教育というと信教の自由、そのほか憲法の問題にも触れるんではないか。先ほど申し上げましたけれども、この精神がどういうところから出てきたかということを十分に踏まえませんと、その先誤りを犯す。 先ほど一神教のお話も出ました。信教の自由というのは、その国の国教以外、ほとんど国教に準ずるような宗教以外の宗教を信じている人も、その国教のような宗教を信じている人と同様な立場に置かれる。いわゆる不利益を被ってはならない、そういうようなことから出ているわけですね。 ところが、これが日本に入ってきますと、日本は非常に同一的な、民族の同一性が強い国ですから、しゃべる言葉も食べるものもほとんど同じ文化を共有しているわけで、宗教が違ってもそう違わない。そこで、いつの間にかこれ、宗教は特に触らない方がいいという意味じゃないかというようなふうに誤解をされてきた。そういう意味で、せっかく現行法にも多少宗教に触れておりますけれども、禁止規定もあることから公教育の場から締め出された。 さらに、最近は、いただきますとどこでも当たり前にしていることが、これはもう習俗に近いんですね。元をたどっていくと、まあこれは本当は元はインドの土着の宗教から、決して仏教のこれは専門ではありません。今は私も諸宗教で世界のいろんな宗教の方と付き合っておりますけれども、カトリックの牧師さんでも何でも合掌して迎えてくださいます。別にある特定宗教の風習でないんですけれども、手を合わせて、いただきますと言うことですら、それは特定宗教の形じゃないかと。だから、やっぱり給食の前にいただきますはやめましょうと。また、ある父兄からそれは特定な宗教の姿だからやめたらどうだと。それに対して校長先生がきちんと反論されないで、厄介なことは起きない方がいいから、まあこれはちょっと横へ置いとこうというようなことで、当然当たり前なことまで教育現場から締め出されている、これはやはり子供の心を荒らしていくんですね。 おかげさまで、これ、おかげさまって何となく言っていますけれども、目に見えない、いろいろな有縁無縁のお世話になりながら今日私たちがいる、人間存在そのものを確認をしている意味でもあるわけでございますが、そういうようなごくごく簡単な、日常かつて美風として行われていた習慣であることを、まず公教育の場で否定はしないで取り入れていただきたいというようなことから始まって、更に一歩。 単に、ちょっと時間長くなってしようがないんですが、歴史上、例えば奈良から、奈良仏教が堕落したから平安仏教、私、天台宗ですからすぐそんなことを言いますけど、そんなこととんでもない話なんですね、実は。これは政治的な見解なんです。例えば、江戸時代は後れていて駄目だというのが、最近の研究になって、江戸時代のあの寺子屋の学問水準があったから明治維新になってからもどんどん西洋文化を消化できて、一躍日本の文明が進んでいったということが分かってきたんです。奈良仏教もそうなんです。奈良の立派な仏教あるけど、更に今の時代には平安の天台宗、比叡山とか高野山、こういう仏教が大事だということで申請をして加わったんですね。ところが、歴史上は一つを悪くしないと面白くないものですから、それがだんだん普通の常識にこう敷衍して。 ですから、やはり歴史を教える上でも正しい宗教的な歴史、社会のついでにちょこっと教えるんでは、やはりそれでは足りないんですね。そういうことで、今までついでに国語の中でちょこっと教える何とかじゃなくて、宗教的な視点を持って、文化がなぜこういう立派な文化が華開いてきたか、そういう意味合いで取り入れれば、必ずしもだからそれを信仰しなさいというんでなくて、日本の文化を幅広く理解できる。そうすれば、世界に行っても、例えばイスラム教のこと知らなくてもばかにされないんです。イスラム教の人にも怒られない。だけど、あなたは仏教徒ですかとか、はいそうですと言ったら、仏教何ですかと、答えられなきゃばかにされる。宗教を持ってないといってばかにされる。 そういうことで、公教育の場ではもう少し宗教教育を改めていただければ有り難いと、このように思うわけです。 参考人(山本恒夫君)家庭教育とか生涯学習の方でどうかというお話でございましたけれども、私は、家庭教育の方に関してまず申し上げますと、やはり宗教ということをその知識として持ち込んでいっても、ほとんど受け止めてもらえないんだろうと。やっぱり人間の生き死にに関する根本的な問題だということで、やはり親の方がこれを受け止める。 例えば、今お話がありましたキリスト教は一神教と、子供のときから神との対峙というので、最初は何も分からないけれどもやってきた。その代わり、ある程度人間としての自覚ができるときになると本当に悩むわけですね、小説にもいろいろありますけれども。そういう中で無信教になる人もいれば、それからそれを更に信仰していく人もいる。そういうような人間の内面との対決みたいな、対峙みたいなものがあって初めて人間らしくなっていくんだと思いますから、そういう点でも家庭教育の中で宗教に関する中身のことを取り上げていく、親が自然にそういうことを取り上げていくという雰囲気は大事だと思います。 特に最近は、例えば小さい子供なんかですと、動物とかそういうものの死んだりするところって見たことがない。ですから、小学校なんかでもそうなんですけれども、ヤギを飼います。ヤギを飼って、農家の方は、子供が生まれるとヤギは子供をある程度独立させようとして突き殺すように突きますよと、だから離しなさいと言うけれども、先生も知らない、子供も知らない。ある朝行ってみたらヤギが死んでいた。死とは何だ、それで小学校二年生ぐらいが深刻なショックを受けてということがあるわけですね。そういうことも含めて宗教ということをしっかり考えていただきたい。 それから、政府の方の案では宗教に関する一般的な教養、一般的な教養というのが入っていますが、一般的な教養というのは一体何だということも真剣に検討してもらいたい。教養というのは生きる方法論ですよ。ですから、生きる方法論を身に付けるということ、ただ単に知識を身に付けるということではないと思うんですね。ですから、その辺のところをやはりこれからの教育では考え直していく必要があるんだろうと思っております。それは生涯学習ですね。 鈴木寛君ありがとうございます。 私どもも、生の意義と死の意味を考察し、命あるすべてのものを尊ぶ態度を養うということ、この生命に関する教育ということを重要だと思っておりますので、今の山本参考人のお話、非常に感銘をいたしました。 それから、杉谷参考人にもう一点確認なんですが、私どもの前文で、宗教と宗教の共生の精神といいますか、宗教協力といいますか、いろいろな多様な宗教をやっぱり認める姿勢というのは非常に重要だと思っておりますが、先ほどからそうしたことをおっしゃっておられますが、改めまして宗教の共生について、杉谷参考人は全日本仏教会であられると同時に、冒頭お話がございましたように、日本宗教連盟の方のこの宗教教育の御議論の中にも大変中心的な人物として加わっておられましたが、そのお考えを確認をさせていただきたいと思います。 参考人(杉谷義純君)今、大変、宗教戦争と言われているようなことは世界で起こっておりますが、一方では、歴史上も、先生方も宗教戦争という言葉をお習いになったと思うんですが、宗教戦争というふうな名前で呼ぶと非常に便利なんですね。日本は別にして海外におきまして、何教、何教、何派というと、あなたの宗教は何ですかというと、ああ、この人はこの国においてはどういう民族である、何語をしゃべって、どういうことだという、いわゆる戸籍調べみたいなことになるわけです。ですから、無宗教というと、どこに属しているか分からない、これはどうも怪しい人だということになるわけで、宗教というのは非常に大事な要素なんです。 しかしながら、なぜ宗教戦争が起こるかというと、その戦争が起きた原因を調べてみますと全部もう利害の対立なんですね。これは宗教がもとで起こったんではないと。起こった後に、仲間を糾合して相手を倒すために、意識統一をするために宗教が利用される。これは利用される宗教者も悪いですし、また利用する方も便利だから利用するわけです。そういうことでございまして、本来、宗教はお互いに話し合う余地がある。 そういうようなことで、一九六〇年代から宗教対話ということが非常に世界の流れになりまして、バチカンにおいてもキリスト教以外の宗教が神が認めたと、これが気に入らないんですね。仏教は神様に認められなくてもあるかもしれませんが、まあ一応それぞれ自分の理解で相手を理解するのは当然でございますから、そういうことで、またイスラムも、ムスリムといいますが、穏健な方々は理解をします。 ただ、イスラムにおいて結局ああいうテロとかジハードとか、ジハードもこれは本来は向上するという意味でございますけれども、万やむを得ず自分がおとしめられるときには仕方がないと、非常にそういうところまで追い込まれるというような悲惨な状況があるわけです。そういう意味で、やはり他宗教に対する寛容の姿勢というもの、また、理解をする姿勢、これは最も私は重要だと思うんです。 それで、またちょっと手前みそになるんですが、分かりやすい例として、例えば比叡山を開いた伝教大師最澄という方は、一目の羅、鳥を得るにあたわずと。一つの網の目、かすみ網を想像してください、一つの網の目では鳥は捕れない、だからかすみ網のように網はつながっていなきゃならない。それと同じように、一つの宗教だけでは御縁ものですからすべての人を救えない、だから奈良仏教のほかに天台の仏教も必要だということで願い出たんですね。ところが、その最澄上人が学んだ天台大師という方の本に、一目、一つの網で鳥は捕れないけれども、捕ってみれば一つの網だというんです。だから、宗教は協力するけれども、シュンクレティズムって、全部教義をごちゃごちゃにするんでなくて協力をしながら人をそれぞれすくい取るのは、やっぱり見てみると鳥が一つの網に引っ掛かっているように、それぞれの宗教であるという言葉があるんですね。 これは、正にこの宗教教育においても、その網の目にとらえるまで教育するんじゃないですね。網を張る宗教がありますよ、皆さんの人生を全うするためにいろいろな道がありますよということを選択する知識を与える、またその意義を教えると。これが非常に重要でありますけれども、自分の宗教でなければ駄目だというようなことでは、これはあってはならない。 例えば、ブッシュさんがキリストに勝利を願い、フセインさんがアラーの神に祈って戦争をしましたけれども、そういうような短絡的な選び方ですと、今のような非常な混乱が招くという一つの教訓ではないかと、このように思います。 鈴木寛君小川参考人にお尋ねをいたします。 私も正に参考人同士で教育基本問題調査会のようなところでどんどんけんけんがくがくやっていただきたいというふうに従来から提案をいたしておりますが、先ほど成嶋参考人から不当な支配をめぐって民主党案は与党案よりなお悪いというお話がございました。それについてどう思われるかということと、それから馬居参考人から、心ではなくて態度にとどめたことがより望ましいというお話がございましたが、それについての御意見を承りたいと思います。 参考人(小川義男君)後の方からお答えしますと、心と態度というものは、私は騒ぐほど大きな違いでないと。教育はすべて心に及ぶものです。例えば、老人を大切にしましょうとか、友達をいたわりましょうというのは、態度の育成の問題ではなくて心の問題です。心なきところに態度の育成など出てきません。その意味では、民主党案と自民党案で、その間に万里の長城できるぐらいどうにもならぬ違いではないと私は理解しております。 ただ、あえて心をそれほど恐れるという辺りに、我が国のいろいろな悲しい歴史も、この六十年以前にあった歴史に対する政治家の一部の方の憂慮があるので、これに対しては敬意を持たねばならないと私は思うんですね。国民主権の原理での国家というのは実は国民なんですね。その辺りを考えて、そんなに心配しないでずばり心で大丈夫ですと。その点が両案にそれほどの違いがないと思いますのと、何より民主党案の方が政府原案より文章が美しい。私は学校の先生なものですから、その点で美しい法文にしてもらった方がいいと、こういうことですね。 それから、不当な支配の問題は、民主的教育とは何かと。一つの学校における教師の多数意思による学校運営ではなくて、国民全体が求めるような内容の教育を推進すること、これが民主的教育であると。あるブランチ、ブランチにおける自治、これが直ちにデモクラシーだというのではなくて、民主的教育というのは、ある町、ある地域における、ある学校におけるそのときの影響力を持つ人たちの多数意思ではなくて、そうではなくて、国民全体の意思で大まかなところは決めておくと。 大綱的基準というのは、今日、私の見解と反対の参考人の先生も大綱的基準ということをおっしゃる。ただ、そこで言う大綱的基準というのは、恐らく教育の内的事項にかかわることは含めてはならないと、こういうふうに言っているのだろうと思いますね。その点で、この大綱的基準の何たるかをめぐって争いが起こると。この辺りは民主党さんの案がどのようにお考えか、私は見解を述べておりませんけれども、要するに国民全体で教育の自主性、創造性を圧迫しない、そういう辺りに配慮した規範というものを設けるということは民主的教育の推進という上では必要だと。現行学習指導要領はその域を脱しているものではない。この辺りを教育基本法改正案の中でも残しておいた方がいいだろうと思っております。 鈴木寛君世取山参考人にお伺いをいたします。 子どもの権利条約のお話、非常に私も感銘をいたしました。民主党案では、実は、子どもの権利条約の二条、十七条、十八条、二十三条、二十八条、二十九条を参照、大いにした条文をそれぞれ盛り込まさせていただいております。子どもの権利条約は九四年に日本は批准をしておりますので、そういう意味でいえば、この際、今教育基本法が議論になっているときに、そうしたことも参考にしながら、あるいは私どもが従来から申し上げております国連の人権規約の十三条の二項の(C)、高等教育の漸進的無償化条項、こういう国際、あるいはユネスコ条約とかいろいろありますけれども、こうしたことをやはりきちっと国内の憲法に準ずる教育基本法で盛り込んでおく意義というのはあるんじゃないかというふうに思っているんですが、その点いかがでございましょうか。 参考人(世取山洋介君)まず、教育基本法が基本法たり得る理由はどこにあるのかというお話をしたいんですけれども、それは、憲法に順接して、なおかつ憲法と同じぐらい重要な権利を書き込んであるから基本法は基本法であるわけですね。 したがって、新しい基本法を作るというのであれば、憲法より下位にありますけれども、下位法を無効にする力を持つ国際人権法の原則を書き込むというのが筋だというふうに私は思っていますし、正直言って政府案の方はそういう配慮がなくて、憲法の原則とは無関係な、あるいはそれと逆接する原則を書き込んでおりますので、でき上がった後、本当に基本法としての力を持たしていいのかどうかというのは今から悩んでいるところです。 民主党案は、確かに国際人権条約を反映させている点において評価できます。それは民主党案のいいところだというふうに私は率直に思っていますが、ただ、書き込みが弱いのは、やはり条約の十二条の意見表明権です。意見表明権について、子供に意見自由に言わせて何させるつもりだというふうにおっしゃられる方も多いんですけれども、これはそういう問題ではなくて、むしろ子供が、うんと俗な言い方をしますけれども、親に対して必ずねえねえと言ってくるわけですよね。あるいは、先生に対してねえねえ、話聞いて。多分、それが先ほど小川参考人が言った好かれるということの本質だと思うんですけれども。 そういう、ねえねえというふうに子供が自由に言えて、先生がなあにというふうにして聞けると、そういう関係を学校教育の中にきちんとつくるんだということを、民主党案がどこまで考えているのか、あるいは気付かなかったのかもしれませんし、あえて排除しているのかもしれませんし、それは分かりません。ただ、どうせやるので、どうも済みません、変な言い方で、国際人権条約の原則を反映させるのであれば、まだまだ反映させるところはあるし、民主党案を発展させて、また次なる国会でまた二つの案が対決する構図が生まれれば本当にいいなと思います。 鈴木寛君ありがとうございました。 |