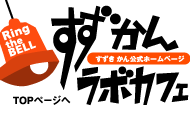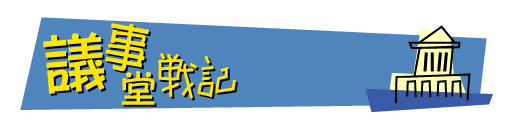2006年11月30日 教育基本法に関する特別委員会鈴木寛君おはようございます。安倍総理におかれましては、大変お忙しい中、よろしくお願い申し上げます。 今日は総理も御出席の下、いじめの問題あるいはタウンミーティングの問題、そして日本の教育行政の在り方ということを議論をしていくと、こういうテーマでこの委員会が設定されたわけでございますけれども、参議院で連日のように、伊吹大臣、塩崎大臣、高市大臣に御出席いただいて、非常に私、率直に申し上げまして、かみ合った議論が、参議院ならではの御議論をさせていただいているなということを思っております。 それで、任命権者の安倍総理に是非御礼を申し上げたいと思いますが、伊吹大臣は本当にすばらしい文部科学大臣でいらっしゃるということを野党の私からも申し上げたいと思います。 と申しますのは、本当に今のこの教育行政に精通されているということと、やはり文部官僚に対してきちっと御指導をされながらこの審議に臨んでいただいているというのは、やはり教育基本法を、(発言する者あり)これは決してやらせではございませんが、やっぱり論ずべき国会、これはやっぱり五十年、六十年後に後世の方々が振り返って、あのときどういう議論があったのかと。と申しますのも、我々も五十年、六十年前の田中耕太郎先生とかの議事録を読んでこれに臨んでいるわけでありますから、同じことが恐らく、今後何十年後に改正されるのか分かりませんけれども、そのときに堪え得る議論をしたいということで臨んでまいりました。 そういう中で、やはりこの参議院で、本当に後世の方々にいい議論だったと、いい議論はさせていただいたと、多分。このことをきちっとやっぱり法案にも反映をさせて、そしてここから教育基本法を、新しい教育基本法を第一歩として教育行政が立て直り、あるいは教育財政にもっともっと重点が置かれという、明らかにあそこが日本の教育のターニングポイントだったと、あそこからV字反転をしたと、こういうやはり法案に私はしていきたい、そのことに総理も是非リーダーシップを取っていただきたいと、このようにお願いを申し上げたいというふうに思います。 冒頭、総理にお願い、御質問を申し上げますが、正にいじめの問題で、あるいは不登校の問題で、あるいは引きこもりの問題で大変に困っておられる、もちろん御本人、そして御家族、いらっしゃるわけでありますけれども、この生徒さん、児童さん、そして御家族、保護者の皆様方に、確かに今大変な状況にあると、しかし政府が、あるいは国会が、あるいは政治家が、このように具体的に対応するのでこれから明るい兆しが、明るい方向に大きな第一歩を踏み出しますよと、こういうメッセージを具体的に総理の自ら発していただきたいというふうに思いますが、お願いを申し上げます。 内閣総理大臣(安倍晋三君)ただいま鈴木委員が御指摘になられましたいじめの問題、またいじめに関しての不登校、またいじめにかかわりなく不登校に悩んでおられる親御さんもおられるんだろうと思います。特にいじめの問題につきましては、いじめを苦にして子供たちが命を、自らの命を絶っているという極めて深刻な問題が起こっています。この問題が連鎖として引き続き何人かの子供が自分自身の手で自らの命を絶っていく、これは何としても食い止めなければならないと考えております。 そこで、まずは、政府は政府として、学校は学校現場として、あるいは教育委員会は教育委員会として、そしてまた地域や家庭はそれぞれ今すぐできることに取り掛からなければならないと考えております。 政府としては、まずは学校現場に対する指導を強めております。この指導において、いじめをなくしていくために徹底的な指導を行うように、学校のホームルーム等を通じて徹底していくようにということも含めて学校現場の指導を行っています。 そしてまた、問題を抱えている子供たちあるいは親御さんたちが相談できるいじめ一一〇番など相談体制について、今まで以上に利用しやすいシステムにしていかなければならない、また相談する側に立って考えなければならないと思います。前の委員会で御指摘があった相談できる時間の問題もあるだろうと思います。そしてまた、対応できる体制の問題もあると思います。この新しい、悩んでいる子供たちに対応できる仕組みを構築すべく、今作業に当たらさせているところでございます。 また、私が主宰をしております教育再生会議におきましても、有識者委員より、昨日、緊急提言が出されました。 この提言におきましては、先ほど私が申し上げましたように、社会総掛かりでこの問題に対応していく必要があるだろうということが指摘されております。学校は、いじめは絶対に許さず、見て見ぬふりをする者も加害者であることを徹底して指導するようにということが言われているわけでありますが、これはやはり、いじめる側といじめられている被害者である生徒、しかしその他大勢の人たちは見ているではないか、そういう子供たちが勇気を持って一人でも二人でも声を上げれば止めることができるということを強く訴えているわけでございます。 そしてまた、問題を起こす子供に対しては、指導、懲戒の基準を明確にして、毅然たる対応を取っていく必要があるということも指摘をしているわけでありまして、いじめられている子供が転校を余儀なくされるというのは、これはやはり私はおかしいんだろうと思います。いじめている子供たちに対しても、もちろん教育的に指導をしていくことが大切です。しかし、直ちにいじめをやめるべく厳しく指導していく、それもやはり私は大切ではないか。また、先生にとってもそういう厳しい指導をすることもできるということでなければ、なかなか問題の解決は私は難しいのではないかと思います。 また、いじめられている子供には、守ってくれる人、その子を必要とする人が必ずいることを伝えて、教員は子供のサインを見逃さないよう緊密なコミュニケーションを図るようにするということを、これも言っているわけでございまして、必ず悩んでいる子供はサインを発していて、まあ、なかなかそれはしかしそのサインを受け止めるのは難しいという、そういう指摘もあるわけでありますが、そのサインをとにかく学校現場において見逃さないように、また家庭において見逃さないようにしていこうということでございます。 また、もちろんいじめを放置をしたり助長した教員には、これは懲戒処分を適用するということで臨まなければならないと思います。 また、学校はいじめを隠すことなく、いじめがあった場合には対応チームを編成するなどにより、家庭や地域と一体となって解決に取り組んでいく。 こうした五点に、主に五点について対応策を示しているわけであります。 政府といたしましても、この緊急提言を踏まえまして、道徳教育等を通じた規範意識を醸成をしていく、子供の悩みや不安を受け止めるスクールカウンセラーの充実や学校外の様々な相談窓口等を周知をしていく、そしてまた学校、家庭、地域が連携したいじめの未然防止の取組、それを推進をしていかなければならないと考えております。 いずれにいたしましても、我々、すぐにできることは、そういうものに対して取り掛かっていかなければならない、何としてもこのいじめによる子供の自殺の連鎖は食い止めなければならないという決意で取り組んでまいりたいと思います。 鈴木寛君私は政治家という言葉と議員という言葉を時々意識して、もちろん議員というのは政治家の部分集合でありますが、ただ申し上げたいのは、例えば西郷隆盛とか坂本龍馬というのは、これ大政治家でありますけれども議員ではございません。伊藤博文とか山県有朋は、これは議員でもあったとは思いますが、政治家というのは、世の中のために、より良くしよう、良い社会をつくろう、良い国をつくろうと頑張っておられる方、これはすべて私は政治家だと思うんですね。 この国にも在野に大変立派な、NPO活動とか、いろいろな活動をされている政治家も一杯いらっしゃると思いますが、我々議員でしかできない仕事というのがあると思っております。それは何かといいますと、二つ、ぎりぎり詰めていくとですね、議員でしかできない、議員たる政治家でしかできない仕事というのは、これは一つやっぱり法律を作るということと、それから、税金を集めて、そしてそれをきちっと使っていく、正にそういう意味での歳入歳出を含めた予算というものをつくっていくこと、大きく言うとこの二つは我々議員に独占的に信託をされているこれは使命、職務だと私は認識をいたしております。 総理の今のいじめに対するいろいろなお取組あるいは教育再生会議のメッセージ、これ、いずれももちろんきちっとやっていただきたいというふうに思いますし、そのメッセージを発せられたことは、これはもちろん大いに結構なことだと思いますけれども、正に、我々は、どういうやっぱりいい制度、あるいはいい、それを実施する法律を作るか、あるいはそれを具体化する予算をつくるかと、やっぱりここがきちっと問われているんだと思います。 それで、私たちも、そしてもちろん政府の皆様方も、どうしてこういういじめの問題あるいは未履修の問題あるいは教育現場のこうした問題が続発をしているのかという、そのいろんな要因、あるいはそれを再発を防止する、あるいはそれをもっともっと改善に転じていく。 ここで、一つ大きなキーワードとして、この間の議論を通じて浮かび上がってきたのは、やはり地方教育行政に携わる方々のこの感度といいますか感性といいますか、それがいささか問題であるケースがやっぱり多いなあという認識がかなり浮き彫りになってきております。少なくとも私たちはそういうふうに思っております。 これ、今大変でございますから、メッセージも出ますから、恐らくこの数か月間といいますか、まあほとぼりが冷めるまでは各学校現場も緊張して、しかしまた元のもくあみになってしまっては絶対いけないわけでありまして、そのためには、そうした地方教育行政に携わる皆様方の行動様式を変えるような、より感度を持って、そしてより児童や、あるいは生徒や、あるいはその保護者の立場になって親身に愛情を注いで教育行政あるいは教育現場に当たっていただくような行動様式が奨励をされて、そうしたことに対して不作為であったりあるいは怠慢であったりするそうした行動様式が戒められるというような制度設計をする必要があるんではないかと、こういう議論になってきているわけでございます。 私どもは、そもそもこれは、今の教育基本法ができたときもそうでありますが、今の教育基本法ができたときは、教育基本法と学校教育法というものが、これは同時に公布され施行されて、そして速やかに新しい学制が導入をされたわけであります。そして、その翌年には教育委員会法というものを施行されて、そして今日の原型であります、もちろん教育委員会法は後に、一九五六年に地方教育行政法ということで変わりますけれども、そうした体制が整備されて今日に至っているわけであります。 当然、今回の、正に大改革でありますから、六十年ぶりの大改革でありますから、新しい教育基本法が作り直されて、私どもも作り直したいと思っていますから新法を出しています。そうすると、当然、それに伴って学校教育法とか地方教育行政法の今の良いところは残しつつも、きちっと新しい改革案に対応した制度設計も同時になされるということが当然に想定をされているわけであります。 私どもは、学校教育法はどこを変えなきゃいけないかという認識を持っているかといいますと、現行の教育基本法は義務教育年限を九年ということを教育基本法で明記してあります。そこを、今後は六三三制をいろいろな形で、小学校の高学年と中学校を合体するとか、いろんな議論があります。こういう議論を経て、もっとフレキシブルにしていこう、もっといろいろな多様な教育体系を実現を可能にしていこうということで、教育基本法で九年ということを決まっていたのを、学校教育法にその九年をゆだねて、学教法でもってその六三三制の次のスタイルというものは変更できるような制度設計にしています。 この点については、そういうふうな学教法でその時々の学制、六三三制に対応する学制というものを変えられるようにということだけ今回決めて、じゃ、それをどういうふうにしていったらいいのかというのは、これは一年、二年きちっと議論をしながら学教法を変えると、こういうことを附則で書いているわけでありまして、それ以外の現行の学校教育法、要するに初中等教育、高等教育、あるいはその学校種の区分ですね、高等教育にはどういうものがあるかとか、ここは現状でいいのではないかと、その組合せ論についてはいろいろあろうかと思います。しかし、ここはそんなに喫緊ではないと、むしろ充実した議論が必要だということで、学教法については附則対応と、こういうことになっています。 しかし、地方教育行政法については、今申し上げましたように、地方の教育行政に携わる方々の行動様式というのは、これは速やかに変える必要があるという認識と、それから教育委員会というのが、今の一九五六年以降の地教行法の中で五十年たって、いわゆる教育長というのはこれは役人でありますが、教育長のやることのその上側に教育委員会というものがあるわけでありますが、そこが形骸化してしまうことによって責任の所在が非常にあいまいになってしまっている。あるいは、教育委員会自体がもちろん非常勤でもありますし、それからその実態がかなりやはり形骸化している、あるいはこのような、いじめのような大緊急事態が起こっても、教育委員会が機能して、機能して何か具体的な予防措置とか、あるいはそれに対する速やかな緊急措置が行われたという形跡もないということで、やはりこの教育委員会制度というのは早急に抜本的に変更する必要がある、教育長の隠れみのとして悪用されている運用を直す必要があると、この認識まではこの参議院の議論でかなり深まりつつあるんですね。 そこからなんですけれども、私どもはその認識に立って一つの案を、一つの案を提示させていただいております。これは非常に案の作り方というのは難しい。やっぱり、ある制度というのは、非常にいい点もあれば、それに伴う副作用といいますか、これはどんな制度設計でもそうだと思います。私どもは、いろいろ党内でも悩みながら、そしていろんな有識者の皆様方とも議論を重ねながら、今回参議院におきましては新地方教育行政法と、それから財政に関する教育振興法というものをお出ししたわけですね。 私どもは政府に是非、私どもは新教育行政法というのを出しましたと。もちろん一長一短ありますけれども、私どもとしてはもちろん最善と思って出していますけれども、是非政府も、その問題認識は大体共有しましたから、それに対する、民主党に対する対案を出してくださいということを与党にお願いするというのは非常にねじれているわけでありますが、それはおいといて、それを両方出して、そして正にその弁証法的プロセスの中でいいものを作っていこうではありませんかということを文部科学大臣にお願いをしているところでございます。 もう文部科学大臣は、いろいろお気持ちは出したいようなことはかなり以心伝心で伝わってくるわけでありますが、これは、申し上げたいことは、これは教育基本法が国会に提出されたのは総理が官房長官のときの四月でございます。今はもう十一月も終わりに来ようとしている。もう七か月たっているんですね、七か月たっているんです。私たちも五月二十三日に提出したときは間に合いませんでした、率直に申し上げまして。それから、しかし、これはやっぱりパッケージで国民の皆様方にお示しをする、特に教育行政と教育財政が日本の問題であるから、そこをきちっとお示しをしなければいかぬということで、徹夜に次ぐ徹夜で出しました。 ここを是非出していただきたい。少なくとも要綱でも、あるいは今政府の中の御議論でも、議論の材料を出していただきたいというふうにお願いを申し上げてきているわけでございますが、そこにまだ出てきていないという厳然たる事実がございますので、是非そこは総理の再度のリーダーシップを発揮していただきたいということをお願いを申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)総理からお答えいたしますが、私が出したいというような意図を持っているということをおっしゃったんで、ちょっとその前に答弁をさせていただきます。 衆議院段階では残念ながらこの法案が出ませんでしたが、民主党が参議院でこの法案をお出しになった見識には私は高く敬意を表したいと思います。 そして、教育委員会の在り方、強化、強化というのか改組というのか、民主党案では教育委員会の最終的な廃止という案になっていますが、これは先生がおっしゃったように一長一短あります。 もう一つ、やっぱり大きな抜けていることは、国が最終責任を持つという民主党案の中で、どういう形で国が最終責任を持つかということを担保するかということですね。ここは我々も非常に悩んでいるところです。そして、民主党さんは今、行政権を持っておられませんから、野党ですから、だからそれは対案はお示しになりやすいんですよ。しかし、我々は行政権を持っておりますからね、この教育基本法は理念法としてはよろしいんですけれども、先生の御意見も伺い、そして国会の御意見も伺い、そしておっしゃったように、ある改革をしようとすれば一長一短ありますから、特に国がどのように関与していくかということについては、これはいろいろな意見がございますから、だから広く国民の意見を伺って、そして作らねばならないと。 我々は我々なりの省内で検討はいたしております。しかし、これはあくまで文部科学省として検討したものであって、総理はまだ当然、御報告もしておりませんし、御存じありません。つまり、行政権を預かっている立場というのはそれほど慎重であるべきだということなんです。必ず、それは国会の御議論を、この基本法についての御議論を伺った上で、それをしんしゃくしてやらなければ何のために審議をしているか分かりませんから、しんしゃくをして各法を改正案としてお出しになったときは、必ず先生が御審議に参加をされて御意見をおっしゃるわけですから、やはり野党という立場と行政権をあずかっている与党・政府という立場は少し違うと。 だから、私が出したいと思っているというのはちょっとね、個人としてはいろいろ気持ちはありますが、内閣の一員としては、今のような印象をお持ちいただくことはちょっと困るということでございます。 内閣総理大臣(安倍晋三君)この教育委員会については、教育委員会を設立した当初の目的としては、まず政治的な中立性、そして安定性、継続性、そしてさらには多様な国民の意見を取り入れていく、言わば普通の人たちに入っていただこう、一部の専門家が独占するあるいは一部の関係者が独占するのではなくて、多様な国民の御意見を反映させようという趣旨でこの教育委員会ができたということであろうと、このように思うわけであります。 しかし、昨今の未履修、またいじめの問題等に対する対応を見ても、それは確かに鈴木委員が御指摘になった問題点があります。我々はそもそも、この骨太の方針において抜本的な教育委員会の改革を目指しているということはもう既に示しているわけでありますが、やはり改革をすべきだという方向は正しかったということがある意味裏打ちされてしまったわけでございますが。 今後、いかにチェック機能を十分に生かしていくのか、もちろん政治的な中立性を担保していかなければいけませんが、チェック機能をどう生かしていくのか。あるいは、高い使命感をこの教育委員会の方々に持っていただかなければならない。その中で、本当に多様な意見を反映させ、国民の意見を反映させるものでもなければならないということでございまして、この教育委員会の在り方については抜本的なこれは、この改革が必要であると。 その論点については、確かにこの委員会の場においても深まってきてだんだん一致点も見えてきたと、このように思うわけでありますが、それを直ちに今すぐこの国会で出せと、これをこう言われても、なかなかそれはまだ準備の点で難しいところもありますし、正に今、教育再生会議においてもこの教育基本法の成立を前提にこの議論もしていただいているわけでございまして、これは何とか我々としても、多くの国民の御議論また御意見を承りながら、この教育基本法を成立をさせた後に成案を得たいと、こう考えているところでございます。 また、国と教育委員会との関与の在り方等についても、これも従来より伊吹大臣からも問題点が指摘されているところでありますが、それも踏まえながら、あるべき教育委員会の在り方について法律で定めていきたいと思います。 鈴木寛君今総理もおっしゃったように、これは内閣官房でも大分議論詰まっているんですよね。もちろん文部省も今まで議論をされているんです。 ですから、大体はその論点というか、何が、一長一短って言いましたけれども、それぞれの制度の長と短というのはもう分かっていまして、もう最後は、何といいますか、比較考量と、それから、あとはこの今のいろんな事態を、どれだけの緊急性を、あるいはこの緊迫した状況を責任を持ってきちっと政治が判断をするかという決めの問題だと私は思うんですね。ですから、総理がどこかで期限を切っていただいて、やっぱりここまでに出すんだと。 要するに、新しい教育の理念は出されています。我々も理念を出しています。しかし、根幹となる、幹となるやっぱり制度の青写真については、これ出していただくということがやっぱり分かりやすい、国民の皆様方に。国民の皆様は、この教育基本法の議論によって現場がどう変わるのか分からないという声がやっぱり圧倒的なんですよ。それは我々もそういうことを聞きましたので、今回参議院で出しているというのはこういうことなんですね。そこは是非、総理のやっぱりリーダーシップを発揮していただいて、そしてもうとにかくここまでに出そうと。もちろん、全部決め切れない部分ありますから、ここはじゃあ様子を見よう、しかし根幹のところはここだという、何にも今出てきていないものですから、ここは再三再四私からお願いをさせていただいているということであります。 それで、その制度設計のときに国会での議論をしんしゃくしてということでありますので申し上げますと、結局、我々もいろいろ考えました。最終的にだれの立場に立つのか、だれの代弁者に立つのかということが、このいろいろ一長一短あるいろんな制度設計の中で決めるポイントだなという我々は結論に達したんです。 すなわち、どういうことかといいますと、私どもはやっぱり徹底的に、いじめ問題で悩んでいる、困っている本人、そしてその保護者の立場に立ったときに、その不安をどこに相談に行ったらいいんだろうか、あるいはその不安が解消されないときにどうしたらいいんだろうかということで、まずは学校ですよね。学校で校長先生に話が通ってないときには、学校理事会というものをつくれば、そこにその保護者の心配事は持っていくことができる。そうすると、学校がもう少し動きやすく、迅速に動きやすくなるかもしれない。そして、それでなお難しい場合には、今は人事権、任命権というのは県の教育委員会にあります、そして、非常勤の教育長さんになかなかその思いというのは伝えづらい。であれば、一番身近なところにある市町村長に任命権を移して、そして市会議員さんとかなんとかを頼めばその不安というものは届くかもしれない。今遠いところにあるそうしたものをなるべく身近なところに寄せていこうという制度設計です。 当然、それについては政治的中立性の問題等ありますから、教育委員会を教育監査委員会ということにして、それは選挙管理委員会と同じような公正な手続で人選をして、一党一派に属しない、過半数以上がという条項も入れています。そういうことによって短のところをなるべく最小化するという案をお持ちをしているわけです。 これは、ひとえにその御本人、家族の立場に立ってみるとこれがいい制度だと。もちろんそれに伴う、もちろんいろいろな副作用というものは想定し得ます。であれば、それについてのいろんな御指摘もあっていい、その点には分かるんですけれども、じゃあどうしたらいいんですかというところで止まってしまっているわけですね、この議論が。 なので総理に、先ほど文部科学大臣が、文部省だけでは決められません、それはおっしゃるとおりだと思います。だから、そうした緩慢な文部省を見かねて教育再生会議を総理がリーダーシップでおつくりになった、これも私は大変評価いたします。であれば、教育再生会議できちっとそうした新しい教育行政制度のあるべき姿というものについてやっぱりお示しをいただきたい。いつまでに、まずいじめについてはメッセージ出ました、じゃ次、教育委員会の問題が問題だと、じゃこれについてはいついつまでに早急にまず前倒しでやってくれという、こういう総理指示をお出しになって、それまで我々待っていますから、出るまで、きちっと。出たらもう速やかに審議を再開させていただいて、そして議論をぐわっと深化させる思いはもう十分ございます。 それから、私どもは、今回、命の問題がやっぱり問われています。民主党のこの十六条では「生の意義と死の意味を考察し、生命あるすべてのものを尊ぶ態度を養う」ということを入れているというのは、やっぱりこういう事態に対してきちっとこたえていかなきゃいけない。あるいは、携帯メールがいじめの原因です。だから、今回いろいろある中でインターネットの条項を入れています、十七条です。それから、先ほど申し上げましたように、理事会制度というのを投入しているというのは、こういう先ほどの本当に困った保護者の声をどうやって受け止めるか、学校が。そして、これは文部科学大臣からもお話がありましたが、やっぱり国の最終責任というのは大事だということで七条に盛り込んでいる。 というような、そういう観点から私どもは、民主党日本国教育基本法案を始めとする教育財政、教育行政に関する根幹法をお示しをいたしておりますので、これを踏まえて文部科学大臣に修正しませんかと言うと、これは自民党あるいは公明党を含む議会の問題だとおっしゃいます。それもおっしゃるとおりだと思っております。 自民党総裁としてお尋ねを申し上げますが、そうした、我々も案を持ち寄っていますので、真摯な議論をきちっとするように自民党総裁として自民党員の皆様方に御指示をしていただきたいと思いますが、自民党総裁としての御所見を伺いたいと思います。 内閣総理大臣(安倍晋三君)民主党が対案、その対案については私どもは私どもの考え方がございますが、この場に対案をお示しになられたことは評価をしたいと、このように思います。私どもの案と民主党の案を国民の皆様の目の前に出して、どちらが優れているかという議論をすることが私は建設的な議論にもつながってまいりますし、国民にとってもこれは分かりやすい議論であろうと、このように思うわけでございます。 政府としては、お出しした以上、私どもが自信を持って提出をしておりますので、速やかな成立を図っていただきたいと、このように思います。 その上で、この委員会において、どうした、どういう形で協議を行っていくかということについては、これは正に委員の、この目の前に座っておられる現場の委員の皆様、理事を始め委員の皆様に私はお任せをいたしております。 私は、他方、もちろん総理であると同時に自由民主党の総裁という立場がございますが、ここで答弁に立っておりますのは正に総理大臣として、行政府の長として立っておりますので、議会運営のことについて私がここで申し上げるのは不適切ではないかと思いますが、基本的にはこれは現場のこの委員の皆様にお任せをいたしておるところでございます。 鈴木寛君終わります。ありがとうございました。 |