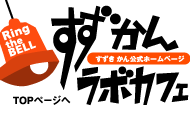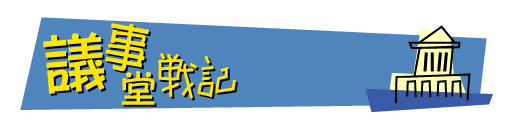2006年11月28日 教育基本法に関する特別委員会浅尾慶一郎君民主党・新緑風会の浅尾慶一郎です。 今日は教育基本法の改正案につきまして条文ごとにいろいろと質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、最初に総論として、これまでいろいろと議論が出てきております直近の課題で、いじめ・自殺問題について一、二点伺わさせていただきます。 来年度、いじめの実態調査を全国的に行うということを聞いておりますけれども、いじめといじめによる自殺、それぞれの定義をまず教えていただけますでしょうか。まず、文科省がとらえているいじめとは何か、いじめによる自殺は何かということの定義を伺いたいと思います。 国務大臣(伊吹文明君)これはもう是非、理事会の御決定ですから私が御答弁いたしますが、事実関係とかこういうことは私が必ずしもすべてをつまびらかにしているわけではございませんので、その点は御了承をいただきたいと思います。 まず先生、いじめの定義をまずやらなくちゃいけませんね。 文科省のいじめの定義というのは、自分より弱い者に対し一方的に身体的、心理的な攻撃を継続的に加え相手が深刻な苦痛を感じているものとして、個々の行為がいじめに当たるかどうかということを判断をしてもらいたいと。そして、表面的、形式的に行うんではなくて、いじめられていると訴えている子供の立場に立っていじめかどうかを判断してもらいたいということを文部科学省の定義として各教育委員会に調査をお願いしているということです。 それから、自殺については、調査時点で学校が把握している自殺の主な理由の一つを報告させる方式を取っているわけで、自殺というのはもういろいろな心理的要因が重なって自殺に追い込まれるわけですから、その大きな理由として自殺に追い込まれたのがいじめであるという場合は、選択肢の一つとしていじめがあるということを報告してくださいということを申し上げているわけです。 浅尾慶一郎君ありがとうございます。 一応申し上げておきますと、事前の質問通告段階で、まあいつものことなんですが、政府参考人は、新しい国会の対応が決まってから、私としては求めていないと。したがって、副大臣、政務官は結構ですと、大臣お一人じゃ大変でしょうからということはもう申し上げておりますので、そのことを付言させていただきたいと思います。 今御答弁いただきましたので、その二番目ですけれども、今までいじめといじめによる自殺、自殺については様々な理由があるという御答弁をいただきましたが、様々な理由がある、理由っていうか原因ですね、原因が様々あると。したがって、それが、そのいじめが主な原因でないと判断されていたから今までいじめによる自殺というのが報告されていなかったのか、それともそこを、何というんですかね、まあ違う理由の方を主にしたかったのかということが質問の一点目と、統計上いじめが減っていると、その減っている理由という、その二点についてまずお願いしたいと思います。 国務大臣(伊吹文明君)先生、まず国会でございますから、当然政治家同士の議論をするというのは私は大賛成で、ほとんど私もだから役人の書きました想定問答は読まずに答弁いたしております。ただ、やはり国会でございますので、政治家同士の議論という、質問がやっぱりお互いにやり取りをするということで、余り役人的なことは私は答えられませんので、その点は御了承ください。 今の御質問について私なりの感じを申しますと、確かに多様な原因があるから自殺の原因がいじめだということを認定しにくいという理由は一つあると思います。しかし、それ以上に、これはテレビの番組等で学校の先生や教育の評論家の方々とも私お話をする機会があってなるほどと思いますのは、やっぱり学校は学校なりの良く言えばプライドですね、教師は教師、担任の教師は、あるいは校長は校長なりのプライド。自分の指導がうまくいかなくていじめが出たとか、あるいは学校から自殺者が出たということを、あるいは更に上に行くと、把握していても教育委員会がそういうことを出したくないという、やはり私はモチベーションは否定できなかったと思います。 ですから、再三文科省も注意はしておるんですが、これは不十分だったと私は思いますのは、いじめが少ないのがいいことではなくて、いじめを把握して、そして事を大きく至らないように処理した学校あるいは担任を評価するという方針で教育委員会が対応してほしいということを申し上げているわけですが、これが必ずしも十分行き届いてなくて、まあ人間だれしもそうでしょうが、己を飾りたい、繕いたいということの表れが、残念だけれどもこういう数字になっていると思います。 浅尾慶一郎君ありがとうございます。さすがに政治家同士の議論ということで、本音の話をしていただきました。 私もおっしゃるとおりだと思います。それぞれの学校現場でのプライドもあるでしょうし、教育委員会でのプライドというものが報告の阻害要因になっていると。今大臣お答えになられたとおりだと思いますので、そこを変えていくというのが求められていることだと思いますが。 通告の三番はちょっと大した話じゃありません、飛ばしますので、四番のいじめ、自殺に関して、そういう意味で大臣の責任ということでいうと、まあ恐らくお答えはそういうことになるんだと思いますが、今おっしゃったように、教育委員会あるいは学校でもって本当の理由を、隠すんじゃなくて見付けて報告をするというのを、それを求めるのが責任だという理解でよろしいでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)責任というよりそれは私の職務の一つでして、責任、あえて責任と言えば、まあ率直に言えば今のような指導をしているにもかかわらず、例えば警察庁の資料あるいは法務省の持っている自殺の資料と、自分たちのところへ上がってくる、各教育委員会から上がってくる統計数字に乖離があるじゃないかということを気付く感性がない役人を、その感性を自覚させる指導ができていなかった大臣ということだと思いますね。 浅尾慶一郎君かなり本質的な話をしていただいたんだと思うんですね。 警察あるいは法務省が持っている数字と文科省が持っている数字が違うじゃないかということに気付いてなかったのが問題だと、まあ端的に言えばですね、今までの問題でいえばそういうことだということだと思いますが、今後は、じゃどうやって気付かせるのが大臣としての。 国務大臣(伊吹文明君)気付いてなかったのか、まあそういう統計があるということも知らなかったのか、気付いていたけれどもまあ何の手を打たなかったのか、いろいろあると思いますよ、それは。 しかし、もうそれは済んだことは済んだこととして、これからはどういうふうにするかといえば、やはり役人としての感性を磨かせるより仕方のないことなんですね、これは。国民の税金をもらって仕事をしているわけですから、常に緊張感を持って、縦横ですね、報告、連絡、相談、そして、やったことの最後の確認、これは私が九月に文科省に行ったときに最初に役人の皆さんにお願いしたことです。報告、連絡、相談、確認だけはしっかりやろうよと、これさえできていれば、あとの責任は私が取ると。しかし、これができていなくて私を国会で立ち往生させるということは駄目だよということを言ってあります。 浅尾慶一郎君役人としての感性を磨くということですが、これはちょっと、我が党の同僚に事前通告をしていない質問をあえてさしていただきますが、今の制度ですね、教育委員会制度というのが、先ほど伊吹大臣の方で、そことしてもプライドがあったんではないかと。ですから、本省の役人としての感性というのも必要だと思いますが、制度を若干、民主党案では学校理事会制度をつくることによって変えていくこともできるんではないかということを主張しているわけですが、今のいじめ自殺の問題に即して、学校理事会制度をつくるとどういうふうにそれが機能するかということを、提案者、ちょっと、事前通告ないですけれどもお答えいただけますか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私どももいろいろないじめの現場に行って教えていただきますと、今問題になっております感性といいますか、感度ですね。要するに、教育現場で何かやっぱりシグナルは小さいながらも出ております。やっぱりそこに気が付くのか、あるいは気が付いていてもそのままにほっておくのかと。そういったことについての感度あるいは感性というものが非常に足らなかったということを痛感をするわけであります。もちろん、そこを、感性を磨く、感度を磨いていただくということは非常に重要でありますが、じゃ、それをより制度論でどういうふうに補完をしていくかということも併せてやっぱり我々非常に重要な課題と思って考えております。 私どもが今回御提案を申し上げております学校理事会というものが置かれますと、例えば保護者の方がこれはおかしいと。今回も担任の先生に相談に行っているというケース多うございます。しかし、そのときに受け止める側の担任あるいは学年主任の感性、感度がいま一つであった場合に、今の状況であるとそこで止まってしまうわけであります。そこで我々は、学校理事会を設けて、その中に地域の代表、そして保護者の代表、そしてその代表者が過半数を超えるという制度を用意をいたしております。 そうしますと、保護者は、地域の代表なり保護者の代表に、こういう問題起こっているんだけれども学校側で対応してもらえなかったと、これ十分対応してもらえないかということを直接申し入れることができるわけですね。そうしますと、その日にでも緊急に学校理事会を開いて、この問題をどう対応していくのかということが学校の機関として、学校の意思決定として行えて、そしてそれが直ちに学校関係者によって実行がなされると。 こういう制度を用意することによって、いわゆる感度、感性の低い、あるいは鈍っている方であっても、その行動様式を変えていくという制度を用意をさせていただいているというふうに御理解をいただければと思います。 国務大臣(伊吹文明君)今のことだけに限って言うと、学校理事会というのは非常にいいと私は思います。しかし、衆議院の審議の際に、学校理事会の在り方について御党の前原議員とやり取りをしたときに、理事会には人事権、人事の上申権を与えるということをおっしゃっているわけですね。これは藤村先生も同じ意見でした。そのときに、どういう方がここへ入ってこられるのかということと、学校現場の教育の中立性というものがどう担保されるのかという、このこととは違う大きな考えなければいけない問題があるわけです。 ですから、教育行政でどう担保するかというのは民主党の提案者がおっしゃったとおりの問題意識を私たちも持っております。ですから、今文部科学省がいただくのは、調査の依頼をした結果の数字をいただいてるわけですね。これは西岡大先輩も同じようなお考えのようですが、やはり義務教育の最終責任は国が負うと。これは民主党案にも書いてあるわけです。だから、学習指導要領その他、このいじめの問題等も国が最終的責任を負うわけです。 それをどう担保するのかと。担保するのは、御承知のように、これはもう予算権と人事権とあるいは法律の執行権によって担保しなければならないわけですね。そこをどう組み立てていくかということは、これは民主党案にも我が方の案にもそこはまだ明確に打ち出せていないんですが、そこをやはり将来的には、かなり共通点がありますので、協議をして、今のような変な数字が上がってこないような行政の仕組みを私はつくり上げるべきだと思っております。 浅尾慶一郎君私どもも、理事会制度というのは、単に案として出しているということよりは、より良い学校現場をつくるというために出している案でございまして、そういう意味で協議をしていただけるというのは大変有り難いということですが、鈴木提案者にちょっと、今の先ほどの説明に加えて、協議ということも含めてお答えいただきたいと思います。 鈴木寛君補足で申し上げますと、これは大臣も御承知の上で今のような御答弁されていると思いますが、現行の地方教育行政法でも学校運営協議会というのがもう盛り込まれて、そして幾つかの地域ではもう具体的に実践がされているわけでございます。それを見ますと、やはりおおむねそうしたその地域の声あるいは保護者の声をとらまえた学校運営が行われていて、そしてそのことが子供たちにとって、いじめ問題も含めて、非常に好影響を与えているのではないかというふうに我々は評価をしております。 そういう中で、任命権者についての、上申権についての、先ほど大臣がお話になった点も既にこの学校運営協議会の中で行われていて、これを評価しながら、より全体の公立学校制度に応用、適用をしていこうというそういう文脈の中で、私どもは学校理事会制度を御提案させていただいているということを併せ御答弁申し上げたいと思います。 中略(以下、午後の部より抜粋) 浅尾慶一郎君私もこの理念は賛成であります。 それで、私の質問の趣旨をよく分かっていただくために、民主党案の発議者に民主党案の中に含めてあります財政支出の話も含めてちょっと伺わせていただきたいと思いますが、今大臣が言われた生涯教育ですね、生涯学習ということですけれども、もちろん学校現場だけがその現場ではないかもしれませんが、高等教育ということを考えた場合に、大学、大学院その他の高等教育ということを考えた場合に、大学、要するに社会に出てから大学に行く人の割合がアメリカその他諸外国の方が日本より、これは数字を持っておりませんが、高いような気がいたします。GDPに占める公財政教育支出の高等教育だけを取っても、日本は〇・五%、アメリカが一・二%、最も高いフィンランドが一・七%と日本よりかなり高くなっていると。 ですから、今のことを実現するためには、初等中等教育ももちろんでしょうけれども、高等教育にいったん社会人になってからも財政的な支援をしていったらいいんではないかなと思いますが、そのことをプログラム規定で書いております民主党案のまず趣旨を説明していただければと思います。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私ども民主党は、まず民主党法案の第二条でもって学習権というものを定めておりまして、何人も生涯にわたって学びを十分に奨励され、支援され、保障されると、こういうことをうたっております。これは、私ども民主党法案の極めて重要な考え方を表した条文だというふうに我々思っております。 そうしたことを正に実現をする上での環境整備を行うということが、これは国のあるいは公の使命でありまして、そのことが、先ほど浅尾委員からもございましたけれども、例えば特に高等教育においては、お示しのあったような、日本が先進各国に比べて明らかに低い水準に高等教育の公財政支出があるという事態にも反映をされているんだろうと思いますし、あるいは国際人権規約の十三条二項の批准が後れているということにもあるんだろうと思いまして、こうした事態を、せっかくあのとき教育基本法の議論をして作り直したんだから、あの二〇〇六年あるいは二〇〇七年からあの議論があって、日本がそうした生涯学習社会そして学習権を本当に真の意味で保障する社会に変わっていったんだなと、ああいい議論をしたなと、こういう議論にしたいということで、私どもはこの第十九条の中で教育の振興に関する計画ということを定めまして、そして、政府は、国会の承認を得て、教育の振興に関する基本的な計画を定めなければならないとともに、これを公表、国民の皆様方に公表すると。そして、その計画がちゃんと進捗しているのか進捗していないのかということをきちっと国民の皆様方が検証し、そしてそのことを基に、もちろん限られた貴重な税金でございます、それを何にどのように、いずれも重要な政策課題でありますが、こういう状況であれば更に高等教育に、あるいは教育につぎ込んでいかなければならないなという御議論を喚起するためにも、GDPに占めるこうした財政支出の比率なども含めて国民の皆様方に明らかにしていくということを考えております。 もう少し実態だけ申し上げますと、やはり私どもが大変危惧をいたしておりますのは、高等教育費における家計の負担割合でございます。日本はOECD加盟三十か国中最高のといいますか最悪の、家計の負担比率が六〇・三%に上っております。これは、アメリカですら三分の一、ドイツ、フランスということになれば、これはもう学費はただでございますが、今の数字は生活費も含めてということでございますが一割程度でありますし、フィンランド、デンマークは三・六%、三・三%、スウェーデンに至っては完全に家計、自己負担というのはゼロ%になっていくと。これが理想でありますけれども、少なくともアメリカ並みの水準にはきちっと毎年予算を確保しながら、こうした方向に向けて実現をしていかなければならないのではないかと。 この教育基本法が施行されている中で、国立大学の授業料の急激な上昇というのが、これは非常に重要な問題だというふうに思っておりますし、そういう中で、私どもも毎年、これは委員御存じのとおり、政府の予算案に対して民主党の予算案というものを対案として毎通常国会、予算委員会に提出を、お示しをさせていただいております。 例えば、平成十八年度民主党予算案、これは私も次の内閣の文部科学大臣としてその立案に参画をいたしましたけれども、政府案よりも文教科学費で申し上げますと八千億円増額という形で私どもは対案を示させていただいて、その中に、奨学金の充実あるいは高等教育費の拡充と、国立大学及び私立大学に対する助成や運営費の増額ということをうたっているところでございます。 浅尾慶一郎君伊吹大臣に伺いますけれども、今、民主党案で公財政教育支出の割合を発表し、増やしていくと、アメリカ並みにしていこうということが説明がありましたけれども、この第三条で定める生涯学習の理念を実現するために、大臣としては財政的措置はどのようにとっていこうと考えておられるのか、伺いたいと思います。 国務大臣(伊吹文明君)これは、各々の生涯教育に入ってきたいと思われる方々の所得の状況その他勘案して、必要な措置があればそれはとらないといけないと思います。 一つ申し上げておきたいのは、やはり私たちは政権を預かっているわけですから支出のことだけを言うわけにはいきません、これはね、予算というのは歳入と歳出のバランスの上に成り立っているわけですから。 ですから、私も教育予算は今の御説明のように増やしたいと思っているわけですよ、文科大臣として。しかし、その中で民主党さんがGNPの何%ということをおっしゃるんであれば、それをどのような租税構造によって国民負担で賄っていくのか、それから、あるいは租税を増やさないんであればどこを減らしてそれを、六千億ですか、何か今おっしゃった六千億、七千億を賄っていくのか、そのことをまず明らかにすると同時に、国民にマイナスになるところには皆さんこれだけの痛みを強いますよと、租税を取るところにはこれだけのことになりますよということをやっぱりはっきり申し上げて、私たちもそれがいいと思えばそれに乗りたいと思いますから。 浅尾慶一郎君じゃ、鈴木委員、お願いします。 鈴木寛君平成十八年度の民主党予算案の対案の概略についてだけ、お時間もございますから申し上げます。 民主党案は、歳出総額が七十九・三兆円ということになってございます。政府案は七十九・七兆円でございますから、政府の総額の歳出よりも〇・四兆円、四千億カットしたそうした予算の中で、先ほど申し上げましたように文教科学振興費については八千億プラスをしていくと、こういうトータルの案をお示しを国会で、さきの通常国会の予算の議論の中でお示しをしております。 じゃ、どこを減らすのかと、一々申し上げませんが、私どもはやはり公共事業関係費等々を、正にコンクリートから人づくりへというのが私どもの予算編成方針でございましたから、そうしたところを削って教育等々に振り当てていくと、こういった予算の考え方できちっとトータルの総額をお示しをしているところでございます。 中略 水岡俊一君はい。 それでは、せっかくの機会でありますので、今論議をしてまいりました学ぶ権利でありますとか、あるいはその学校教育をどういうふうにどういった形でとらえていくのか、第二条、第三条、第四条、第七条、いろいろとありますけれども、できましたら我が同僚の鈴木寛議員にお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私どもは、正に国際社会の中で国際社会の一員としてそうした条約を最大限実現をしていく、そういった意味でも国際社会のリーダーになりたいという思いを持ってこの法案を作らさせていただいております。 したがいまして、第二条におきましては、何人も、生涯にわたって、学問の自由と教育の目的の尊重の下に、健康で文化的な生活を営む、学びを十分に奨励され、支援され、保障されると、こういう条項を盛り込んでおりまして、これは日本国民のみならず日本社会すべての人々にこうした権利を保障していきたいと考えておりますし、第三条の主語も、何人も、その発達段階及びそれぞれの状況に応じた、適切かつ最善な教育の機会及び環境を享受する権利を有するということ、それから第四条で、学校教育におきましては、すべての国民及び日本に居住する外国人に対して、意欲を持って学校教育を受けられるよう、適切かつ最善な学校教育の機会及び環境の確保及び整備に努めなければならないという条項を盛り込まさせていただいておりますし、また第七条でも、何人も、普通教育を受ける権利を有すると、こういうことを盛り込まさせていただいているところでございます。 このことが、やはり日本社会の健全な発展に極めて、今委員のおっしゃった不就学の児童の問題を放置するということは、日本社会全体の教育の在り方にとって極めて望ましくない状況だという判断の下でこのような条項を整備させていただいているところでございます。 水岡俊一君ありがとうございました。 民主党案では、何人もという主語を使う、そして、日本に居住する外国人という言葉も使いながら、日本がこれから取るべき姿、方針を一生懸命表しているというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。 そこで、今、不就学のお話を申し上げましたが、それだけの数の、あるいはもっと多いかもしれません、不就学の児童生徒がいて、そしてこれに対して効果的な施策が行えないとすると、これは何年かしますとその方々が成人をしていく、その中で働くことも難しいかもしれない、さらに、厳しいその生活の制約が出てくるんではないかということが想像されるわけですね。 そういったことについて、大臣、ちょっとお考えがあればお聞かせください。 国務大臣(伊吹文明君)今からもう、そうですね、三十五年ほど前なんですが、私は四年間英国に駐在していたことがあります。英国は日本とは違って植民地国家ですから、特に労働力が非常に不足して、海外からの人を入れてきているんですね。これは、国策として入れてきておったと思います。しかし、不況になると必ずトラブルが起こるんですね。社会不安が起こります。特に、英国のロワークラスの人と外国から入ってきた人との間に一番激しいフリクションが起こる。 日本はそういう国にしてはやっぱりいけない、これは先生と私と共通の思いだと思いますね。やはり世界各国を見ましても、外国から人を入れてくることについての大きな国策がまず表に出てこないと、教育の問題、福祉の問題についての扱いもきちっとできないんですよ。これは立法政策上の問題として、基本法に、国家の憲法だとか教育基本法という基本法に、これは調べてみないと分かりませんよ、私が知っている範囲では、外国人のことを書いているということは極めてやっぱり少ないと思います。それは、それ以下の法律においてその現実をどう担保するかということだと思うんですね。 だから、先生の人道的な温かいお気持ちは、私は決して反対じゃありません。しかし、国家を預かっている立場からすると、外国人の労働者という、外国人の方で日本へ来ていただく方を全体として日本国家がどういう形で迎えるのか、制限的にやるのか、それから国際条約も、今は、先ほど先生がおっしゃった数の足し算引き算からいうと、確かに何のとがもない子供がそれだけ不就学であるという数字になると思いますが、同時に日本の教育基本法は、日本の国民について、保護者は受けさせる義務があると、こう書いているわけですね、御承知のように。そうすると、保護者というものが違法な状態で、日本の法律上違法な状態で国内に存在しておられるとした場合ですよ、その人の保護の下にある子供さんをどう扱うかという、これは人道上のことはよく分かります。しかし、これは国際法上、かなり詰めないとやっぱりいけない問題を含んでいるということは理解してください。 鈴木寛君お答え申し上げます。 法律には、属地主義と属人主義という、この二つの大きな考え方があろうかと思っております。で、我々は日本社会における教育のありようを議論をしておりまして、もちろん外国人をこれ受け入れる受け入れない、これは教育政策の範疇外の話でありますが、結果として不就学の多数の児童が存在していて、それが同世代の日本の国民の教育に対して極めて大きな影響を持っているという観点も我々は十分踏まえさせていただいております。 それから第七条で、民主党教育基本法案では、義務教育を受けさせる義務は、「国民は、その保護する子どもに、当該普通教育を受けさせる義務を負う。」ということで規定させていただいているところでございます。 水岡俊一君大臣、最後に、私一つ勉強してきた中で分かったことは、憲法第二十五条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と、こう書いてあって、すべて国民はということに対象がなっているということはここからもよく分かるんですね。ところが、憲法三十条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と、こう書いてある。これも国民なんですね。ところが、在日の外国人労働者は、同じようにやはり納税をしているわけですね。 そういった意味からすると、納税をさせながらそれに対する手だてを、やはり一部、少ないということであれば、それは問題があると思うんですね。やっぱり国際化の中で、それは日本の、先進国の一つの大きな代表的な国として、その問題はやっぱりきちっととらえていく必要があるんだというふうに私は思うので、今後のまた論議の中でもお示しをいただいたらというふうに思います。 これで私の質問を終わります。 |