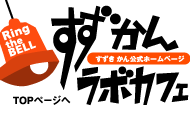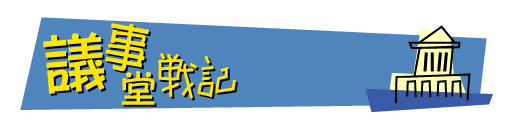2006年11月27日 教育基本法に関する特別委員会岡田直樹君民主党案の提出者の先生方にお伺いをしたいと思います。 ただいまも伊吹大臣からお話がありましたとおり、民主党の憲法提言、これは日本国教育基本法案にどのように反映をされておりますでしょうか、お願いをいたします。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私ども民主党も正に憲法調査会と教育基本問題調査会、これを正に同時並行的に議論をこの数年深めてまいっております。私ども民主党におきましては、二〇〇五年の十月三十一日に民主党憲法調査会の民主党憲法提言というものを党としてまとめさせていただいているわけでありますが、その中で一番最初に掲げている項目は、未来志向の憲法を構想するということでございます。 憲法というのは、先生も御承知のように、正に主権者が国家機構に公権力をゆだねると同時にコントロールをすると、こういう固有の役割があるわけでありますが、と同時に、私どもはやはり国の在り方というものをきちっと宣言をしていこうと。やっぱり、どういう国をつくるんだ、どういう社会をつくるんだということについて、日本国民の精神あるいは意思をうたうということ、これも重要ではないかと。すなわち、我々は、国際社会と共存し、平和国家としてのメッセージをやはりきちっと示していこうということを憲法提言の中でも言っております。 そうした提言に呼応いたしまして、私どもが提出をいたしました日本国教育基本法におきましてはその点を前文の中で相当意識をいたしておりまして、すなわち、我々はこの教育基本法を作る上で新たな文明の創造ということを希求するんだと、こういうことを強く打ち出させていただいているところでございます。 じゃ、新たな文明というのは何なのかということでございますけれども、今まで、今、現在は正にフランス市民革命あるいはアメリカ独立革命以来、いわゆるブルジョア革命の中で、どちらかというと物質文明偏重型の社会というものが構築されてきたと思います。環境問題にいたしましてもテロの問題にいたしましても、様々な問題というのがいわゆるそのモダンソサエティーの枠組みの中で相当なゆがみが来ていると、これは人類共通の課題だと思います。 そういう中で、ヨーロッパもそうでありますけれども、日本としても次の、いわゆるポストモダンといいますか、近代の次のその枠組み、これを人類全体として新しい時代を創造していくわけでありますが、今回は我々日本国民もその人類の大きな営みの中に率先してリーダーシップを発揮していきたいということを考えて、正に物質文明偏重主義を超えて、これからは情報でありますとか知恵でありますとか文化でありますとかコミュニケーション、いわゆる物の時代から情の時代と言ってもいいかと思いますが、そういう時代をつくっていきたい、そのための人材を育成していきたいということをこの中で強く意識し、盛り込まさせていただいているところでございます。 そして、私どもは五つの基本目標ということを憲法提言の中に掲げておりまして、その中に自立と共生ということ、これも極めて重要な課題だと思っておりますし、それからこの五十年の、六十年の日本のいろいろな憲法あるいは教育基本法をめぐる議論を見ていて思いますのは、国民主権なんですね。真の主権者になれば、そんなに、何というんでしょうか、我々が本当に常識的にそして正しいと思うことを堂々と議論をしていけばいいわけでありますから、もっともっと国民主権が徹底をされれば、何というんでしょうか、不毛な議論というか、もっと実質な議論ができるのではないかなということもございまして、私どもはこの一条の中で真の主権者を育成するということを盛り込み、そして十五条の政治教育の中でもそうした真の主権者をつくっていくんだということをうたっております。 それから、世界人権宣言や国際人権規約という普遍的な人権保障というものを確立していく、これも重要だと思っています。 例えば、これは先生御承知だと思いますが、日本は国際人権規約十三条の二項の(c)で、これは高等教育への漸進的無償化条項というのがございますが、残念ながら日本はマダガスカル、ルワンダとともに、この三つの国だけこの条項を留保しているわけでありまして、せっかく教育基本法を作り直すという議論の中で、やはりこうした人権についてはきちっとこれを機会に留保を撤回をして批准をしていくということもこれに呼応した、この我々の憲法提言に呼応した動きでございます。 それから、我々民主党は五つの基本目標の中で、日本の伝統と文化の尊重とその可能性を追求し、併せ個人、家族、コミュニティー、地方自治体、国家、国際社会の適切な関係の樹立、すなわち重層的な共同体的価値意識の形成を促進することということを言っておりまして、新しい文明の創造にもかかわりますけれども、やはり情報、文化、コミュニケーションということになりますとアイデンティティーというのは非常に重要であります。 そういう中で、日本のそうした、きちっと日本を愛する心を涵養する等々のことを盛り込みながら、同時に、コミュニティ・スクールあるいは地域立学校など、共同体意識ということも大事にしていくというようなことを盛り込んでいるところでございます。 鈴木寛君民主党・新緑風会の鈴木寛でございます。 少し今の議論を引き取らせていただきたいと思いますが、大臣、こういうことなんですね。教育には今回から大学教育も入っているんですね。大学教育においては、学問の自由というのは、これは極めて重要だということはこれはもう疑いのないところで、先ほど大臣がおっしゃいましたが、憲法二十三条、これ学問の自由を規定していますけど、これは何の制限なく学問の自由を保障しているんです。これは、もう大臣御承知のとおり、憲法の基本的人権にはダブルスタンダードがありまして、表現の自由にかかわる話というものは、これはノーコンディションで認められなきゃいけないと、学問の自由というのは表現内容をつくると、創造するという上で根本的な人権でございますから、したがって学問の自由は何の留保もないというのがこれ憲法二十三条の解釈だというところは大臣も御了解をいただけると思うんです。 したがって、私どもの案では、「学問の自由と教育の目的の尊重の下に、」で、アンダー・ザ・コンディションなんですね。大臣がおっしゃったように、これはウイズ・ザ・コンディションなんですよ。ここはやはり違うんです、法制的に。それで、大臣が立法者として、提案者としてそういう意図がないという今御答弁、これは非常に貴重なというか重要な御答弁で、そのことは我々大切に受け止めさせていただいて、ある意味で胸をなで下ろしているところがありますし、大臣は非常に常識的な教育基本法を作ろうとしておられるという意思はよく分かりました。 要するに、これは私非常に、大臣就任以来、いろいろな委員会で御一緒させていただいております。これ、たらればということはないんですけれども、この教育基本法案を閣議決定されるときに大臣が、伊吹大臣が文部科学大臣でいらっしゃったらよかったのになと思うことが物すごくあるんですね。といいますのは、伊吹大臣はやっぱり相当立法についてもきちっと御理解していただいていて、正に今の立法者が言わんとすることと、それをどのようにするといろいろな法的な懸念なくきちっと伝わるかということについて、相当分かっておられるというか、極めて非常に正確な理解の下にいろいろ御答弁をいただいていて、すごくある意味でかみ合った議論になりつつあるのを大変うれしく思っているんですけど。 要は、こういう言い方ちょっと失礼になるんですけど、率直に申し上げますと、今回の政府案は、その中身がいい悪いの議論の前に、ちょっとやっぱり詰まっていないことが多いんです。といいますのは、教育って、ここではやっぱり大学教育も含めた定義をしているんです、新しい方が、明らかに。大学という項目が入っているわけですね。そうするとやっぱり、初中等教育も大事ですけど、やっぱり教育全般について、生涯教育も全般について、やっぱり第二条をきちっと見直すということが、これは法令審査のときになされるべきなんですけど、明らかに文部省の方々は初中等教育を念頭にこれ一号、二号、三号、四号、五号書いているんですよ、やっぱり。もちろん大学教育でもこういうことが達成されたらいいと思うんですけれども。 だから、やっぱり、今日これから申し上げたいのは、いろいろと、ちょっと不適切と言うとまた語弊がありますから、不十分な表現というか、要するにまあ役人の言葉で言えば詰まっていない表現が多いんですね。で、大臣がその提出時のとき言っていただいたら、ちゃんと詰めていただいて、で、もう一回内閣法制局に差し戻して、これどうなんだと、これで本当にいいのかという確認をしていただけたのに、とっても残念だなという気がしているんです。 それでちょっと、まあ昔の教員は良かったという話がありますが、昔の官僚はやっぱり良かったなと。大臣は何年の御入省でいらっしゃいますか。 国務大臣(伊吹文明君)私は、財務省にというか現在の、大蔵省へ入りましたのは昭和三十五年でございます。 鈴木寛君これやはり大臣、二十二年いらっしゃったということをホームページで拝見させていただきましたが、やっぱりもう昭和三十五年入省の先輩方というのは、本当にやっぱりもう国会を支えるんだという高い志と、それからそれを支えられる物すごいやっぱり御見識と使命感を担ったお仕事をされていらっしゃったなというふうに思います。 それで、これ正直に申し上げて、最近この文部科学省のみならず、やっぱり霞が関から出てきている法案のクオリティーが下がっている、これは間違いないと思います、これは、と思います。それは間違いない、本当に間違いないと思います。 それで例えば、文部科学省にお伺いしますけれども、中教審の平成十五年三月二十日で示された、これ教育基本法の骨子というのが出ているんですね。ほぼ法案要綱です、政府の考える。そこと、今回政府がお出しになった教育基本法で決定的に違う、まあ違うことをいかぬと言っているわけじゃないんですよ。もうちょっと言うと、中教審答申を書くときに、まあ文部省が忘れていたというか見落としていた項目があるんですよ。それはどういうところですか。 政府参考人(田中壮一郎君)お答えを申し上げます。 中教審の答申と政府案との相違点についてのお尋ねでございますけれども、主な相違点としては二点ございまして、一つは、答申においては、引き続き規定することが適当とされておりました九年の義務教育期間、この定めを、別に法律に定めるところによりということで、学校教育法に任せておるというのが一点でございます。 二つ目には、答申では、特に平成十五年三月の答申では特に提言されておられませんでした幼児期の教育の条文を新たに設けたところでございます。 鈴木寛君これ、一点目のところは非常に重要な政策論争といいますか、要するに中身を詰めていく議論で、我々もそのように対応しておりますし、正にこの教育基本法を見直す上で政策論議として、していく点です。 しかし、二点目は、まあ端的に申し上げると、中教審のときは幼児教育というものが教育の重要な要素だという認識がなかったわけですね。で、中教審やりながらですよ、これ諮問を受けてから一年から二年掛かっているわけですよ。二年間の間、教育の中で、で、これだけ少子化で幼児教育が、就学前教育が重要で、イギリスでもスウェーデンでもフィンランドでもそこのあるいは無償化とか、年齢の引下げとか、そういう議論がありながら、二年間中教審で幼児教育とか就学前教育を入れるのを忘れていたというのがこれ実態なんですね。それは答弁は幾らでもできると思いますが、これは大臣に正確にその実態を御理解をいただきたいと、そういうことなんですけれども。 それで、私どもは、これはいかぬなと。別にこれは民主党とか自民党とかという話じゃなくて、やっぱり就学前教育あるいは幼児教育、あるいは一方でこども園法案とか、まあそういうことをやっている中で、やっぱりそれは就学前教育というのはこれは本当に大事なんですね。そこのところはもう恐らくもうすべての党が一致していると思いますが。で、我々は作業部会で就学前教育の重要性ということを入れました。そして、自民党と公明党さんの討議の中で、そこで出てきたペーパーの中に、まあやっとというか、幼児教育、就学前教育という項目が足されて、そして法案では入ったと。これはまあ一安心なわけですけれども、幼児教育のような重要なこともちょっと抜け落ちちゃうというのが今の残念ながら事務方の実態だということは御理解いただきたいと思います。 それから、政府案七条では大学という項目になっています。私これ見て、ああまた、これ別に政策的にわざと大学だけしたんじゃないと思うんですね。答弁の後付けで、何というか誤謬性を、後付けでもとにかくこれは守らないといけないのが立場ですから、いろいろな答弁ありますけれども、私どもの案では高等教育としているんですよ、趣旨は同じで。恐らく立法者の御意思は、高等教育機関、例えば高専とか、大学以外にも立派な、大変重要な任務を負っていただいて実績を果たしていただいている高等教育機関あります。恐らく大臣も、それも重要だと思っておられると思いますし、もちろん大学は大事だと思っておられます。これも恐らくここにいる委員の、すべての立法者の意思は、高専も含めて、あるいは専門学校の後期課程も含めて、是非日本の高等教育機関の一翼として頑張ってほしいという、多分総意だと思うんですよね、これはもう自民党さんから共産党さんまで。 そういう立法意思がありながら、ありながらですよ、法律というのは、これ反対解釈とかいろいろな解釈ありますですよね。書いていないことは要するに反対解釈として含まれない。高等教育という法律用語があって大学という法律用語があれば、それは大臣おっしゃったように違う用語ですから、その差異は何かということになります。この場合のその差異は明確に高専が入るわけです。あるいは、要するに学校教育法で高等教育はいろいろちゃんと条項があって決まっているわけでありますから、その中で大学だけ抜き書きしたということは、それ以外は排除するというのは、これは反対解釈ということも御理解いただけると思うんです。ここも後付けでいろいろ言いようあるかと思いますが、やっぱり忘れていたんだと思うんですよ、これは。 大臣に聞きます。大臣は、ちょっと、要するに責任論に落とし込むと話がどんどんどんどん何というか重箱の方に行って本筋からずれてしまうので、ずれてしまう。私はもう今日はストレートだけでいきますから、引っ掛けとか変化球とかなしで、それはもう本当にやっぱり教育現場を良くしたいと思っていますから私は、思っていますから、この後の処理はどうするかということは別として、やっぱり教育において高等教育重要で、その中で大学も高専も大事だと、決して高専を、反対解釈を、意図的に抜いたわけじゃありませんと、そういう立法意思を提案者として持っておられるか。いや、その後のことをぐちぐちは言いませんから、そこどうですか、政治家の気持ちとして。 国務大臣(伊吹文明君)まず、私にシビルサービスに入った年次をお聞きいただいたんですが、鈴木先生は通産省には何年にお入りになったんでしょうか。私よりかなり若い年次にお入りになっていると思いますが、先生の御質問をずっと聞いていて、近ごろの若い公務員の立法マインドが先生を通じてそんなに落ちていないということを私は理解して、非常にうれしく思っております。 その上で、まず先生もずっと公務員をしておられましたから審議会の役割というのは分かると思いますが、役人がいろいろ審議会を適当に隠れみのに使ったり動かしたりしているという事実もあります。しかし、審議会が答申をしたことを大臣がみんなそのとおり聞くかどうかは、これは大臣の判断です。そして、省の行政というのは大臣が最終責任を持っておりますから、私は、例えば英語教育というのは必修にするには小学校ではやや早いんじゃないかと、国際感覚を養うのはいいですよ。だが、中教審はそういう御答申になっても、私はそれを取るかどうかは私が判断すると。中教審が十年という研修期間をお示しになっても、十年がいいかどうかは私が判断するということを申し上げているわけです。 ですから、自民党、公明党で現在の政府提案の骨子になるものを作っていただいたのは中教審の答申ではないんですよ。自民党、公明党で長年練り上げたものなんですね。ですからそこで、その政治の場で、今先生がおっしゃったような幼児教育が抜けているということに気が付いたということであれば、これはやっぱり議院内閣制のいいところであったと前向きにとらえていただいたら私はいいんだろうと思いますね。 ですから、今の専門学校その他についても、これは、ここに書いていないとやはりウエートが落ちるということは分かりますよ。しかし、ここに書いてないからできないのかというと、そんなことは何もないんで、三十何本の法律の中でその重要性は十分認識をして、そして予算等でそれに肉付けをしていくと。だから、当然、大学教育ということだけを書いておりますが、専門学校その他について軽視をしたりですね、それを、ここへ入っているか落としたかという議論はちょっと御勘弁いただきたいんだけれども、それを軽視するということは私はいたしません。 鈴木寛君私もその役所の書いた…… 国務大臣(伊吹文明君)何年ですか。 鈴木寛君私は昭和六十一年でございますが、私は霞が関の限界を感じまして脱藩をいたしまして、慶応大学の湘南藤沢キャンパスの助教授になり、役所で磨いた立法技術を活用いたしましていろいろな、その後学者として立法提案活動をさせていただいております。 それで、私はそのために政治があると思っています。だから、私は今政治家としてここに参加させていただいているわけでありますが、大臣おっしゃったとおりだと思うんです。それは、与党の御議論の中で、御審議の中でより良いものが追加された、これあるべき姿だと思って、そこは与党の御見識というものを評価したいと思います。 と同時に、これはやっぱり議院内閣制であると同時に議会制民主主義でございますから、やっぱり国会の議論の中で皆様の思っている立法意思、あるいはやっぱり人間に完璧はありませんから、だからいろいろな与党審査あるいは国会審査ということを経てより良いものを作っていくために審議をしている、正にこれが熟議の民主主義だというふうに思います。 私は、常々残念だなと思いますのは、日本ほど国会における修正というのが行われない国はないんですよね。ドイツでもイギリスでも、正にドラフトが出てきて、そしていろんな知恵を入れて、そしてちょっとでも、もう一%でも二%でもいいものを作っていこうということで法案ができている、これが本来の私は議会制民主主義だというふうに思っております。 それで、ここでちょっと法務省さんのことを褒めたいと思うんですけれども、私が議員になりまして五年半たちますけれども、法務省だけビヘービアが違うんです。要するに、おかしいなと思ったら、法務省というのは恐らく霞が関の省庁の中で最も引き続き立法能力の高い役所だと思います。まあ逆に、だから自信があるのかもしれませんけれども、その法務省さんが提出された法案、重要法案、どの役所も重要法案出していますけれども、国会の議論の中で、あっ、これはおかしいなと、みんながあっと顔を見合わせるような条文の、まあ何というか、漏れとまで言いませんけれども不十分なことが、要するにもっと良い案が議論がなされた場合は、物すごく柔軟に修正に応ぜられるんですね、法務省さんは。 したがって、与党の法務委員会の理事の先生方も、これは過去の事例見ていただいたら、明らかに法務省だけが議会に出てからの修正多いですよ。残りの役所は、これも私もよく分かりますけれども、役所の原理として、これはきっすいの霞が関の役人ですから。法務省さんの場合は、法務省民事局長というのは裁判官から来られるんですね。刑事局長は検察官から来られます。だから、ある意味では正に立法者としての良心というのが、こういう言い方は分かりません、分かりませんけれども、僕はとてもあるべき姿だといって、いいことですから評価させていただいているんですけど。正にやっぱりそういう姿というのはすごく尊重していいと思いますし、とりわけ教育基本法ですから、本当に英知を結集して、この国の教育現場を良くするための議論と、そしてそのことをより正確に伝わるような条文化、そしてそれを今度は現場にどうメッセージを伝えていくのかということに私はやっぱり与野党を挙げて全力を挙げたいな、私もそのお手伝い、一員でありたいなと、こういうことを思っているわけでございます。 私たちは、そういう意味で、本当に今までの長年の、何といいますか、この五十年、六十年、教育基本法、今の教育基本法の下でやっぱりいろいろ制度疲労とか時代に合わなくなってきたこととかがあると思っています。したがって、教育基本法をもう一回やっぱり全部見直して、そして日本国教育基本法ということで出させていただいているんです。 私たちは、実は平成十七年の四月十三日に「新しい教育基本法の制定に向けて」という報告書を出したんですけれども、そのときのポイントは、こういうことで教育基本法の議論をし直そうと。一つ目は、現場において発生している重要な課題を解決、改善するため。それから二つ目は、現場からの国民的な改革運動をより強力に推進するため。これ現場では実はいい動き一杯もう既に起こっております。これに対してどうやって我々が更にエンカレッジしていくかということ、とっても重要だと思います。それから、長年懸案となっている課題を政治主導により決着させるため。そして四としては、憲法、教育基本法の趣旨実現のために教育関連法制の改正、追加を行うため。そして五番目として、国際条約、国際宣言等で、その実現のための必要な国内法の整備を行うため。この五項目に照らして今の教育基本法がどうなのかということを一から検証し直して、そして作らさせていただきました。 例えば、今日も午前中に岡田委員等の御質問の中でいただきますの話がありました。これは富山県で起こったという事実が確認されているわけですね。こうしたこともやはりおかしなことだと私たちは思います。大臣が御答弁されたと全く同じことを私たちも思っています。それで、であるので、そういうことをきちっと、今一部に解釈の揺れがあって、一部にそういった事実が起こっているから、今後はそういうことがないような、法律の疑義がないように少しでも書き直せるところは書き直そうとか、あるいは、これは是非もう使ってくれるなということで徒競走の例を前回佐藤議員が申し上げましたが、しかし、あの例は実態なきことでもありますが、ただ、いわゆる形式的平等主義がいろいろなところではびこっているという認識は我々も持っています。 したがって、私たちはその形式的平等主義を排除するために、大臣、お手元に私どもの案もあると思いますけれども、例えば、今まで、ひとしく、その能力に応ずる教育というふうに書いてあるところを、その議論をしました。形式的平等主義をなくして、本当にその子供それぞれにとっていいことは何なのかを考えてそのための教育行政をしようと。そのために、せっかくのこの大改正あるいは抜本見直しの中でしようということで、例えばその発達段階及びそれぞれの状況に応じて適切かつ最善な教育機会及び環境を享受する権利を有すると、あるいはこの表現が随所に出てきます。そういうような一つ一ついろいろ検証させていただいて今回のを出させていただいているんです。 私は決して今の文部省の方々が能力が落ちたということを言うつもりはありません、我々の仲間もまだ一生懸命頑張ってやっていますが。しかし、パフォーマンス、出てきた結果はやはり私は落ちていると言わざるを得ない。その要因を今日ここで議論するつもりはありませんけれども、それはひとえに、やっぱりいろんな要因あると思うんですよ。 ただ、大臣おっしゃるように、政治主導なんだと。それ私大賛成です。だったら、もう一回政治家がこの政府案なり、あるいは私たちもきちっと一つ一つそういう議論を全部して、今起こっているいろんな非常にナンセンスな問題を解決するために、その疑義の源となる教育基本法の関連の分については少しでも改善をしようという努力をしてきましたから、それをこの良識の府の参議院で一つ一つ、一文一文皆さんと一緒にチェックして、ここはこういうふうにした方がいいよねとか、もちろん全部の案を我々のんでくれと言うつもりはありません。 それから、我々以上にいろいろな、逆に言うと、四月の政府案が出たときには気が付かなかったけれども、やっぱりいじめ問題とか見てみたらこういう案があるなというのは、恐らく自民党の委員の皆様方も公明党の委員でも共産党も、皆さんいろいろお知恵をお持ちだと思うので、そういう議論を私は是非していきたいと思いますし、そのことを受け止めていただける大臣にここにお座りいただいているということは、我々大変に幸せなことであります。 この幸運を生かさない限り、後世の皆様方に申し訳が立たないなと思うわけでありますが、いかがでございましょうか。 国務大臣(伊吹文明君)先生の先ほど来のお話をずっと伺っておりまして、大変私は感銘を受けました。政治家は本来そういう形で議論しなければならないと思いますね。ただ、私の立場からしますと、これはやはり一番いいものだとして出しているわけです。だから、そういう立場で私は答弁しなければなりません。 しかし、日本国憲法によれば、国民の総意を代表しているのは、タウンミーティングでもなければ、あるいはまた世論調査でもなくて、国民全員が参加をして投票した、もちろん棄権している方もおられますが、国会なんですよ。だから、国会議員が決めるんですよ、最後はね。ですから、立法府としてはどういう御判断になさるかは、これは私は立法府の中で御議論いただいて、困ることは私たちが行政府として申し上げますけれども、そこはお話合いがあったって構わないと思いますよ。 ただ、一つ、是非先生に申し上げておきたいのは、先生のようなお考えで、実は今国会じゃなくてその前の国会、先生の通商産業省の先輩である町村信孝先生が、衆議院で我が党の教育特の筆頭理事でありました。通産省出身だから同じようなお考えだったんだと思いますが、そのようなお話を少し申し上げたようですね。 それで、具体的にはどうぞ党の大幹部から聞いていただきたいと思いますが、いろいろな政治情勢があってそれを受け止められる形にはならなかったという事実だけはどうぞ党内でよく御調整をください。 鈴木寛君そのことは、私も、いろいろな背景があって、そして衆議院のいろいろな経過があるということで、そこを一々今反論は申し上げません。 しかし、ここ参議院で、正に二院制で、更に良識の府で、これはもう舛添先生も冒頭、今いらっしゃいませんが、おっしゃいました。正に我々参議院議員のこれは特に国民の皆さんから求められている責務だということで、その職務に忠実に我々は仕事をしたいという思いも持っているということも御理解をいただきたいし、あるいは、今大臣の、正に国会が決めるんだということは是非、すべての党の委員の皆様方と今ここで聞かしていただきました。感銘を持って聞かせていただいたということをお話を申し上げたいと思います。 そこで、今日御議論をさせていただきたいのは、やはり私は、いじめ問題等々起こりました。我々も、私、実は民主党の教育基本問題調査会の事務局長を五年間させていただいております。それで、いろいろ教育現場の皆さん方のお話を聞いたり、あるいは、私自身も慶応大学にいるときに本当に小学校、中学校に情報教育を普及させるということで回りましたし、私自身も高校の非常勤講師もさせていただきました。 結局、いろいろ問題があります。そして、教育というのは決して制度論だけでは片が付きません。しかし、制度論も重要な一つの要素であることも間違いないと思いますが。民主党は、あるいは、これは私の持論でありますけれども、民主党へ入る前からの、やっぱり地方教育行政法は少なくとも長年経て制度疲労に来ていると。さきの総選挙のマニフェストでも、地教行法はやっぱり見直すということをマニフェストで問題提起させていただきました。 ただ、地教行法というのは、これ大変に重い法律でありますし、それから、特に教育委員会法の時代から地教行法の時代で、これはもう本当にその当時の時代背景も含めて、冷戦構造も含めて、朝鮮動乱とか、もういろいろな要素の中であのような地教行法ができたということであります。 したがって、やっぱり地教行法を変えるということは、これは正に日本の教育基本法を頂点とする法体系のコア中のコアの議論だと。これをやっぱり変えるというのは、正に教育基本法を変えるというこういう時期でないとこれは議論できないだろうということで、その問題提起をずっとしてきたわけであります。 で、中教審も二年間掛けられました、あるいは与党協議も十分にされましたということなんでありますけれども、しかし、思い付いたときに、まあ善は急げですから、そのことをみんながそうだと納得したらそのための枠組みを作ってそのための検討を急げばいいわけなので、別に昔のこととか過去のことを、中教審が何やっていたんだということを言うつもりは私、毛頭ありません。正にこの議論、ここでの議論できちっとじゃ議論しようということになればいいんで。 そこで、私たちは少なくとも今回の参議院において日本国教育基本法と同時に新教育行政法を出させていただいたわけです。もちろん、これが我々ベストかどうか、私たちはベストだと思って出していますけれども、どうぞ御議論いただきたいと思っています。我々も家内制手工業で頑張っているんですね、徹夜に徹夜を重ねて本当に。これ大変なんですよ、やっぱり野党で法律出すというのは、もう。 しかし、これ政府が教育基本法改正案出したのはいつですか、閣議決定して国会へ提出されたのは。 政府参考人(田中壮一郎君)本年の四月二十八日、閣議決定で国会に提出させていただきました。 鈴木寛君これ大臣ね、七か月たっているんですよ、七か月。 文部省本省の職員、何人いらっしゃいますか。 政府参考人(田中壮一郎君)文部科学省の定員といたしましては、二千二百人弱でございます。 鈴木寛君文部省がいろんな問題を抱えて大変なのは私どももよく承知をしております。しかし、我々は五名プラスアルファぐらいの陣容で、しかしやっぱり国会議員として、あるいは本当に日本の教育を何とかしたいという思いで新教育行政法を出させていただきました。 やっぱり七か月たった今日、政府が明らかに、大臣も、今の教育委員会でいいとは思わないということはこれ恐らく自民党から共産党までのコンセンサスだと思います。そこに、私は法案までとは言いません、明日にでも法案出していただきたいと思いますけれども、民主党が出すということはもう分かっていたわけですから、それにちゃんと対抗法案を出す準備してほしいわけですね。私たちがいたころはやっていましたよね、そんな野党に出される前に、本来。 だけど、まあそこは言いません。私は明日にでも出して議論すべきだと思いますね。これを突き合わせて本当にいい成案を得て、そのために、結局、地教行法だけで引っ掛かる部分があります、上位法として。概念的には上位法ですから、教育基本法。そうすると、今朝、憲法と教育基本法の整合性という議論がありました。教育基本法と地方教育行政法の整合も取らなければいけません。だから、地教行法と教育基本法は少なくとも連動させなきゃいけない。それは手続論の話を言っているんじゃないですよ、前とか後とか、もう今日はそういうことはもう全部置いておきます。そういう議論をする材料をやっぱり御提示いただきたいと思うんです。 で、法案はできていません。しかし、要綱はこうです、あるいはその基本的な考え方はこうです。で、もう審議会すっ飛ばしていいと思うんですよ。もう大臣が自ら筆を執っていただいたら非常に明快な教育基本法案できると思いますから。やっぱりその基本的な考え方だけでもお示しいただきたいと思うんですけど、それをいただかないと、というか、いただくことによって本当に議論が深まると思うんですね。 国務大臣(伊吹文明君)先ほどの、両方いいものがあれば、特に教育の問題であるから云々というお話があって、衆議院の現場のことを私は申し上げましたし、今先生がその細かなことはこちらへ置いておいてと。 私は、先生が民主党の党首になられたら、そういう話はすぐ進むと思うんですよ。ところが、衆議院でどういう議論があったかというと、内々検討したポンチ絵のようなものがあったんですよ。これは、あったというか、内々検討していると。これは私は立法者としては当然のことなんだと思うんですがね。しかし、衆議院でどういう議論があったかというと、まだ教育基本法が通ってないじゃないかと、その段階でこんなものをもう作っているじゃないかと、立法府を軽視するのも甚だしいじゃないかと。つまり、こっちへ置いておくことを、置いておかれない野党がおられるということなんですよ。ですからこの議論が深まらないんです。 ですから、私は、私との間のやり取りで、御党の松原先生、それから前原先生、藤村先生、三人と、この今、先生が多分思っておられる教育委員会の在り方だとか、その他、学校協議会その他についてずっと議論をしました。そのときに、御党の影の文部科学大臣である藤村先生が、お考えもよく分かったと、自分たちの法案も万全でないというところも、なるほどと思うところもあったと、今日の意見は非常に建設的であったとおっしゃっていただいたんですよ。私は非常にうれしかったです、そのときはね。これが国会なんだなと思いました。是非そういう議論をこれからもしたいと思っております。(発言する者あり)影のじゃないのか。何というんですか。明日の。ごめんなさい、明日の。 鈴木寛君その中身を是非お伺いしたいんですよ。これはもう、別に文部省とのすり合わせ、あるいはもちろん大きな方向性ですから、改めて大臣、やっぱり自分はこうこうこういうふうにした方がいいんじゃないかと、もちろん検討中のこともあろうかと思いますし、大体のお考えはまとまっていることあろうかと思いますが、そこをちょっと御披瀝いただきたいと思います。 国務大臣(伊吹文明君)これは衆議院で申し上げた程度のことで御勘弁いただきたいんです。失礼な表現ですが、私はやっぱり国会で指名を受けた与党の内閣の一員で、行政権は総理大臣ではなくて内閣にございますから、私は国務大臣として軽々なことを申し上げるということはやっぱり適当じゃないと思います。 私が衆議院で申し上げたのは、民主党の出しておられるこの人事権と措置権を合わせていくということ、これはその後ろにある財源の移譲、市町村間の財源の移譲その他、大きな問題がくっ付いておりますから、法律だけで解決できる問題ではありませんが、人事権と措置権はできるだけ一緒にした方がいいんじゃないかと。 それから、大変申し訳ないんですが、私は、都道府県知事あるいは市町村長に今教育委員会が持っている権限を譲るということは適当ではないと。これは、再三申し上げているように、国会は全国民に選ばれた議員から成っておりますから、国会で議決された法律、国会で指名された内閣はやはり全国民を代表して行動しております。もちろんそれでも、私たちは間違ったことは、絶対不当な介入はしないと思っても、そう思われる方がおられる可能性はありますが、それは法律で、それは司法の場で解決をしなくちゃいけない。しかし、地方の首長は全国民は代表していないんですよ。地方住民は代表していますから。 ですから、私はやはり特定の政党が推薦したり、だから東京都で、例えば学習指導要領を全国一律に出しておるわけですね。しかし、その学習指導要領を具体的に実施する権限というのは東京都教育委員会が持っているわけですよ。これのやり方に不本意だとおっしゃる方がいるから訴えがあったわけで、東京都以外では訴えは出ておりませんね。だから、やはり地方自治体の首長のイズム、やり方によってかなり違ってくる可能性があるわけですよ。教育委員会においてすらそうですから。ですから、私は、教育委員会はやはり残しておかないといけないのかなと。残しておくと、今言ったように、予算権、人事権、措置権、設置権、これはやっぱりきちっとした方がいいと。 それから、今度はこの未履修の問題その他も含めて、国と、それじゃ地方の教育委員会の関係をどうするかと。これは民主党案でも教育の最終責任は国にあるとおっしゃっておるわけです。西岡大先輩がお答えになったのも、学習指導要領は国がやはり基本的には発出するんだろうと。それをどう担保するかは附則において今後検討するということをおっしゃっているんで、そこは私たちと教育委員会、新たに改革された教育委員会と国の関係、あるいは民主党案で言えば、知事あるいは市町村長と国との関係は、この対象は違いますが、同じような実は考えでいるんじゃないかなと、こんなふうに思っているわけです。そんなイメージで少し法案ができれば、また国会へ、当然これは国会の御了解を得なければできないことですから、考えているということです。 鈴木寛君ありがとうございました。 それで、今二つのことをおっしゃったと思いますが、ちょっと後半の話から申し上げますと、大臣が、私どもが、やはり国が、最終的な責任でございますけれども、をというお考えに非常に、何といいますか、近いお考えを持っておられるということはよく分かりました。 それを前提に、これは今国会になるんですかね、通常国会になるのか分かりませんが、そうしたお考えを法案の形でお出しいただけるというふうに聞かせていただきましたけど、そのときに政府案の第五条で、要するに何を申し上げたいかというと、第五条の第三項、国及び地方公共団体とありまして、適切な役割分担及び相互の協力の下にその実施に責任を負うと書いてあるわけですね。これですと、我々はなぜ最終的責任という条項を置いたかというと、どちらか少し分からないあいまいな話というのはありますね、どんな制度論でも。そうすると、どちらか分からないときにこういうふうな制度設計と、バスケットクローズというか、要するに分からぬことはどっちかって決めておくという制度設計があって、我々は要するに白黒どっちのポテンヒット、守備範囲が不明なときはとにかく国が全部スイープすると、総ざらえすると、こういう制度設計が望ましいということでその最終的責任条項を置かせていただいたんですよ。 そうすると、大臣がそういうことでおっしゃるんであれば、ここのところはやっぱりそういうバスケットクローズというか、ポテンヒットになる分は全部国がスイープするというような制度設計であるということをちゃんと明記しておいた方がいいんではないかという思いで我々は入れているということですよ。 国務大臣(伊吹文明君)それは立法技術上の問題だと思います、先生もお役人を長くしておられたから。これは基本法であり、理念法ですから、ここに書いてあることは分担してやると。そして、国は学習指導要領のような基本的なものを決めると同時に、財政、もう三分の一に減っちゃいましたけれども、国民からお預かりしている財政支援を行うと。地方自治体は残りの部分を負担をして、そしてこの学校を設置し、今の状態で言えば人事権を行使すると。それに従って学校現場の校長に権限が譲られて、学校が動いていくと。こういう仕組みになっているわけですね。 この仕組みの中で、国というか、が教育委員会に対してどういう責任を持ち、そして責任を果たすためには、先生もよく行政官の御経験から御理解になると思いますが、法律の措置命令権、こういうものをどういうふうに担保していくかと。これは実はあったわけですね、御承知のように、十一年まで、平成十一年まであったわけですよ。ところが、教育長、都道府県教育長と政令市教育長の任命承認権と措置命令権が外れて一般法へ行っちゃった部分があると。だから、この辺の書きぶりによって、そこをどう担保していくかという立法技術もあるわけです。 ですから、そこへ明記をしておいた方がはっきりするというお考えは私は別に否定はいたしません。 鈴木寛君先ほど大臣がおっしゃった前半の方の話なんですけど、不当な支配をめぐる論争を私も聞かしていただきました。それで、さっき大臣がおっしゃった答弁はそのとおりなんです、と私は思います。で、それは、まあ国にとってですね、まあ国にまず法案の解釈権があると。もちろんそれは、しかし通達は、最高裁判例で法的な、最終的な解釈権は司法だ、これはもうおっしゃるとおりでございます。 しかし、議論のポイントはそこじゃなくて、要するに国なのか県なのかという議論じゃなくて、県知事が今その任命権者ですと、ああ、ごめんなさい、県教委、県の教育委員会が任命権者ですと。これをその市長とか区長にゆだねるというのが我々の案ですよね。 まず、どこが同じでどこが違うかというところを明らかにしたいんですが、大臣おっしゃっていただきました、正にその措置権者と任命権者と、それから、我々は実は、地教行法の二十三条で教育委員会の業務がだあっと書いてあって、二十四条で、これは首長の職務権限が書いてありまして、その第五号で予算を執行することが首長なんですね。ですから、措置権と設置権者と任命権者と予算権者というものは一体であることの方が機動的で具体的な対応が取れるんじゃないか、特にいじめのような緊急事態においてという考え方なんです。恐らくその辺りまでは同じだと思うんですけど、その制度設計のイメージとして。 そこからは、これは確かに議論があります。我々も大議論をしました。で、方法論は二つしかないんですね。我々が出させていただいた案か、アメリカのように、徴税権も教育委員会が持って、要するに、今、地教行法二十四条の五号で書いてある予算執行権、ここにアメリカの場合は徴税権も付くわけですが、財産税ということで集めて、そして当然設置主体にもなるし任命権主体にもなると。だから、こちら側に行くのか、それとも民主党案かという、大きく言うとこの二つしかないと思います、その三位ばらばらを一体にするという話になった場合には。 そこで、我々は考えました。どう考えたかということだけこの場で、いろんな委員の方々、逆に先ほど、大臣は政府の一員だからそれは案は出せない、それはおっしゃるとおりだと思います、自民党を始め与党の皆さん方に是非期待をしたいわけであります。であれば、是非自民党案を追加で出していただきたいということを、これ私は提案させていただきます。そうすれば、正にこの国会で議論ができますので。 それで、それはおいておきますが、そうすると、いわゆる教育委員会に徴税権を、あるいは予算措置権をもくっ付けた形で、任命権をくっ付けた形で、措置権をくっ付けた形でと、こういうことにしますと、これ大臣お分かりだと思いますが、地方自治法の大きな例外を作ると、こういう話になりますよね。そうすると、要は、ある人、だれかが責任持ってきちっと機動的にきめ細かくリーダーシップ取ってやれるようにしたいわけですよね、皆さん。それは恐らく変わらないと思います。 そのときに、地方自治法にそれだけの大きな制度変更というか例外のある種の体系を持ち込むということの法律上の難しさと、それから、を考えて、で、憲法上のいろいろな話もあります。しかも、徴税権になりますと租税法定主義の話も出てくるわけで、そこの大議論をやることと、私は中期的にはこれやっていいと思ってるんです。だからこそ、我々のその考え方は、そこまで、ちゃんと教育基本問題調査会のようなものをつくって、アメリカ型徴税権を持った教育委員会制度、これは地方自治の大構造改革みたいな話ですから、これは一国会ではもう済みませんよね。という話を御提起したんですけれども、それは難しいということであれば、少なくとも、今、今回お示しをしている案しかないのかなというところでの今日に至っているというところは、これは是非御理解をいただきたいということなんですが、逆に、大臣がそこのところは、そこまでやる御予定というか、あるいは逆に言うと、総務大臣とかあるいは総理と、あるいは今、塩崎官房長官いらっしゃいますけれども、内閣でそういう議論提起をもされるということをも少し期待させていただいていいのかどうか。 国務大臣(伊吹文明君)これは、先生、二つしかないわけじゃないんで、民主党も菅さんやその他の方々がイギリスの労働党を考えて第三の道があるとおっしゃった、正にその第三の私は道があると思うんです。 ですから、その二つの極端な例に分けてしまいますと、どちらもやっぱり欠点があるんですよ。特に、まあ教育委員会に徴税権までということになりゃこれは大問題になりますよね。そして、地方の自主性によって、教育を重視する教育長が出てきた途端に租税負担率がぼんと上がるというようなことはやっぱり適当じゃない。じゃ、地方の首長に任せればいいかというと、再三私がここで御答弁申し上げているように、やはり政治的介入とかイズムという問題が出てくると。 だから、例えば、国と地方と合わせて一つの行政をやっているのは国家公安委員会方式というのがありますよね。いろんなやり方があると思うんです。だから、いろいろなやり方を考えなければいけないんですが、これは単に教育行政だけでは論じられないですよね、もう御承知のように。その裏にある三位一体で動かした税源をどうするかということをも含めて、それから、県と市町村間の税源配分の問題等あります。何よりも、今教育というのは地方自治事務になっておりますでしょう、義務教育上。だから、先生の民主党案は当然それをお直しになるという前提ですよね。 ですから、そういうもろもろのことを含めて、やはり一番大切なのは、立派なことをやることも大切なんですが、現実を混乱させずに着地させるということがもっと私はこういう行政の立場にいると大切なものですから、先生のおっしゃった二つのところまでは踏み込む勇気は率直に言ってないということです。 鈴木寛君正にその第三の道というか、アウフヘーベンするために自民党なり与党のお考えを出していただいて議論したいなという、改めてお願いなんですけれども、じゃ現実論に立ち返ったときに、やっぱり今これしかないのかなということを私は思いました。 それはなぜかというと、結局、私も福岡とか岐阜とか、あるいはいろいろな北海道とかの事例を聞かしていただきました。あるいは、今日も教育長と教育委員長がお辞めになったようでありますけれども、結局、大臣は政治家と役人と両方やっておられる、私もそうでありますが、私は学者もやりましたが。 私、教育長さんにお会いしました、県も市も町も。残念ながら、教育委員会あるいは教育委員長、これは非常勤ですし、ワークしていない。ここはもう恐らく大体のコンセンサスだろうと思います。 そのときに、教育長さんが事実上その責任者として今現在おやりになっているんですけれども、今日の国会の議論でも明らかなように、やっぱり国民の代表として選ばれておられる大臣と、それから法律の枠組みの中で、国家公務員法に基づいて法律により忠実に仕事をしなければいけない役人と、いや、これ悪いと言っているんじゃないんですよ、これは役人の仕事ですから。それは当然踏み込み方というか、ある制度があったときにぎりぎりまで運用、それは国会議員にとって、あるいは大臣にとって法律は絶対守らなければいけませんけれども、法律とか制度の運用を極限までその現場にとって望ましい運用ができるのは、これはやっぱり政治家だと思う。なぜならば、我々は国民あるいは市民、県民、町民のために最善を尽くすというのが我々のミッションですから。それぞれ皆さんミッションに忠実に頑張っておられると思うんですけれども、しかし教育長とかあるいは文部省の担当の方は、それは大臣も私も昔はそうあったと思うんです、公務員のころは。ただ、むしろ昔の方が逸脱していた人が多かったのかもしれませんけれども、それはおいときまして。 そうなると、結局やっぱり、今回本当によく分かったんですけれども、いろいろ責められる。本当は人間としては、これはまずかったなと、おわびしないかぬなと思っても、そこで非を認めてしまうと法律上の責任論とどうなるのかなということがちょっと頭によぎるもんですから、ここで発言がもごもごとなるわけですよね。鈍るわけですよ、結局は。そういうことなんですよね。 まだ国会での議論は、それはいろいろ国会ですからあれですけれども、これが同じことが教育現場で起こっているんですよ。教育現場は一秒、一分、一時間たりとも待てないんですよね。やっぱりまず事前に、その制度はそうであれ、あるいは予算があろうがなかろうが、やっぱり緊急的にある種制度を超越、まあ超越、どこまで超越というのは難しいんですが、そういうことを機動的にできるためには、やはり民選による政治家と行政官とのやっぱり適切な役割分担。そして私は、最終責任は民選による政治家が担うということがそういう対応にとっては望ましいなということをやっぱり改めて痛感したんです。 今回、やっぱり町長さん、町議会議長さん、それから町の教育長さん、あるいはいろんな方会いました。やっぱり選挙で選ばれている町長さんとか町議会の方は、それは別に与党も野党も含めて、やっぱり一番、その中ではですよ、その中ではその御遺族とか生徒さんとか保護者の立場を代弁しようという思い、あるいはそういうビヘービア見えるんですね。だけれども今の教育制度が阻んでいるんで、本当は口出ししたいけれども口出せないよなという話になってしまっているということの中で、やっぱりその首長さんというか政治家が、民選がちゃんと最終責任を持つという制度設計は必要だということで提案させていただいているということと、そして、我が党案のその懸念すべき政治的中立性ということについては、教育監査委員会というのを設けて、オンブズパーソンのように、政治的に中立を欠いた場合にはやっぱりここできちっとその後で叱正を受けるということで担保をしましょう、それからもちろん選挙によってチェックをされるわけでありますし。 それから、もう一つは、教育委員会を入れた理由は二つある。これはまあ大臣も御承知だと。一つは政治的中立性の問題、もう一つはやっぱりレーマンコントロールということだと思います。レーマンコントロールの部分は、正に学校理事会で、学校現場にレーマンが入るわけですから、その保護者とか地域住民とかいうことで、その教育委員会制度がそもそも目指していた問題はきちっと手当てをしながら盛り込んでいる案だということはやっぱり御理解をいただきたい。 もちろん、それ、第三の道というかアウフヘーベンする道あっていいと思いますが、まあ今日は、そういうことをこれからもこの委員会できちっと議論をさせていただきたいということを是非お願いをいたしまして、大臣のこれからのこの議論を是非深めていく上での御見解を伺いたいと思います。 国務大臣(伊吹文明君)大変今日は充実した議論をさせていただきましたし、是非、もう先生はお読みいただいていると思いますが、今の例えば監査委員会的なものの選ばれ方、学校理事会と言われるものが実際はどういう形になったときには大変だなあとか、これ衆議院で先ほどの松原先生、藤村先生、前原先生と議論しておりますんで、その議事録も多分ごらんいただいていると思いますが、一度目を通していただいてですね。 それと、何よりのお願いは、先ほどおっしゃった中で国が最終責任を持つということを具体的にどう担保するんだということですね、法制上。これは御承知のように、予算権、人事権、法律の措置権のないところに責任は持てませんから、それをきっちりお書きになった上で、党内でそれで通るのかどうなのかということを再確認した上で一度お話ししたいと思います。 鈴木寛君再度お願いを申し上げますけど、私どもの藤村議員、松原議員、前原議員から御議論いただいて、既にもう一か月たっているわけですよ。 国務大臣(伊吹文明君)いや、一か月たってないですよ。 鈴木寛君いや、もう、だって二十、今日は七日ですかね。で、その間にあの議論があったんであれば、少なくともその大綱的なことをやっぱりある程度落とし込んでいかないと議論が、その次の議論できないわけですよね。 ですから、今日の御議論はその藤村議論と進んでないんで、私ども案を出しました。もちろん、まだまだ議論する余地あると思います。是非、これ自民党さんでも結構ですし、政府でも結構ですけれども、政府が出せないんだったら自民党にお願いしますが、それ是非出してください。そして、それを突き合わせてより良い案を作ることを是非大臣からも働き掛けて、あるいは委員長からも働き掛けていただきますことをお願いを申し上げまして、私の質問を終了させていただきます。 どうもありがとうございました。 |