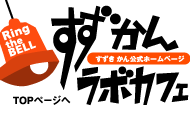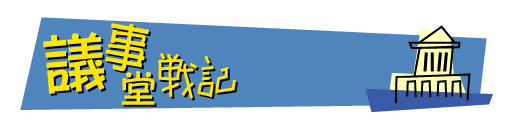2006年11月22日 教育基本法に関する特別委員会蓮舫君民主党・新緑風会の蓮舫でございます。 まず、佐藤委員の関連で、冒頭、伊吹大臣に一点だけ確認をさせていただきたいんですが、不当な支配、先ほど審議がございました。この定義を教えていただけますか。 国務大臣(伊吹文明君)まず、民意の反映というのは、やはり選挙によって民意の上に立って選ばれた国会が民意だと思います、最終的な。その国会で決められた法律と違うことを先ほど申し上げた特定のグループあるいは特定の団体が行う場合を不当な支配と、こう言っているわけです。 蓮舫君ありがとうございました。 次に、ちょっと今、私、資料をいただいて驚いたんですけれども、文部科学大臣にお伺いをいたします。 高等学校の未履修の状況ですけれども、十一月一日に政府・文部科学省が発表したのは国公私立合わせて五百四十校とありましたが、最新では幾つになったんでしょうか。 国務大臣(伊吹文明君)これは、衆議院の教育基本特で民主党の野田先生から再三御質問がありまして、三つのことを我々言われました。一つは、調査が漏れて、その後、新聞社の調査でいろいろ漏れているから、それをはっきりしろということが一点。それから、過去にさかのぼって高等学校の未履修のことを調べてくれと。それから、それが終われば、今度は中学校の未履修の可能性があるんならそれを調べてくれ。取りあえず、御指示のあった件についてやっと現場の教育委員会、知事部局から数字を、調査を依頼して、強制調査権はございませんから、依頼して取りました数字が多分先生の今お手元に行っている数字だと思います。一応、テレビが入っておりますので、私から口頭で御説明いたします。 まず、国立は二千八百二十六人の生徒がおりますが、これは前回の調査も今回の調査も…… 蓮舫君合計で結構です。 国務大臣(伊吹文明君)合計でいいですか。 まず、前回の調査では…… 蓮舫君ここですね。真ん中ですね。ここが、五百四十が六百六十三に。 国務大臣(伊吹文明君)ああ、ごめんなさい。ああ、学校数ですね。 蓮舫君はい、学校数ですね。 国務大臣(伊吹文明君)学校数は、十一月一日時点での学校数が五百四十校。国立、公立、私立合わせまして、これは五千四百八校のうち五百四十校。今回、もう一度知事部局及び都道府県教育委員会に尋ねまして出てまいりました未履修校が六百六十三校、百二十三校増えております。 蓮舫君ありがとうございます。初見だったんでしょうか。 五百四十校だとしていた未履修の学校数が二十日間で百二十三校増えているんですね。児童数はどれぐらいかというと、約四万一千人。新たに四万一千人もの高校三年生が未履修だった事態が明らかになっているんですよ。やっぱりこの問題もっともっと、調査を進めているとしているんですけれども、じゃ、すぐさまどういうふうに、文部科学省が指導していた学習指導要領がこれだけ守られていなかったという大きな問題の部分での審議も併せてしていかなければいけないんだということを改めて御指摘をさせていただきたいと思います。 今日から参議院での教育基本法改正案をめぐる審議が始まりました。冒頭、安倍総理大臣にお伺いしたいんですが、総理が掲げておられる教育改革、当然これ、私たちも大切だと思っておりますし、今ほど多くの国民の間で教育に対する関心が高まっているときはないと思うんですね。ただ、残念ながら、それは総理がおっしゃっている規範意識ですとか学力という問題以前に、いじめの自殺ですとか、未履修の問題ですとか、あるいはもっと前提にさかのぼると、政府自身が主導してやらせのタウンミーティングを行っていたんではないかという疑いとか、残念ながらまだ総理が目指しておられる本体の改革にはなかなかいっていないと思うんですよ、国民の声というのが。 そこで、お伺いをいたしますが、衆議院で与党が単独で採決を強行しましたが、そこまでして総理が進めたいとする教育基本法改正案、与党案が改正されたら、今保護者が抱えているいじめに関する問題、あるいはいじめられている子供たちの悲痛な心の叫びを解消することができるんでしょうか。 内閣総理大臣(安倍晋三君)教育基本法の改正は、新しい時代にふさわしい教育における基本的な理念、原則を定めるものでありまして、今個々に起こっている、例えば未履修の問題あるいはいじめの問題にこれはすぐに対応するための法律ではもちろんないというのはもう委員御承知のとおりだろうと、このように思います。しかし、この理念あるいはこの原則を定めることによって、新たに現在起こっている問題に、種々の問題について対応していくための制度あるいは法律の改正について議論を深めていくことはできると、このように思います。 例えば、このいじめの問題につきましても、道徳心を涵養するということもあるでしょうし、あるいはまた豊かな情操をはぐくんでいくという中において、このいじめという行為自体が恥ずかしい行為であるということを教えていくことにも私はつながっていくのではないだろうか、あるいは、いじめられている子供を傍観、他の子供が傍観をしない、それは正にある意味では公共の精神ということにも私はつながってくるのではないだろうかと、このように思います。 また、このいじめの問題につきましても、学校だけで解決する、できる問題ではないわけでありまして、保護者が一義的に負っている責任もあるでしょうし、また家庭や地域や学校が一体となって、教育委員会も含めてですが、対応していくということについての重要性についてもこの教育基本法の中に触れているわけでございまして、そういう意味におきましても、このいじめの問題に対応していくためのいろいろな原則についてもこの教育基本法の改正案には盛り込まれていると私は考えています。 蓮舫君今の安倍総理の御答弁ですと、確かに理念法を改正しただけではすぐさまいじめの問題に対応できないと、ただ原則は定めることができるということだったと思いますが、原則だけでは親御さんの不安ですとか、あるいは実際に困って悩んで本当に追い詰められているお子様の声にこたえることはできない。ここが私は政府・与党案と民主党案の違いだと思うんです。 私たちは、もちろん理念は大切で改正したいという気持ちは共有しておりますけれども、同時に、今ある問題に緊急性を持って政治が責任を持って対応するんだという姿勢で三法、新法を出させていただいておりますが、民主党法案提出者に伺います。 民主党の法案を提案された理由として、今の学校の問題にどうやって対応できるのかを端的にお答えいただけますか。 鈴木寛君お答えを申し上げます。 私どもは、正に今起こっているこのいじめの問題への解決の第一歩にここで行われている議論がならなければ、何の意味もないというふうに考えております。 例えば、衆議院で教育基本法の議論が行われている間だけ取りましても、実に九名の若いお命が自ら絶たれる、あるいは三名の校長先生が自殺をされるという痛ましい事件が続発をしているわけでありまして、本当に亡くなられた方々に我々は申し訳ない、そういう思いで一杯でございます。心からお悔やみを申し上げたいと思いますけれども、正にこの参議院の審議の中で、こうした問題に対して我々国会はどうしていくんだと、そういう議論を私は全力を挙げてさせていただきたいというふうに思っております。 私も、民主党のいじめ調査団の団長としていろんな現場を議員とともに一緒に歩かせていただいております。私どもは、いじめ問題解決のポイントは三つほどあろうかなというふうに思っております。 まず第一点は、やはり迅速な対応を、少しでも兆候が表れたときにやらなければいけないというのが一点。それから二つ目は、いじめの問題というのはケース・バイ・ケースでございます。したがいまして、やはりそのケースに応じてきめ細かな対応を綿密にやっていくということが第二点。それから三つ目は、最近残念な事件はございますけれども、やはり子供のことを一番愛しているのはやっぱり親御さん、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんです。そうした方々が心配、不安を抱えたときに、きちっと学校、行政の側がそれをどれだけ受け止められるかと。 こういう制度にしていくということがいじめ問題に対する重要なポイントだということで、我々は、今回の日本国教育基本法案、それから関連して出しました新地方教育行政法、教育振興法、この三法の中で三点のことについてうたわせていただいております。 第一点目は、民主党の日本国教育基本法の十八条、それから新地方教育行政法の七条で、すべての学校に学校理事会というものを設けるということを盛り込まさせていただいております。 学校理事会と申しますのは、保護者、地域、学校関係者、教育の専門家が入って、学校で起こった問題は基本的にこの理事会が解決をしていくと、しかも保護者と地域の方々が過半数を占めると、こういう機構にさせていただいております。 私も瑞浪に、岐阜の瑞浪の例を岐阜まで行ってお伺いをいたしましたが、お母様、中学校の二年生の女の子が亡くなられた件でございますが、お母様はもう兆候に気付いておられて、そして学校の担任に相談に行っておられるんですね。しかし、その相談がその中二の学年では検討されたけれども学校長まで上がってなかったと、こういうことであります。例えば、学校理事会があれば、こうしたときに十分に学校に対応してもらえなかった場合には、保護者代表の、大体副理事長になると思いますが、副理事長に直接この問題をきちっと対応してくれということをお願いに行けば、学校理事会がきちっと学校として動くということがこれ可能になるわけであります。 それから二点目、民主党の二点目は、これまた十八条の二項でございますが、やや文部科学大臣誤解されているところがありますが、我々は、現在の教員の人事権は、給料を県が三分の二、国が三分の一払っているということもありまして、市立とか区立の教員であるにもかかわらず、県の教育委員会が人事権者になっております。この人事権者を県の教育委員会ではなくて市長さんや区長さんに移譲をしていくというのが我々の考え方であります。知事に移譲をするわけではありません。市長や区長に移譲をしていくということでございます。 今回の例えば福岡の事例を見ますと、これは教員の子供に対するいじめを端緒とするいじめ事件というところでありまして、正にその教員の人事権者である県の教育委員会が初動をしなければならない。私は事件が起こりまして三週間たったところで福岡県の教育委員会にお邪魔をいたしました。しかし、この問題、私たちの感覚であれば、毎日徹夜をしてでも対応するというのが我々の感覚、皆様方もそうだと思いますけれども、福岡県の教育委員会は三週間にただの一回、しかも数時間しか開かれてないと、これが実情でございます。 したがいまして、親御さんやあるいは近所の方が心配があったときにその県の教育委員会に言っても、そもそも教育委員長は非常勤であります。基本的には教育長がその職務を代行しているわけでありますが、教育長はお役人であります。これ、我々もよく分かったわけでありますけれども、結局は組織の維持、自己保身、これに走らざるを得ないというのが、これは残念ながら実態であります。 私たちは、例えば福岡の事例で申し上げますと、その中一のときの担任に会ったんですかと、話を聴いたんですか、事情聴取したんでしたか、三週間たって一回もしておりません、それは入院されているということでありましたが。であれば、私から、病院に行かれて医師立会いの下でその事情聴取をされたらどうですかと御提案をしたところ、あっ、それはいいお考えですねと。 こういうのが県の教育委員会の無責任、形骸体制の実態でございますから、私どもは今回、そうした事案があった場合には、一番近い、正に市立小学校であれば市長さんにこういう問題を何とか解決をしてくれということをちゃんと言いに行って、きちっと対応ができる。今回も、町長さんは分かっておられるんですね。しかし、教育委員会の壁があるのでできないと、こういうことでございまして、正に今の教育委員会制度というのは形骸化していますし、保護者の皆さんからすると正に鉄の壁だと、ここをきちっと対応していきたいということでございます。 それで三点目は、先ほど来出ております国の責務でございますけれども、今非常事態です。全国で連鎖が起こっています。この問題を文部省にきちっと解決をしてくださいということを我々文教科学委員会でも申し上げました。伊吹大臣は、文部省にはその権限が十分に与えられていないという御答弁をされます。これ、正しい御答弁であります。 だから、ここを我々は変えなければいけない。そのためには、日本国教育基本法案できちっと国の最終的な責務ということをうたって、こうした問題については、やはり非常事態でありますから、全国連鎖を止めなければいけないわけでありますから、国が全面的にありとあらゆるこうした事態には対応できると、こういうふうな制度改革を具体的に盛り込まさせていただいているというところでございます。 |