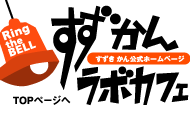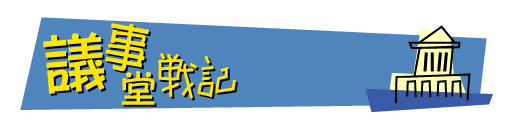2007年5月21日 本会議鈴木寛君民主党の免許法改革案の趣旨及び政府案との違いについてお答えを申し上げます。 民主党提出の教育職員免許改革法案におきましては、質の高い学校教育を実現をするためには、高い資質及び能力を有する教員が学校教育に携わることが不可欠であるとの認識の下に、教員の資質、能力向上のための具体策を綿密に検討し、盛り込んでおります。 すなわち、教員養成過程の改革案として、今後、教員免許については、教職大学院などで一年間の教育実習を経て修士の学位を取得した者に授与することを原則といたしてまいります。また、教員の皆さんには、教育実務に就いて八年たった段階で教職大学院において学び直していただき、学校経営、教科指導、生活・進路指導のいずれかの専門免許状をさらに取得していただくことを原則としてまいります。 当然、任命権者にも、大学院修学、専門免許状取得のための機会を教員に提供することを義務付け、修学のために現場を離れる教師の補充についても定員の確保を行うこととし、さらに、政府は特別の奨学制度を設けるといった内容としております。 このような機会がありながら、十年経過してもなお専門免許状を取得しない教員については、演習を含む約百時間の講習を義務付け、それを修了しない場合には免許失効といたします。 また、免許状の授与権者を文部科学大臣とし、教員に非行などがあった場合には、即刻、大臣の判断で免許状を取り上げることもできる制度といたしております。 政府案との違いですが、政府案では、教員の資質、能力向上を図る上で最も重要な養成課程の問題、つまり、現在、教育実習をわずかに二週間から四週間しか行われないまま年間二十万弱もの教員免許を交付しているという根本的な問題に全く手が付けられておりません。また、教員免許に十年間の有効期間を設け、十年ごとに三十時間の更新講習を行うことが盛り込まれておりますが、これは既にほとんどの都道府県で行われている十年研修を追認しているにすぎず、有名無実の政府案では教員の能力向上は全く期待できません。それどころか、世間の教師バッシングをいたずらにあおり、結局、現場教師のやる気をそぐだけの内容となっております。 核心の教員の修士化についてでございますが、政府・与党は、公立学校や国立大学の教員の純減を定めた行政改革推進法を堅持し、教育予算の抜本拡充を行わないことを前提に議論をしておりますので、その実現はそもそも目指されておりません。一方、民主党法案では、大学院修学で現場を離れる教員の定数補充と教職大学院の設置の妨げとなっております諸規定を行政改革推進法の中から削除をし、また、教育予算を対GDP比五%にまで引き上げることを党全体で決定をいたしておりますので、法律論からも予算論からもその実現は十分に可能となっております。 崩壊寸前の日本教育を立て直すためには、教育世界一を実現したフィンランドに見習い、全教員の修士号取得の必修化実現に向け、国民の皆さんの理解と合意を取り付け、必要な予算確保に財政当局をきちっと指導する政治的リーダーシップと気概が求められております。この気概の差こそ、政府案と民主党案の最大の違いでございます。 もう一問、子供に直接かかわる教職員定数増の必要性について民主党の考えいかんとの御質問をいただきました。 授業時間が日本より少ないフィンランドが学力世界一になっておりますその理由の一つに、全員修士号を持つ高い指導力を有する教師が日本の約一・六倍の割合で現場に多数配置をされていることが挙げられます。 政府は、従来、五年ごとに欠かさず行ってまいりました教員定数改善を行政改革推進法を理由に凍結をし、本来、二〇〇五年の年末に決定すべきであった第八次定数改善計画がいまだに宙に浮いております。 民主党は、さきの総選挙のマニフェストにおいても掲げましたけれども、OECD諸国の中で最悪の状況にある我が国の教員一人当たりの生徒数を、まずはOECD平均の初等教育十六・九人、中等教育十三・三人程度の水準にまで改善すべきであると一貫して主張をいたしております。 今回の法案提出に当たりましても、民主党提案の学校教育環境整備推進法の第六条に基づきまして政府が策定をいたします整備指針、第七条に基づき地方公共団体が定める整備計画において教職員数の増加やカウンセラーなどの充実についても盛り込み、あわせて、第八条においてその実現のために必要な財政上の措置を講ずべきこと、さらに、附則において、教員増の足かせになっております行政改革推進法の第五十五条の第三項、第五十六条の第三項などの教員純減規定を削除をいたしているところでございます。 教育改革の王道は、教育現場に優秀な人材を大量に投入し、子供に対してその力を存分に発揮してもらうこと以外にあり得ないという基本方針に基づき、今回の民主党教育改革関連法案を提出させていただいておりますことを是非とも御理解をいただきたいと思います。 以上でございます。(拍手) |